シナリオ詳細
<バーティング・サインポスト>ミロワールの迷宮に揺れる
完了
冒険が終了しました! リプレイ結果をご覧ください。
オープニング
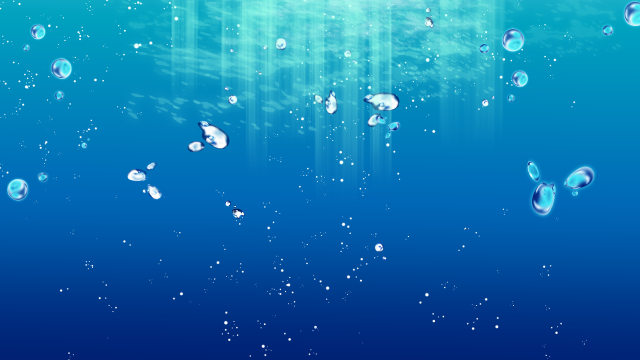
●かがみの少女
「ねえ、ミロワール。遊びましょう」
セイラ・フレーズ・バニーユはそう言った。
アフタヌーンティーを楽しみながら、他愛も無い会話を重ねるように彼女は言葉を重ねる。
「ミロワールが寂しくないようにしましょう。貴女も私も、どうせ後は『死ぬ』だけなんですから」
「ねえ、セイラは私とは一緒に居てくれないの?」
「ミロワール、貴女の姿すら知らない私に心中しろって言うのですか?」
ちら、とセイラが顔を上げれば、彼女の前には『自分と寸分違わぬ姿をした』女が座っている。所作も、そして、好んだ菓子でさえ全てが自分自身であると言うのに、口から毀れ出る言葉は幼い少女そのものなのだ。
「違う、違うわ。私は死にたくないの。
この病を背負って其の侭一人で死ぬなんて嫌だもの。救われたいわ、救って欲しいわ」
「ふふ、可笑しい。ミロワール。私にはそんなこと出来ませんよ。
そんなの――そんなの、出来たなら……! 『彼女』だって!」
「……ええ、ええ、そうだわ。愚問だったわね、セイラ。
それで、『可哀想なセイレーン』は私に何をくれるのかしら」
「ええ。ミロワール。――あのね」
「そう、そうなのね!
じゃあ、私にとっての救世主! わたしとあそんでくださいな」
●大いなる一歩
海洋王国近海にて海賊連合を下した事は記憶に新しい。そして、ゼシュテル鉄帝国によるグレイス・ヌレでの戦争をローレット共に跳ね除けた王国は未だ見ぬ新天地(ネオ・フロンティア)目指して外海『絶望の青』への航海をスタートさせた。
絶望の青。それを聴けばカヌレ・ジェラート・コンテュールは唇を戦慄かせ不安を浮かべ、ソルベ・ジェラート・コンテュールはそのかんばせを凍らせる。その海域は幾多もの勇者を殺め船を沈めた墓所であり、『絶望』の名を欲しい侭にする空間であった。
局地嵐(サプライズ)、狂王種(ブルータイラント)、幽霊船に海賊ドレイク、そして――貴族派有力貴族であるバニーユ男爵家の現当主セイラ夫人はじめとする『魔種』。恐れるべきは多く、敵が身内に居たという事実からも一筋縄では行かぬ航海であることをソルベたちは知っていた。
「お兄様、嫌ですわ。死兆――『廃滅病(アルバニア・シンドローム)』もあるんですのよ。
これ以上、皆を危険に晒すだなんて……それに、バニーユ夫人だって何かの間違いで――」
「カヌレ」
唇を噛み締めるカヌレは魔種オクト・クラケーンより齎された疫病を恐れ、これ以上の被害が出ぬようにと航海を控えて欲しいと言った。外海への進出が王国の悲願であれど、だ。
「カヌレ、それは今、廃滅病に侵されるイレギュラーズを見捨てるという選択だ。
廃滅病を治癒するためにはアルバニアを倒すしかなく、発症危険があるのは絶望の青に踏み込んだ全ての者だという……コン・モスカの祈祷だって『治癒』に繋がるわけじゃない。一時凌ぎだ」
コン・モスカ辺境伯による祈祷の効果がいつまであるかもわからない。ならば、アルバニアを一刻も早く倒して絶望の青を超えなければならないのだ。
命を救うため――ならば。
ローレットと王国に齎されたのは『アクエリア』と仮称される島であった。その島を足がかりにすれば、この先へと希望をかけられる。
拠点を得ることが出来なければいつまで経っても進むことが出来ないのだ。
『アクエリア』――そこには多数の『敵』が存在した。
アクエリアを攻略し、大きな一歩としなければならないのだ。
●『鏡像アクエリア』
アクエリアに設置された無数の鏡。魔的な気配を感じさせたそれからは狂王種がずるりと姿を見せる。
鏡を覗き込めば、その中には『寸分違わぬアクエリア』が存在していた。しかし、おかしなことがある。存在しないはずの狂王種たちが鏡の中を動き回っているのだ。
それは別世界か。鏡の中にだけ存在する場所があるのか。
絶望の青攻略時にファルケ・ファラン・ポルードイ一行が発見した『真実の鏡』の如く、その鏡の中には『異空間』が存在していた。
アクエリアに無尽蔵に追加される敵影を止めるべく、鏡の中に入らなければならない。
しかし、鏡の中は『異空間』だ。以前無人島で発見された鏡は魔種の手によるものだということが判明している。
あなたは鏡の中で自分が笑っていることに気づき、がばりと顔を上げた。
「ねえ、あなた。『ミロワール』の迷宮にいらっしゃい。
セイラが言っていたわ。死ぬ間際まで私と遊んでよ。ううん……あなたなら『私を救ってくれる』かもしれないんでしょう?」
あなたの口が、そう言った。
鏡の中に引き込まれる、そして、気づけば目の前には狂王種と『あなた』が立っていた。
「救ってくれるなら、私のところまで来てね。……生きてなくっちゃいやよ?」
振り向く。しかし、そこに出口はない。
目の前の『あなた』がにたりと笑っている。
「ねえ、出たいなら『あなた自身』を倒さなくっちゃ駄目なのよ?」
招かれたのだ。あなたは。
一先ず、狂王種を倒しながら出口を探そうではないか。
- <バーティング・サインポスト>ミロワールの迷宮に揺れる完了
- GM名夏あかね
- 種別ラリー
- 難易度HARD
- 冒険終了日時2020年03月17日 22時03分
- 章数3章
- 総採用数269人
- 参加費50RC
第3章
第3章 第1節
それは思い出の話だった。聞いて下さる?
私は*****という名前なの。闇の色の黒髪に、闇色の瞳。真っ黒の姿をしていたの。
それから、わたしには妹が居たわ。金の髪に、私とお揃いの闇色の瞳。対照的な光の様なあの子。
けれど、両親は私を可愛がってくれたわ。愛しい愛しい宵の子といって。
気味悪がられたのよ。それでも、大切な愛しい子って。ふふ、それでよかったの。
けれどね、かたわれはずっと愛されていたわ。
誰にだって愛されて――私は愛されないままだった。
一人ぼっちよ。友達もいない。両親だってきっとかたわれが愛しいの。
――あなたがいるから、あなたがいるから、あなたがいるから――!!!
だから、私は貴女を殺したわ。それから、深い海に身を投げたの。
もう、耐えられなかったの、愛されないことが。悪いお姉ちゃんでしょう。
ええ、そんな私がこの海でこの身を蝕まれたときに酷く怖かったのよ。
私ったら、貴女を殺しておいて! 一人きりなんて耐えられなかったの!
まるで鏡の様に同じことをしてくれた貴女を殺したら『私を殺す人はいなかった』もの!
いやよ。廃滅病で溶けて海に混ざるだなんて。
貴女の傍にいけないじゃない。いや、いやなの。いや――だから……寂しい。
……ああ、寂しかったのね。うふふ、ふふ。
寂しいだけなの。もう、誰でもいいわ。かたわれはもういないんだもの。
誰か、私と死んでくださる?
誰か、死ぬまで私の寂しさを消してくださる?
誰か、私の事を、愛して、慈しんで、嫉妬の魔種だなんてこと……忘れさせてくださる?
============
★プレイング冒頭にて
『鏡の魔種ミロワールを受け入れるor受け入れない』をご選択ください。
プレイングで選択された『数』によって『多数決』で物語が進行します。
【A】受け入れる
【B】受け入れない
をご記載ください。
また、本章は難易度がHARDとなっておりますことをご承知おきください。
============
第3章 第2節
その虚無の洞の中で、聞こえた少女の声を『受け入れよう』と手を伸ばしたイレギュラーズたちが居た。
彼らは皆、魔種であれど『ミロワール』の言葉に耳を傾けんとしたのだろう。闇の中、少女の気配が何処からか感じられる。
「そっか、そうだったんだ。妹をその手で……うん……けど、その行為を許すことはできないかな。
何があったとしても肉親に手をかけることはあってはならないよ。それはとても……とても悲しいことなんだよ」
唇を震わせて、スティアはそう言った。彼女のその声に「ええ」とミロワールが声を震わせる。それは拒絶の様に思われたのだろう――しかし、スティアは小さく笑った。
「でもね、一度は助けてあげたいと思った。だから私は貴女のことを助けるつもりだよ。
……でも廃滅病が治った後は戦うことになるかもしれないね。
私達と魔種は相容れぬ存在だからね、だからこれは今だけの馴れ合い」
「それは――許されるの?」
「うん。貴女と一緒に死ぬことはできない。でも、貴女の寂しさは消せるかもしれない……でしょう?
そして嫉妬の魔種であることも忘れさせるもできるかもしれないね。そう願うのなら戦うのが一番なのかな?」
魔種になって人を戻す術をスティアは知らない。魔種をそうでなくすための希望を、乞うたのは彼女だけではなかった。
「お前のやった事は許されない、許すつもりも無い。
けどよ、お前は悪人じゃねぇ。魔種でもねぇ。寂しいって泣く、どうしたら良いか分からなくなっただけの女の子だ」
プラックはそう言った。死ねやしないのだ。それでも、救えるかも分からないその存在を見過ごすことは出来なくて。だから、プラックは手を差し伸べた。それは友人同士がするように自然な仕草で会った。
「なぁ、ミロワール。俺と友達になってくれねぇか? そんでよ、お互いの話をしよう。
今までの事が嘘だったみてぇに、これからの事を忘れるくれぇにさ……好きな事や苦手な事だったり、想い出の話とかもしもの話でも良いな」
「お友達になれるかは分からないわ。もし、なんて言いたくないけれど……『もし』未来があったなら」
「未来、ね。もしもだったら……そうだな。俺さ、パン屋の息子なんだよ。
そんで、お前の家に配達に来るんだ。話してみたら気が合ってよ――毎日通う様になる、んで俺達は友達なってる……ってのはどうよ?」
涙を湛えたような、それでいて、どこか嬉しそうな声が闇の中に響く。くす、くすと漏らしたその笑みがあまりにも――切なげで。
「それって、きっと、素敵ね」
すすり泣きが響く。ああ、そんな未来――夢に見てもいいのだろうかと彼女は首を振る。
「スコーンが上手に焼けたねミロワール。……狂王種の邪魔さえなければもっと早く作れたのに。
美味しいねミロワール、本当に初めて? もしかして誰かと一緒に作ったことが昔あったり?」
柔らかに笑った史之の声にミロワールが唇を震わせた。もう、『覚えてはいない』のだとその声音に彼がここに来るまでに『見た愛しいあの方』の姿を見ても尚、対話の姿勢をとることを意外に思う様にミロワールは言葉を待った。
「俺も昔は寂しかったよ。だけど現金なもので今思えば意外と悪くないこともあったなって。
これをあげる。封じていた思い出の切欠になるかな。
昔のこと、俺にもっと話してみてミロワールがまだ*****だった頃の話をさ」
プレゼントを、とリボンをかけたそれを手渡した史之の手元よりそれが闇に溶けるように消えた。
ミロワールはそれを見つめてから「ママはお菓子作りが得意だったわ」とぽつりと漏らして、またすすり泣きを響かせた。
「愛して慈しんで寂しさを失う程甘やかすのはおにーさんとても得意でね。可愛らしいレディが望むなら全力でその願いを叶えよう」
ヴォルペは微笑んだ。内心との感情に『相違』があったとしても、それを悟らせぬ様に彼は微笑んだままだ。
「だからね、愛しい宵の子。君の本当の望みが知りたいんだ。
一人が寂しいなら傍にいよう、一人が怖いなら手を差し出そう――望むだけの愛をあげるけれど……君が本当に欲しいものは、傍にいて欲しい子は、」
ふるり、と闇の中で誰かが首を振った気配がして、ヴォルペは彼女を蝕む鎖を断ち切らねばならぬのだと感じていた。それは逃げだ。内心感じたその怒りを向ける矛先さえ失い、彼女が『死に絶えていく』それが許せやしないのだ。
「泡に溶けさせやしないよ」
「けれど、死ぬのはきっと同じね。愛されない悲しみにお姫様は涙して項垂れるのだわ」
囁くように、そう言った。その声を聴きながらシラスは小さく息を吐いた。酷く疲れていたのかもしれない、どうしようもなく彼女の声が離れないのだ。
次々に沸く狂王種を許すことは出来なかった。其れを許してしまうと、世界を喰い尽される事をよしとしているかのようで。ミロワールが作り出した鏡像だって打ち破った。手にかけてはならない人の影を引き裂いたその時に『帰り道を失った気』さえしていたのだ。イレギュラーズという使命感ではない、只管に嫌悪感が自分の体の中で巡っていたのだ。
「どうして、だろうな……『耐え切れなかった』のは同じかもしれない」
シラスは小さく笑った。彼女は自分の影法師だ。
妬ましかった――母が兄ばかりを目で追っていたのを。大切で、大好きで、世界でたった一人の兄弟。
「俺は、兄貴が母さんを傷つけることに耐えられなかった。だから……殺した? この手で? 分からない………俺は……」
言葉が漏れて、飲まれていく。そして、海の果てで死病に侵され消えていくのだ。何者にもなれないままに。
溢れた言葉に、ぼろぼろと涙が溢れた。膝を吐いたシラスは吐き気がするほどの悍ましさの中で、少女が泣いている気がしたのだ。
「そう、そう……あなたは愛されたかったのね。
片割れと同じものを貰えず、それを欲しがったのね」
フルールは、そっと、闇へと囁いた。それは『誰かになれず』『欲しがり』だった少女のわがままであったのかもしれない。闇を抱きしめるようにフルールは手を伸ばす。
「でもね、死は孤独よ。誰もその先を知らない。旅人さんの誰かは知っているかもしれないけれど、こことは世界の仕組みが違うから。だから、死後まで共に在れることはないのでしょう。
それでも、死に寄り添うことはできますから。そっと手を繋いで、覚めない夢へ堕ちる光になることはできるでしょう」
そこに、彼女は居なかった。怯えた様に息を潜め、静寂の中ですすり泣く幼子のような魔種。その気配を感じながらフルールは何時もの如く慈愛の笑みを浮かべた。
「もう、寂しくありませんよ。ええ、ええ。私がそばにいます。あなたを愛しましょう。
愛したくて、でも愛されなかった私もあなたに愛されたい。そう願って止まないのです」
「私は貴女を愛せるのかしら。貴女も私を愛せるのかしら?」
「さぁ、どうでしょうね」
ふ、と浮かんだ寂しげな笑みにすすり泣く少女の声は「ええ、そうね。誰もわからないわ」と呟いた。
「さぁ、眠りましょう、宵の子。覚めぬ夢の果てへ。子守唄を歌ってあげる」
「けれど、眠るのは怖いのよ」
首を振った。ミロワールと思わしき気配は啜り泣きを続けている。彼女が語ったその思い出をミーナは反芻した。
「……わかるようで、わからないようで。いや……私には、わかるな」
呟き、ミーナは狂王種を退ける。切り裂き、倒れ付した狂王種にミロワールが息を呑む気配をさせる。
「こいよ、悲しき娘ミロワール。お前のその命終わる時まで、この死神が、見届けてやるよ。
私は……今、この瞬間だけ。ミロワールを護る騎士となる!」
ミーナにとっても、何故そうしたのかは分からない。ただ、ミロワールの境遇に同情したのかもしれない。ミーナにも鏡写しの存在が居た。そっくりの母は天真爛漫で陽の下で微笑んでいた。花の中、楽しげに歩むような生活を送った愛らしい乙女――それと自身は対称的だったとミーナは小さく笑った。
「対する私は子供の時に攫われ、闇の下で血の塗れた生活だ……少しだけだが、わかるんだよミロワール。お前の事が」
「ああ、あなたも」
一緒だったのね、とじわりと闇が滲んだ。そこに彼女が居る事は分かる。しかしながら――『彼女は姿を現すことを恐れるかのように』自身を受け入れんとしたイレギュラーズ達に自らの声を響かせた。
それは、か細い少女の声だ。不安げなその声音は何処までも悲し気な気配を孕ませている。
彼女が語った通りの闇色の髪。それはこの虚無の洞にも溶けるような色なのであろうかと秋奈は小さく笑った。
「見て。髪の色私も黒よ。おそろいね。んー、これなら仲良くなれそう?」
「どう――かしら」
ミロワールのその声に秋奈は「そう簡単に分かんないわよね」とくすくすと笑う。
「寂しい? 寂しい? 私は寂しいわ。ぼっちだもの。妹がいた? 家族がいた? 僚機がいた?
だったら私が紛らわせてあげる。救ってあげる。……と言っても私、戦いの中にしか、私の存在する場はないの」
好き勝手に生きて、あっという間に死ぬ。それは途方もない輪廻の中にあって、そうして自分が戦って死んでいくことを秋奈は『当たり前』の事だと思っていた。
「言葉なんて意味をなさないわ。私は戦神だから。だから、一緒に死合いましょうか!」
「ええ、じゃあ、少しだけ待って。私という『闇』は少し……ナイーブなの」
囁くその声音と共に秋奈が縫い留められる。魔種は『少し誰かと話したい気分』なのだと小さく笑った。
「オレは魔種アイテであっても助けを求めて来るなら拒絶はしたくない。
ただ、オレに出来る寂しさを遠ざける方法は戦うことだけだけれどね」
イグナートは肩を竦めてから、「まずは、ありがとう、ミロワール」と穏やかに言った。その言葉が予想外であったのだろうか。ミロワールは「え」と小さく漏らしてからイグナートを見遣る。
「あの日に残して来た後悔と再び出会えるキカイがもらえるなんて思わなかったからさ。
今度はオレが借りを返そうじゃないか。キミがして来たことを赦すようなケンリも無いけれど、苦しさを、嫉妬を忘れたいって言うなら最期の最期まで付き合うよ! その場所から変わりたいってことなら幾らでもオレの命を削ろう!」
「同意です! 言ったはずです! 拙者はミロワール殿を救うと!
あ、ミロワール殿じゃないんでしたっけ? 名前あまり聞こえませんでしたがなんて言いました?」
ルル家が耳を澄ませればごにょごにょと名を告げる声がする。しかし、それは鮮明ではない。名を聞かれたことを喜ぶようにミロワールはくすくすと、笑った。
「まー、それはそうとしてですね! 廃滅病で死ぬ心配はありませんよ!
だって拙者がアルバニアのこん畜生を倒すからです! いやぁ……拙者も実は死兆ってましてね! 是が非でも倒さないといけないわけなんですよ!」
「貴女も、私と同じなのね……?」
「そうですね! まー、そうなれば、死ぬ心配ないので普通に友達としてやっていければなと思います!
一緒に死ぬより一緒に生きる方が楽しいですよ! 冠位だか何だか知らないですが、えらそうにふんぞり返ってるやつに生死を決められるなんて憤懣やるかたないじゃないですか!」
堂々と告げたルル家にミロワールは「私は魔種だもの。『アルバニア様』の味方なのよ?」と困ったように笑った。その声に感じた寂寞が、彼女が『そう』ではなかったのならば良き友人に慣れた気がしてルル家は肩を竦める。
「イルミナは……人のために作られたッス。だから……あなたがヒトだと言うなら。
助けろ、と。そう言ってくれるなら。その願いを叶えるために、動くッス」
イルミナは震えた声でそう言った。そうだ、人間のために作られた存在であるというのに――『ヒト』を否定することは出来なかった。
寂しいというならば傍に居る。イルミナが自身がそうすることで『ミロワール』が納得するというのならば、彼女と共に在るのだって悪くないのかもしれないと、そう感じていた。
「……どうせ、壊れた機械ですから。
一緒にいろ、えぇ。いつまでも一緒にいましょう。
救い出せ、えぇ。確約はできませんが、努力はしましょう。
……殺せ、というなら。えぇ、確実に。成し遂げましょう」
なんなりと、とイルミナは頭を下げた。その声にミロワールがひ、と小さく息を呑む。
「そうでないと……私の存在価値がなくなってしまう」
「それって、寂しいわ。とっても、とっても、寂しい……」
闇が俯く気配がする。誰かのために生きているとするならば、その『誰か』が居なければ自己を保つことが出来ぬという事が酷く寂しくて、酷く悲しいのだとミロワールは声を震わせる。
「知らねえよ。こちとら美少年のメッキを纏う気力も失せるぐらい疲れてんだよ。
身の上話なんぞに興味はねえし、誰をどんな理由で殺そうとどうでもいい。美しいボクを死なせる気もさらさらねえよ」
美しい笑みなど浮かべる事無くセレマはそう言った。苛立ちを露にし、そして、『セレマ』という自分自身を曝け出す。
「そも自分の欲望で現実を捻じ曲げる魔種が、可愛い可愛い片割れをこの世界に投影しないのはなぜだ?」
ひゅ、とミロワールが息を飲んだ気配がした。それは『自分自身でも想像したことがない』選択肢であり、自身の中では禁忌であったからだ。――片割れを作ったとしても、それは望みの通りの片割れにはならないからだ。
「答えは簡単だ。その気がないからだ。
死にたくないくせに生きようともしない。寂しい癖にただ待っているだけ。助かろうともしない奴が助かるわけねえだろ」
「ッ―――」
ミロワールはセレマの言葉をただ、只管に聞いていた。彼の言葉を否定することも出来ないミロワールにとって肯定することは自身が今迄やってきたことを否定されているかのようにも思えたからだ。
「……だが、ボクは魔性とも契約する魔術師だ。有用ならボクの物にしてもいい。
契約し、ボクの役に立て。キミの為にキミを使い、活かしてやろう。その気があるなら手を取れ」
闇が蠢いた。それをセレマは伸ばされかけた手を、下ろされたのだと感じる。躊躇いを孕んだミロワールが小さく呻いた声が確かに聞こえた。
「……ああ、やっぱりそうでしたね。貴方は。愛することは、出来ないかもしれません。
ボクには愛なんてわかりません。愛のために何かを捨てる気持ちも、人を憎む気持ちも、わからない。ですが慈しむことは出来ましょう」
そっと、ヴィクトールは囁いた。機械仕掛けの青年は自身の中には所在も不明の想いを辿るようにミロワールへと言った。
「……貴方が満たされ他の人が苦しまぬのでしたら。
『死ぬまで』愛されたいのでしょう? なら、貴方の願いは叶います。
ボクが貴方を愛している間に貴方は死ぬのです。最初から言っていたじゃないですか、ボクは『貴方(ぼく)』を殺したいって。ボクを連れて行きたいなら――連れて行けるものなら連れて行け」
それこそ、ヴィクトールが知っている愛であった。それこそ、ミロワールが想像した愛であり、自身ができる唯一であった。
その唯一を向けられて鏡の少女は闇の中で笑う。「ねえ」とまるで友人に囁くような声音で言った。
「その愛は、わたしには勿体ないかもしれないわ。だって、あなたにとっての唯一だもの」
「そっか。君は『優しい』のかもしれないね。本質的に、君は鏡像ばかり作って私達を直接害してはいないもの。
何も聞かず首を撥ねるのは嫌だなぁって思ったから……話、聞きに来た」
シキはそう、笑った。ヴィクトールに向けた穏やかな少女の声音があまりにも優し気であった事も相まって、彼女は普通に友人へ語り掛けるような声音で「あのね」と口を開く。
「私ねぇ、人の首を撥ねるたびに思うのさ。あぁ、この人にはどんな物語があったんだろって……元の世界では肩入れするなって言われたけど、今の私は自由だからね。
ねぇ、教えてよ。君の物語をさ。君の寂しさに付き合うから、私の好奇心に付き合ってくれる?」
そう、へらりと笑ったそれに闇が小さく動き、傍らに確かな存在を感じた。シキは闇を纏いながらもミロワールが傍らに腰かけたのだろうと、そう感じたのだ。
「やりたいことあるから一緒に死ぬのは嫌だけど、君の話し相手にはなれるよ。
武器は抜かないし、ぬくもりがあった方が安心するなら手でも繋いであげる…でもさ、ミロワール。ほんとに誰でもいいの? 君のかたわれとやらじゃなくて」
シキの手を握りしめて、ミロワールは首を振った。本当に寂しさを埋めたいというならば、イレギュラーズ達も、誰も、ダメなんじゃないかと、そう思わせた。
「きっと、貴方たちで、よかったのよ」
「わたしは、いつも、海のようでありたいと、願っていますの。
ありのまま、ただ横たわり、そこに生きる、すべてのものを受け容れる、海のように」
柔らかにノリアはそう言った。海はどのようにも表情を変えていく。大いなる母の様な、あたたかな世界。
「ちいさな範囲で見れば、生のよろこびを謳歌する、初夏の、満月の夜の珊瑚礁だって、恐怖と絶望にいろどられた、巨大な鮫の口許だって、ありますけれど。でも……全体として見れば、すべてを見まもってくれているんですの」
そんな海の在り方は魔種を受け入れる事を許容しているのだ。今や絶望を煮詰めたスープのようなその場所だって、すべての命を受け入れてくれている。
ミロワールすすり泣きを聞きながら「わたしは、あなたを、棘の様に、傷つけたくはありませんの」と静かに静かに告げた。ぽきりと首を折った椿の様に儚い少女の精神の脆弱性は、誰もの心に受け入れられぬという『彼女の思い込み』の上に成り立っていたのだろう。
「ボクもね、家族から愛されたかった。だからキミの気持ち、少し解るの。
他のヒトがどう云うかなんて関係ない。ボクはキミを受け入れます……ねえ『*****』、ボクと一緒に遊ぼうよ」
そっと、手を伸ばしたアイラはぎゅうとしましょうと闇を抱きしめた。そこにいるのだ、彼女は泣きながら、立っている。
「見てください。キミとボクは、似た髪の色をしていますね。
ああそうだ。ボクはアイラと言います。今日からキミの友達です! 一緒にたくさん、遊びましょうね」
彼女を眠らせてあげることこそが『あい』の形なのだとアイラは言った。ラピスはゆるりと頷く。彼女が受け入れるというのならば、ラピスは拒絶はしなかった。
「孤独も、何物にもならずに消えて行く事も、耐え難い苦しみだろう。
解る……と、容易く言いはしないけど。宵の子、君はとても美しいと僕は思う」
群青の宝石に金の星を散りばめた夜空の石。それは、ラピスにもアイラにも似ていて。闇色は美しく映るのだ。その宵に彩られた愛らしい娘。彼女が眠るその時が来たならば、穏やかな眠りが来ることを祈るようにラピスはアイラがそっと抱きしめたその存在に囁いた。
君が望む未来が、そこにありますように。アイラが『あい』するならば、自分だって受け入れる。いつか、愛するという、その意味を君が気づけますように――
「魔種というのは、なんて悲しい存在なんだ……あまりに哀しい声を聴き、心が揺れなくもない」
利一はそう、呟いた。『滅びのアーク』を蓄積する魔種はこの世界を破滅に導く。それは分かり切った真実で、特異運命座標とは相容れぬ相反する存在なのだ。「誰に味方するのか、どう生きるのかは、早退した問題ではない」と彼がギルドマスターに言われたとおりに、『鏡の魔種』のミロワールを受け入れることは出来なかった。
「……『妹想いの悲しいミロワール』でれば、受け入れたいと、思う。
とはいえ最後には……非情な判断をせざるを得ないかもしれないけどね」
それでも、彼女が幸福になれるのであれば、そう願ってやまないのだ。その存在が否定されるべきであれど、どうしてだろうか、彼女の事を――真っ向から否定する気にはなれなくて。
「俺は同情しない当然だろ。ここまで最悪な気分にしてくれやがってよ!」
キドーは唸った。しかし、魔種という存在がそういうものである事をキドーは知っていた。願いは歪み、器は捻じくれて――それでも『性質』が歪むだけで全てが全て引っくり返って別人になる訳ではなく、全てがリセットされて『彼女』が『ミロワール』として生誕する事も、兄と弟、そして仲間と両天秤かけて両方選んだ強欲なオクト・クラケーンがオクト・クラケーンの儘であるように。
キドーは掌に力を込めてから、歯を噛み締めた。
「聞けよミロワール、俺だって強欲なんだ。
それに、あいつの息子のせいで希望や奇跡ってやつに期待するようになっちまった。
よしよし可愛がりはしねえ。死ぬ気もねえ。最後まで俺は立ち続ける」
「――」
ミロワールは息を呑む。ああ、殺されるのだろうかと緊張したような彼女にキドーはゆっくりと息を吐いた。
「お前が目を瞑るまで、冒険いっぱいの三賊のお話を聞かせてやらなきゃいけねえからな」
「……ごめんなさい。私は貴女の望む『廃滅病で死ぬまで一緒に』いてあげられることは、出来ません。何故なら――そうですね、ローレットの皆さんを信じますから」
リンディスはゆっくりと頭を下げた。ローレットはきっと、どんな未来だって切り開いて見せるのだと、そう感じていたのだ。
「だから、貴女も治って死ぬ日はまた遥か遠くなりますから。寂しいからと自分の本を閉じず、次のページに進んでください。
自分から踏み出してみればいろんなことがたくさんで、『寂しい』なんて思える暇がないかもしれませんよ?」
「ああ、『きっと』――そうね」
涙の落ちる音がする。それは、有り得ない未来だと悲観しているのだろうか。リンディスは『そうした悲劇の主人公』が居る事を知っていた。
「そうですね。貴女は魔種ですから……きっと、知ることも無いのでしょう。けれど、私は知っています。ローレットだけでもたくさんの『人の生』という物語が満ちているのです」
リンディスの言葉に、ミロワールは「羨ましいわ」と呟いた。自身の物語を『憶えて居てくれる人が居たならば』、こんな――魔種になることはなかったのだろうかと、ミロワールの涙がポタリ、ポタリと落ちていく。
「ミロワール。あのさ、……いや、僕の知った事じゃないんだけど。
質問に質問を返すようだけど、それ、聞く意味ある? 僕がどう答えたって、君は結論を変える気なんて、ないんじゃないの」
ため息を混じらせてからルフナはそう言った。誰かの姿や声を借りるまでもなく、ミロワールはミロワールとしての意志や言葉があった。それは分かり切っているのだとルフナは呟いた。
「妹を殺したくせに自分は一人で死にたくないって駄々こねて、こんな迷宮作ったんでしょ。
なら、魔種なら魔種らしく、欲望に従って好き勝手すればいいじゃんか。僕は君と心中する気も、君を甘やかす気もない。……でも、君の意思や行動を否定する権利もない」
だから、受け入れるのだと、ルフナはそっぽを向いた。ふん、と鼻を鳴らした彼の言葉にミロワールは「そうね」と小さく囁いたのだ。
「ミロワール。そう言えば君に言ってなかった事があるのだ。
君が姿を隠すように、僕も本当の姿がある。……誰も愛さず。誰からも愛されず。ただ喰い尽すだけの『化け物』だ」
愛無の告げた『愛の告白』めいたそれにミロワールは「私だって化け物でしょう」と囁いた。
「だが僕は言った。『誰か』の代わりにはなりたくない。だが君は言った。私もそうだと。
君が本当に殺されたいのは。共にありたいと願うのは誰なのだ? 死ぬまで誰かの代わりを演じ。誰かの代わりを求め続けるのか?」
愛無のその言葉に、ミロワールは続く『言葉』を知っているように口を開き、重ねる。
それでは、あまりにも――寂しい。
そうだ、戦の中で命(あい)を謳う愛無は戦うことは何時だってできるのだと虚無の洞の中、影へと告げる。
「そもそもミロワール(鏡)などというのが出来すぎだろう。本名から教えたまえ」
「私? 私はね」
くぐもって、うまくは聞こえない。どうにも、彼女はまだ、決めかねているのだ。
イレギュラーズたちの言葉に惑わされまいとする少女の心と、
イレギュラーズたちの傍に居たいと『願ってしまった少女の心。
そのいずれもがぶつかり合っては意味をなさぬ問答を繰り返している。
――『有り得もしない未来を見る』それが彼女をまだ鏡像と闇の中に隠してしまっている。
リアはミロワールの言葉に、その雑音めいた響きの中に微かに流れた旋律が彼女の本質を見せているように感じ、嘘を告げているわけではないことを悟る。ならば――『別の形』で『別の世界線』で出会えていたならば、手を差し伸べられたのであろうかとリアは感じた。
今は魔種と特異運命座標。彼女が途惑い、闇に紛れるように。リアたちも『彼女に立ち向かうん迷』にあるのだから。
金の髪に闇色の瞳、ミロワールの『妹』を纏う様に旋律を奏でたリアは静かに声を震わせる。
「ほら、良く見なさいミロワール……あたしのこの金の髪を、この瞳を。
……あたしはこの旋律の持ち主のままに、お前を『受け入れる』。そして、お前の願いを叶えてあげる。お前が受け入れなかった妹の旋律を纏って、この手でお前を殺すわ」
そう言った、その言葉にミロワールは「きっと、それがいいのね」と囁いた。目を伏せて、最後まで幸福でいられるのならばそういう幸せのかたちだってあるのだと、少女はどこか予期していた。
――それが、魔種に許されるのならば。
「そうさ。僕たちは君が消えるまで寄り添うことなら、傍に居てあげることなら、できるんだ。
共に死ぬことはできない。一緒に消える事はできない。
……これから救えるかもしれない命を、僕が諦める事はできないから」
マルクは首を振った。彼女は魔種であり、世界と相容れず、世界に許されない存在だ。
しかし、彼女は同時に人間だった。その命が費えるまでを見守るくらいなら許されるのではないかとさえ、感じさせた。
「たとえ話だけどさ、家族じゃなくても、誰かが、君を愛していたなら、こうなる事も無かったんだろうか。……もう時は戻せないけれど、君が消えるまで、君を見ているよ」
「ええ、そうね。妹の事を愛していた村の彼や、彼女の親友の様に……私が信じられる人が居ればよかったんだわ」
ミロワールのその言葉にマルクは「そうか」と囁いて目を伏せた。彼女の命が費える終わりまで幸せを与えたいというのは独り善がりの強欲であったのかもしれない――それで、何か救えるなら、手を伸ばす事はきっと間違いではないのだ。
寄り添う様に存在した闇が、泣いている。リアはその悲し気な旋律に「ああ」と小さく呟いた。
「受け入れる、そうさ。受け入れよう……あ。ただ一緒に死んでなんて、心中は厭だよ?
それをするならもっとちゃんと、人を選んでちょうだいな。形ばかりの心中なんて、見苦しいばかりで何もきれいじゃない」
謡うたようにカタラァナは言った。
――ミロワール、あわれなあわれなおんなのこ。
「でも。その痛みを忘れたくて、終わるまで付き合ってというなら……ミロワール。
君の声を、もっと聴かせて。僕は君の声を聞くから。
そしてどちらかが終わるまで、ぐるぐる、いつまでも」
まるでそれはこの絶望の航海を共にするかのようだった。ああ、こんなことを言うとカタラァナは『かたわれ』が叱るのだろうかと考えて小さく笑う。残されるのは何時だってつらい物なのだ。
「そう……寂しかったんだね。それなら遊びましょう。お話しましょう。
寂しさを埋めることが貴女の救いになるのなら、私はいくらでも遊んであげるよ。何をしようか、どんな話がいいかな」
アレクシアはそっと微笑みかけた。話したい気分だと言った魔種はこちらを害すつもりもないらしい――少なくとも話が終わるまでは、だ。
「でもね、一つだけ。『一緒に死ぬまで』なんて言わせない。
この海に溶けてなくなるのが嫌ならば、そうならないようにしてしまえばいい……貴女に戦えって言ってるんじゃないよ」
「どうする、っていうの?」
「困ってる人がいたら助ける。それが私の役目だから。だから私は貴女と一緒には死ねない。だって死なないんだものね?」
アレクシアの意図に気づいたようにミロワールは笑った。廃滅病を退けるのは『大罪』を退ける事と同義だ。彼女にとってそれは有り得ざる未来であり、覚悟した死の向こう側に存在するのだ。
「くす、くすくす。有り得ないかもしれない未来の話だと思っておくわ!」
「今はそれでもいいよ。それに、生きてた方がきっと楽しい。
ほら、こうやってお話もできたしね? ふふ、私じゃ役者不足かもしれないけれど。だから、*****君も少しだけ『可能性』を信じてみてよ」
「ねえ……不思議ね。あなた達って『私のお願いを叶える為に自分が犠牲になってもいい』というのね。
他人が不幸な目に合わなければいいのかしら。それってすごくヒロイックで、すごく……『悲しい』わ。自分の欲求の為に『あの子』を殺した私とは真逆みたいなの」
闇の中で、アレクシアは確かに『彼女』を見た。闇色の黒髪は長く、揺れている。
闇色の瞳は悲し気な色を湛え、ただ、切なげであった。
――彼女は世界に救われない事に諦観しながら死した。
――私は世界に救いはないと諦観しながら生きた。
「貴女と私、まるで正反対に映る鏡ですね。だからこそ、貴女を受け容れましょう。
……貴女を一人、海に溶けさせなぞさせません。貴女の苦しみ、痛み、嘆き、怒り、あまねく全てを受け容れましょう」
そして、その刃で救うのだと無量は囁いた。無量の死生観の中で、死したものは仏の弟子となると彼女は告げた。死したものは生けるものに死というものを教える立場になるのだという。だからこそ、仏と呼ばれるそうだ。
「それは、人と寄り添い合う事と同義で御座いましょう。故に、死を恐れる事はありません。貴女は死した後、此処に居る者達と共に在るのです」
「寂しくはないのね……――『分かりやしない』なんて、言わなくて『有難う』」
囁くその声音と共に、その気配が闇に融けた。シラスの手をとる様に握った指先が静かに離れる。小指に約束するように影が纏わりふ、と消えた。
「ねえ、私がこの海で生き残ったなら――貴方の物にしてくれた?」
セレマに囁くように、ミロワールは言った。その声音はただ、幼子が親に縋るかのようにも感じられる。
「私のことを、忘れないで」
成否
成功
第3章 第3節
――そうして、優しい言葉をかけてくれる人たちは居た。
ああ、けれど『それを信じられない』のは魔種となった己が卑怯な儘に妹を殺したからだろうかとミロワールは囁いた。
「もしも、もしもよ。もしも……『私がみんなの友人になれたならば』」
そこまで口にしてから、彼女は目を伏せった。そして――有り得ない未来に希望を持つことに疲れたかの様に闇の中で一人、歩き出す。
「済まないミロワール……私はお前を受け入れることは出来ない。
お前に愛情を注ぐことは出来るかも知れないけど、一緒に死ぬことは出来ない。私はこの先もずっと、リゲルと一緒に歩いて行くと約束したから」
ポテトはまっすぐにそう言った。道を違える事無く愛しい人と前へ前へと進むことを彼女は堂々と宣言したのだ。左の薬指の約束と、願いを編んだミサンガを確かめてポテトは『闇』へと向き直る。
「海に溶ける前にお前のかたわれの元へ、お前の妹の元へお前を送り出す。一緒に死ぬことは出来ないけど、お前の本当の望みが妹の元へ行くことならそれを叶えたい」
金の妹は怒っているのだろうか。それを知る由もないけれど――妹が鏡だというならば、ミロワールは妹の元へと向かいたいと願うのと同じように妹だって待って居る筈だと、そう言った。
「だから、もう終わらせようミロワール」
「そうだ。……お前は可愛そうだな。お前は金の妹を愛したんだろ?
『鏡の様に同じことをしてくれた』ソイツはお前を愛していなかったのか?」
カイトのその言葉を『確かめるように』ミロワールは首を振った。嗚呼、どうだっただろうか――それさえもミロワールは忘れてしまったのだとため息を漏らすように言った。
「……俺は一人っ子だから、よくわかんねぇけど、きっと兄弟姉妹ってのは、仲が良かったんだろうな。まあ、もうわからねぇけど」
だからこそ、ポテトの云った通りカイトも『海の溶ける前に殺してやろう』と考えた。
「こんな趣味の悪い世界を作りやがって。自分自身を殺させ、好きな人を殺させる世界なんて、潰れてしまえばいい」
「私は彼女に殺されたかった――! 『あなた達が勝手に入ってきた』のに!」
その確かな声音がどこからか聞こえ気がして、アカツキは「うむ、しっかりと聞こえた」と頷いた。
「受け入れるも受け入れないも、相互理解はまず自己紹介からじゃと妾思うし……。
妾はアカツキ・アマギ! 炎を愛し炎に愛された炎の幻想種じゃ!! よろしくのう!」
堂々たるアカツキは名前からどうぞ、と勢いよく宣言するが――ミロワールが答えたであろう『名前』には靄かかってうまくは聞こえないのだ。
「難しい話は分からんが、要するに愛されたかったって話じゃろ?
だったら友達とか作ればいいんじゃないかのう。妾も思い切って燃やして外に出てみたらすぐに友達できたし……そう、燃やすのはよいぞ……焚火とか一緒に眺めてみるとかどうじゃ?」
あまりにアグレッシブな『深緑の禁忌』を堂々と宣言するアカツキはカイトとは対照的に楽し気に笑っていた。相互理解は魔種と特異運命座標という間柄では程遠い気さえさせるのだ。
「なるほど……魔種にも色々昔話があるもんなんスね。
アンタにも事情があるのは分かった、辛い思いをしたのも伝わったっス」
葵はそれでも『ミロワールの誘い』に乗る必要はないのだと肩を竦める。彼女は――ひょっとすれば彼女も理解しているのかもしれないが――我儘を言っているだけなのだ。
「オレには手のかかる妹と契約相手がいるんスよ。仮にも二人を手放してまでアンタを受け入れる気にはなれねぇんだわ。この答えが悪いと思わねぇし謝る気もねぇ」
葵が淡々と告げた言葉を聞いていたミロワールは「そうね」と囁いた。きっと、我儘なのだ。子供じみた我儘をそのままに内包したのがこの鏡。彼女は『セイラ・フレーズ・バニーユの誘い』でこのアクエリアに居る。そして、狂王種を生み出すための場所になっている。
寂しいは、悲しい。悲しいは、苦しい。
それは紗夜にとても判らない訳ではない。寧ろ、異色を宿した彼女はそれを理解しているのだと目を伏せた。
「古くは、愛しい、を、かなしい、とも詠むように……どちらも他人を求める痛みを、胸に感じて人は生きるのでしょう」
だからこそ、紗夜はミロワールを受け入れることは出来なかった。同じ悲しみや寂しさを抱いて同族同士で傷のなめ合いをすることは誤魔化しに過ぎないのだ。
「私は私であり、あなたはあなたでしかない。
慈しむことができないのも、やはり私であり、私が私である所以でもあるのです」
共に痛みを噛み締めましょうと、静かに言った彼女にミロワールは「ええ」と小さく呟いた。
「だから、ここからは我儘比べの我慢比べなのね。私が、強ければ私の我儘が押し通る。そういう事、でしょう?」
頷いたセリアはミロワールの話をじいと聞いていた後に肺の中の空気をすべて吐き出すように深く息をついた。
「愛されない、もっと言えば、自分に注がれるはずの愛が他人にしか向けられない気持ちは分かるわ。
わたしもあくまで集めた孤児の一人として実の父親から扱われてたんだし。
でも擦り切れるまで我慢したわたしと違って、あなたは行動した。嫉妬しそうよ」
もしも、受け入れたならば彼女が救われるというならばセリアは受け入れた。その『受け入れる』という行為がミロワールにとっての代替で、気を紛らわすだけであることが分かれば分かるほど受け入れる事ができないのだ。
「あなたが欲しかった愛はもう過去、二度と得られないものだもの。
愛は代用品じゃごまかせない。だから、わたしはあなたを受け入れないわ」
「欲しい物は、もう、ないもの」
囁くその声にアーリアは柔らかに笑みを浮かべる。それは大人びた笑みであり、そして寂し気な響きを孕んでいた。
「昔話をしましょうか。さっき妹がいるって話したでしょう? 私も、妹も、愛されていたわ。
母にも、父にも――二人目の父にも。でもね、妹は二人目の父からの愛を受け取れなかったの」
そして、そして。訪れた不幸は間接的に命を奪った。死ぬと分っていて受け入れるほどに愛していたというのに、『思い出』に囚われた妹は、父を忘れたように見えた未来に酷く絶望したのだ。
「貴女が寂しいのも、怖いのも、解るけれど。
でも私は『誰でもいい』なんていう子は愛しても慈しんでもあげない。だめよ、ミロワールちゃん。貴女はもう嫉妬の魔種なの」
首を振る。誰でもいいだなんて強欲を、許すわけにはいかなくて。ミロワールは「私は、嫉妬の魔種」と何度も繰り返す。
「嫉妬、ええ、ええ。貴女は悲しい方ですね。
妬んで、殺して、そして無くなった者を惜しんで寂しいと……? 自身で招いた結果ではないでしょうか?」
沙月は目を伏せる。誰でもいいとそう言うミロワールに『共に死のう』と手を差し伸べる者はいないだろうと彼女は告げた。もしも、そうだとしても『寂しがり』は満足しないはずなのだ。
「死ぬまでの間、貴女の寂しさは消してあげましょう。
戦いの中であればそのようなことを考えている暇もないでしょうから――そして貴女の望み通り、殺して差し上げましょう」
それこそが、ただの一つ。特異運命座標が為せる最も簡単な『攻略方法』なのだ。けれど、沙月はゆっくりとその様子を見た。
「あの世で妹へとかける言葉を考えておくといいでしょう。
それくらいの時間であれば待ってあげれますので覚悟が決まりましたら教えて下さい」
「優しいわね、とっても」
ミロワールは酷く寂しげに呟いた。いくら自分自身を『憶えて』『忘れず』『愛してくれた』としても、世界は自分を否定しているのだと闇に溶けるように少女は言う。
「優しい……優しいか。キミが『それ』を願うのは……少し遅すぎたかな。
キミは十分僕達に対して敵意を顕にして、散々鏡像をけしかけてきた……すまないね。一度は殺す気でかかってきた相手の頼みを聞いてやる程、僕は優しくないんだ」
シルヴェストルは最初に『彼女のテリトリーに踏み入れたことは悪かっただろう』とも告げた。しかし、それは『この世界に仇なす場所』であったのだから、断りを入れて踏み入れる事はできない。
「キミが最初から無害に振る舞っていて、かつ友好的な態度であったなら、また違った話が出来たのかもしれないね。残念だけど僕に出来るのは、精々死因を『廃滅病』から変更する程度だ」
海に混ざって死ぬというその事実から逃れ得る可能性。それこそが廃滅病以外の可能性だ。寂しさを紛らわせられるならば、それが一番なのだ。
「確かに、自分のすぐそばに、自分より輝いてる存在が比較対象として存在してたら、辛いよな。その気持ち、ちょっとはわかるよ」
風牙は確かめるように、そう言った。彼女がやったことは許されることではなく、妹を殺し両親の愛を裏切ったという事実は変わらない。
「お前は、両親の愛を信じなかった。誰も自分を愛さないというお前自身が、他者を愛さなかった。
一緒に死ぬ。死ぬまで寂しさを埋める。……はは、まるで将来を誓う恋人みたいだな」
愛しい人へと生涯を誓う様に。風牙は姿も見えぬ少女に首を振った。それは『誰かの代わりに語られた愛の告白』なのだ。
「そばに行きたいんだろう。なら、行かせてやるよ。お前の大事な人の『代理』としてな」
あくまで、花嫁をヴァージンロードの上で案内する事しかできなかった。それ以上の事は何もできないのだという様に、風牙が首を振る。
「ミロワール。貴女は…妹が大好きでしたのね。憎いほどに。死して共になりたいほどに。……たとえ殺してしまうほどの嫉妬心に駆られても。
寂しいのは苦しいわね? 孤独って人を追い詰めるもの。1人は嫌よね? 人は誰かと一緒でないと行きていけないもの」
ライアーは穏やかに言った。だから、受け入れない。知っているからこそ、『満たされない』
「『かたわれ』がいないのならそこはずっと空のままですわ。ミロワール。
片割れを喪ってしまった似た者同士。けれど私は貴女と違う道を行く。
だから――望むのなら、『貴女を殺す人になってあげる』わ」
その言葉にミロワールは喜んで、と言った。それが最善であることを彼女は分かっていた。わかってしまった。『優しくされたって』『無い未来を求めたって』『自分は魔種なのだから』知ってしまったのだ。
魔種。それが『戻せる可能性』がまだ、分からないことをメルトリリスは知っていた。
「貴方は、本当に欲しいものは手に入らないし、満たされない。何故なら貴方は嫉妬の魔種だから。
……貴方の境遇は悲しいもの、それは受け止める」
「家族に愛されていたんだろ? 大事な子って言われたんだろ?
どうしてそこで、家族と、妹と愛し合うことを選ばなかったんだよ…!」
アランは声を震わせた。そうだ。慈しみ、ただ、その愛の中で過ごしていればよかったのだ。彼女が、そうでいれなかった『狂った要因』がそこにあったとしても、だ。
「俺は知ってるさ。姉や父親が魔種になり、国からも責任を求められても、なお、前を向いて人を助けようとする奴を――メルトリリスっつー俺の最高の娘をな!!」
その信頼は確かな力になる。メルトリリスは堂々と、言った。
「ひとつ貴方を慰めるのなら、反転してしまったのは貴方の責任じゃないわ。
反転させるこの世界の仕組みがいけない。反転した人全てを私は否定しない」
聖女は静かにそう言った。アランが自身を信じてくれるというならば、彼女は胸を張ってミロワールに向き直れる。
「ごめんなさい。私達に貴方を助ける術が殺すことしかなくて、ごめんなさい。
私は貴方のために泣くことしかできない。
……あなたに誓うわ、いつか、この世界から反転を消すことを」
指を組み合わせ聖女は決意する。勇者になるが如く。この世界の優しさを伝えることが出来ないその悲しみを胸に宿しながら。
アランは負の連鎖を断ち切るがためにその剣の切っ先を闇へと向けた。魔種の宿す欲は終着点のない無限でしかないのだ。だからこそ、『彼女の欲を断ち切らねば』ならない。
「私はあなたや、あなたの作り出した鏡像とは戦いません。
……こんな悲しいこと、何の意味もないってわかったから、寂しいのなら傍にいます、友達にだってなる。でも、一緒に死ぬことはできません」
アニーはしっかりと、意志を感じさせるとの瞳をミロワールと思わしき闇へと向けた。蠢くそれを見つめる彼女の傍らで零は自身もアニーと同じくミロワールと戦いたくないと言った。
「死ぬのは無理だ。だが――お前と友達にはなれる。
パンに馴染みないなら……今度はギフトで普通に食える様上げてもいいし。それに、廃滅病で死ぬのが厭なんだろ?」
自分だっていやだと零はちら、とアニーを見てから言った。大罪魔種アルバニア。それを倒そう、と差し伸べる手を闇は取ることはない。彼女は『それに協力することが出来ないから』だ。
「どうする? もしお前が生きたいと望むなら『生きたい』と、言ってみろ……!
言えるなら、俺が……全力で生きれる様協力する。他の奴らにも頼みこむ」
「うん。あなたは確かに自分勝手な嫉妬心で許されないことをした。
あなたや私が死んでも、やってきたことは一生消えない永遠に残り続けるものよ。これからも残り続ける――だから、一緒にこの現状を打開しましょう……!」
アニーも手を伸ばした。零が言う様に、彼女が生きたいというならばそれを否定してはならないと。
闇は笑った。優しいのね、と囁くような声音を響かせて、どか切なげに笑っているのだ。
「まるで、子供の頃の俺を見ているようだ。間近に手を伸ばし、求めれば無償の愛で心を埋めてくれただろうに……それが出来ず、愛に飢えていた。とても可哀想な人」
ヨタカはそう言って、目を伏せた。愛しの紫月。そう視線を向けた『小鳥』はゆっくりと掌に力を込める。
「だがらと言って俺の大事な人を連れていこうと誘うのは決して許さない」
無理はしたくない。けれど、彼が――武器商人が居なくなるというならば頬を張ってでも引き止めたいと、そう思えたのだ。
「気の毒にねミロワール、嫉妬の娘。きっと世界中の誰が嫌おうと、かたわれだけはキミを愛してくれただろうに! キミの強欲が嫉妬に火を付けたんだね、愛しいなァ」
武器商人は笑う。傍に行ってみたい。何にでも忘れ溺れるほどに愛してやりたい――そうして忘却する事こそが、幸福で救いであることを武器商人はそう感じていた。
その手をヨタカがしっかりと掴んだ。逃がすまいと、そっと、握りしめられたそれが『彼を留める』。
「嗚呼、でもそうだ。おまえがいたね、小鳥。
……我(アタシ)の小鳥の傍に居ないと、キミは誰でもいいけど、小鳥は我(アタシ)でないと泣いてしまうようだから」
ユゥリアリアは小さく笑った。心中を求めてくるだなんて――あまりに、あまりに『面倒』で、そうするのは『あの人』が好いのだと心の中でそう半分以上は本気で思っていることに驚きながらも唇に笑みを浮かべる。
「心中は御免ですわー。メリルナートの家名にこれ以上傷はつけたくありませんしー。
それにわたくし、心中するならこの人と決めている人がおりますものでー」
ユゥリアリアのその声音は、優しさが滲んでいた。ミロワールの境遇に対して突き放そうとは彼女は思えなかった。一種の憐憫を覚えたともいえる。
「……第一、忘れられるわけないじゃないですか。一時的に忘れたとして、直ぐにそれは足元に這い寄ってくる。
だから、ここでもう終わらせましょう?その介添ぐらいなら、わたくし達ならできるでしょうから」
それは、最期の時を『与えてあげる』と言ったのだ。ミロワールは特異運命座標たちの提示した言葉の意味を飲み込んでいるかのように気を荒げる事無くただ、優しく微笑んでいるだけだ。
「ごめんなミロワール。俺はお前を受け入れられない。
……俺は元の世界で待ってる息子、梨尾の為に帰らないといけないから、お前と一緒に死ねない」
ウェールは緩やかに首を振った。その傍らでレーゲンがじいと彼の仕草を眺めている。
「同情から受け入れても。俺ではお前の悲しみを完全に消すことは難しいだろうから……。
ただな、ミロワール、お前さんが後悔しているなら、妹さんはきっと向こうでお前を待ってるかも知れない」
さよならと、ありがとうと、ごめんなさいを言う練習を。そう告げるウェールの言葉にレーゲンは何処か身に覚えがある気がしてゆっくりと昔話を辿る。
「レーさんは死にかけている友達の為に自身を犠牲にして治癒しようとしたっきゅ。
でも友達はそんなの嫌だと言って、レーさんは決断できず、友達は転生して待ってると言い残して魂が何処かへ行ったっきゅ」
そうして、自身が生きている。それは誰かの犠牲の上に成り立った未来だった。
レーゲンは自分が今、ここに立っているのは友人のおかげだっと認識していた。
「友達は一緒に前に進む仲だと思うっきゅ、一緒に死ぬ仲じゃないっきゅ!
傍にいなくても! 心でずっと想い続けて共にある仲っきゅ! だから今のミロワールは受け入れないっきゅ!」
死ぬまで友人でいてだなんて、レーゲンには受け入れられなかった。死しても尚、友人として傍に居て欲しい。そう願うのはきっと間違えではないはずなのだから。
「悪いが一緒に死んでやることも、ヴァレーリヤ……仲間を死なせることもできないな」
グレンはそう言って困ったように蠢く闇を見た。祈るように目を伏せたヴァレーリヤはええ、ええ、と何度も頷く。
「……貴女の気持ち、分からなくはありませんわ。『そうしなければ生きられなかった』のですわよね」
それは自分を『保つため』には必要な事だった。そうしなければ彼女は耐え切れず――罪だと言われど、罰を受けようとも、消えぬ過去であろうとも、『少女が自己を保つため』には必要だったのだ。
「ですが、それと貴女を放置しておいて良いかは別の話。
……グレンの死兆を治療する術を見つけるためにも、貴女にはここで死んでもらわなくてはなりませんの。どうか貴女の魂の行く先に、主は慈悲があらんことを」
ヴァレーリヤは分かっていた。彼女は魔種で。手を取り合うことが出来なければ『敵として現れた彼女』がアルバニアを味方し牙をむくことを。だからこそ、ここで斃さねばならぬのだと、分かっていた。分かりながらも、その行く先に輝かんばかりの祝福があることを願ってやまない。
「失ってからでも、気付いたんだろ? 『片割れ』がいたから、羨んでも寂しくはなかったのだと……誰でもいいなんて、そいつまで否定しちまうなよ。
自分の、妹の姿を忘れて俺達を模倣しようと、俺達は片割れにはなれっこない、誰かの代わりなんていない。精々、最期の瞬間まで看取ってやるぐらいだ」
グレンは呻いた。それはどうしようもない話なのだ。最後の最後まで、彼女を彼女として送ってやることしかできない。
「……今度は本物のようだな」
そう安堵したように言ったグレイシアにルアナははっとして顔を上げた。グレイシアの脳裏に過ったのは鏡像を攻撃することに躊躇はなかった筈ではあるが『大切な人』として彼女が現れたことだ。対するルアナはグレイシアの姿を見てその目に涙を貯めながら下手な笑みを浮かべた。
「やっと本物のおじさまに会えた」
「やはり、ルアナにも……ふむ」
ルアナの雰囲気から、グレイシアは確かに彼女の目の前にも自分が現れたことを感じていた。――それが、魔王と勇者という関係であるから現れたのだろうという妙な感覚を覚えながら、グレイシアは出来ればこの迷宮から出てしまいたいとルアナを見た。
「ここに来たからには、そろそろはっきりさせなきゃね」
「そうだな……元の世界に戻る為にも、此処で一緒に死んでやるわけにはいかん」
ゆっくりと、ルアナは頷いた。彼女は勇者として――そして、己の中で囁く誰かの声を聴き――堂々と宣言する。
「ミロワールさんの望みは叶えられないよ。わたしは元の世界に帰って魔王を倒さなきゃいけないから」
どんな理由があろうとも、争いを生む者を良しとはしないと『勇者』は決めていた。
――魔種であろうが、好々爺を演じる魔王だろうが同じこと。
そうとは幼い彼女は言わない儘、ただ、直向きに前を見据えていた。
「……そっか。寂しかったんだね。
それで、思いっきり優しくしてくれて、一緒に死んでくれる人を探してたんだね。……そっか、そっか。あんまり馬鹿にしないでくれる?」
ティスルは淡々と吐き捨てた。そうだ、ミロワール本人が言う通りの『我儘』の『我慢比べ』なのだ。そこで「はい、OKです」とおちおち死んではいられないのだ。
「代わりにアンタが死ぬまで遊んであげる。だから、紫髪の私でも金髪のあの人でもない、黒髪の『本当のアンタ』の姿でかかってきなさい! それくらいはできるでしょう?」
ティスルの傍で頷く気配がした。黒く、闇の色がずるりと『何か』を生み出していく。それが形を作る中で、クロバはミロワールと名を呼んだ。
「お前のやった事は確かに許さない。
だが、そこの根底に寂しさと愛されなかった悲しみがある事は確かに理解した」
理解することは出来る。ただし、受け入れる事とは違うのだと影が人の形となりゆく様子を眺め続ける。
「誰でもいいというのは違う。特に妹を手にかけてまで得ようとしたそんなものを”愛”とは言わない、言わせない。
でも虚像でも彼女を殺しただろって? だから愛されないんだバーカ。お前がいくら取り繕ったって真似できないものってあるんだよ」
真実はいつだって『ここ』にあると、胸へと親指を向ける。とん、と音を立てそこで音を立てる臓器が今迄歩んできた道を告げる。愛するべき人の熱も、思いも、失いたくない笑顔も――全部が全部、胸に大切に抱えている。
「来いよ『嫉妬』。目に見えずとも俺を繋ぐ愛(いと)、やれるものなら断ち切ってみせろ!
そして俺はお前が真に愛すべきだった家族の元へと葬(おく)ってやる!」
そう言ったクロバにミロワールはくすりと笑う。その笑顔が『見えた』気がして、作られ続ける影の形をただ、見遣った。
「ようやく会えたね。話を聞かせてくれてありがとう、ミロワール。
君の姉妹、家族。幸せな家庭にもなれたのに……どうしてこうなってしまったんだろう」
文は哀れだ、と口にしてから首を振った。歪んではいない、ミロワールはただ、ただ、まっすぐなのだ。自身の欲求に幼い儘のその心に。
「遊んであげようか」と手招いた。救いたいと語る事も出来ずに、けれど死んだ方が救いになるという本心さえ言えずに文は厄日だと呟いた。
黒い髪、黒い瞳、姉妹。娘と同じような容姿と年頃の相手というだけで文は酷く疲労を感じたのだ。
「……でも、そうっスね。アンタみたいな奴がいたってのを覚えとくくらいなら、してやれるっスかね」
葵がそう、呟いた言葉にミロワールは「ふふ、優しい人も多いのね」と困った様に、そう、呟いた。
そこには、黒髪の少女が茫と立っているだけであった。
成否
成功
第3章 第4節
「確かに、私は弱くて、甘ったれで……未熟者です。
ミロワール、貴女と同じく誰かを妬んだ事もありましょうそれこそ先の姉、そして兄も――」
どう足掻いても追いつけない人がいた。何も答えぬ鏡像に、刹那を感じた事だってある。すずなは静かに首を振った。目の前にずるりと姿を見せ始めた『闇』は少女の形を形作り続けているではないか。
「でも! そんな弱い私でも、姉を! 兄を! 殺したいなどとは思わなかった! だから――私は貴女を認めない。私が今を乗り越え、先に進む為にも!」
ゆっくりと刀を向ける。それが彼女なりの『乗り越え方』なのだという事をミロワールもわかっていたのだろう。
「さあ、殺(あい)し合いましょう。それが、貴女への餞です。
――だから、姿を見せなさい、ミロワール……!」
その声と共に少女がしっかりと姿を見せた。戦闘行動をとるわけでもなく、イレギュラーズ達の言葉を繰り返すように唇に乗せ、『何かを放棄したように』宙を眺める。
「いいえ、私は貴女を愛さない。私は貴女を許さない。私はサクラ・ロウライト。
この世全ての不正義の敵。貴女にどんな理由があっても、不正義を許す事はない……私が貴女に送るのは祈りの聖句だけ」
だからこそ、天義の騎士として、神の徒して、サクラはその剣を向けるのだと決めていた。
それに――嗚呼、これを不正義というにはあまりに酷だ。勘違いでの罪。それは万人に起こりえる事なのだから。ミロワールは一人ではなかった。彼女は誰かに愛されており、幸福であったはずなのだ。そう、なれなかった理由は『彼女が自分を愛せなかった』からだ。
「そして自分を愛しなさい。自分を愛せない今の貴女じゃあ、誰が貴女を愛しても、貴女は誰も信じる事なんて出来ないんだから」
だから――剣を以て『大切な人』の所へ送り届けるとサクラは静かに、そう言った。
「元々家族がいたにも関わらず、妬んで、自分から手放して……そして寂しいと……? 詳しい経緯はわかりかねますが、自分で行動して変えれば良かったのではありませんか?」
リュティスはサクラの言葉を続けるようにそう言った。人を妬み嫉み、他者のせいにし続けた。それこそがミロワールの罪なのだ。
「あの世で家族に謝罪してくると良いでしょう。
道案内は私が承りました。入り口までお連れすることを約束致しましょう」
その扉を開く事はしましょうと、使用人の装いをそっと持ち上げてリュティスは一礼する。淑女の礼はただ、美しく、信念が込められていた。
「始まりが如何に不幸であれ、不遇であれ。其れが他人を不幸にして良い理由になんかなりゃしないわよ。
無理心中の相手だなんてお生憎様。私達は生きる為に、生かす為に此処へ来たんだもの……目的も手段も最初から相容れないのよ。屹度ね」
ゼファーはそう言ってから目を伏せる。ああ、けれど。あんまりだ。
「愛して、愛されて。其れを語る場が命のやり取りの中でだなんて。
貴女も……本当に、辛かったわね?」
ゼファーのその言葉にミロワールは唇を噛んだ。辛いだなんて、言うことは出来ずとも――確かに、悲しかったのかもしれない。少女はあまりにも幼い。
(私の命は……人生は、もう私だけのものじゃない。肩を並べて生きるって、決めたんだ)
ウィズィは「だからお前にくれてやるわけにはいかないよ」とミロワールを見て、そして、後ろより聞こえた足音にゆっくりと振り返った。必ず同じ道に戻ってくることを信じていた最愛の人。だからこそ、その名を呼ぶ。
「そうだよね、イーリン?」
「ウィズィ、おまたせ。やることは分かってるわね?」
イーリンは柔らかにその声を発し、そして、常の通りの言葉を発する。
『貴方』はそこに居る。『私』はここに居る。『私』は『私』に言う。
「貴方が欲しいのはこんな、水底で朽ちていくだけの運命では無いでしょう。
見なさい『私達』はこうして飛ぶことができるのよ――神がそれを望まれる」
片翼では飛べないから。だから、二人ならばそれをも飛べるのだ。それはきっと、彼女だって同じだった。光の色をしたかたわれがいれば空だって飛べたはずなのに。
それは影との対峙か。のっぺりとした影――それは『物語』と己を称するオラボナの姿だ。その眼前には黒い髪と黒い瞳の少女が立っている。
彼女は何か迷う様に立っているだけだ。然し、それが『放置できない魔』であることをオラボナはよく知っていた。
「貴様は我等『物語』――否。私の事を如何に認識したのだ。何方にせよ。
傲慢の内に嫉妬を抱く己。拒絶以外の選択肢は存在しないのだ。解るのか。判るのか。
私は既に愛する者以外を愛せないのだよ。哀れな人間だと罵り給え!」
堂々たる彼のその言葉にミロワールは息を飲む。その言葉の中には確かな決意と、そして己が進むべき道の果てを感じさせる。傲慢たる嫉妬。強欲たる嫉妬。それは種別が違えど似ているのかもしれない、そうとさえ思わせる。ああ、彼も自分も愚かなのだとミロワールは小さく笑った。
「一緒に死んではくれないのね」
「えっ。いやですがっ? だって、だってですよ。
魔種であるあなたは、この世界の未来を妨げる要因にしかなりえないじゃないですか。
そんな存在をなぜヨハナが助けなきゃいけないんですっ?」
こてり、とヨハナは首を傾げた。本来的に意味が分からぬという様に目を丸くして。明るいかんばせを歪めてヨハナは「んー?」と唸る。
「そもそも、助けてもらうことしか考えておらず、自分で助かろうともしない方が、ここから出て生き延びたとして何ができるんですかっ。なにもできるはずないじゃないですか」
「ええ、それが『イレギュラーズがとると思った行動よ」
「成程。否定されると認識していたけれど、大いに肯定されて驚いているんですねっ。
倫理的にも実利的にも心情的にもあなたを助ける理由なんてありません。百害あったところで何の薬にもならないあなたは即刻ここで潰えてください。
それが未来を目指し今を生きる全ての皆様のためにできる唯一のことです」
ヨハナのその反応にミロワールはそうだ、この反応が『セイラ・フレーズ・バニーユ』が言っていたイレギュラーズなのだと小さく笑う。何故ならば、可能性を収集する彼女らは自身とは真逆の存在なのだ。
「『愛してくれ』だなんて、愛の悪魔としては応えてあげたいわ、そうじゃないと身体が治らないモノ……でも。嫌よ、なんで私が死ななきゃならないの? 貴女の業が呼んだ事でしょうに、嫉妬を忘れる事なんて出来ないでしょうに!」
利香は叫んだ。共に死んでと言われて手を取って、愛の悪魔が破滅する事なんて許されて堪るものか。
愛されたいなら愛してやれても死という絶対的な『独り占め』は愛の悪魔には許されない。「私は紅の終焉を勝手に迎えようとする阿呆を一人止めないといけないの」とそう言った利香へとミロワールは「貴女も、誰かがいるのね」と小さく呟く。人は一人では生きていけないから――なんて、誰かに言われなくても、ミロワールはもうわかっていたのだろう。
ああ、だからこそ――
「醜いことです。
――醜いことです」
薫子は呻いた。ぞ、としたように息を飲みまじまじと宵の色の少女を見つめている。
「貴女にできることは、ただ一つ。
その愚かで醜い本性を抱いたままに。そのおぞましき嫉妬を抱いたままに。――この場で死んで果てることだけでしょう」
唇から溢れ出たのは彼女への否定だった。愛を以て忘れるなど以ての他、自身の凶刃振るった相手の元に行きたいと願う事があまりにも醜く烏滸がましい。
「貴様が殺した全てを呑み込んで前に行くことでしか、手を染めた者には許されないのですから
人を手にかけた以上、死ぬときは手にしたの嘆きを抱いたまま眠るべきです」
例え、死した世界に『愛した誰か』がいたとしても救いを求めてはならぬ。その掌を握る事さえも許されない。薫子は宵の少女を見つめた。微動だにせず、只、薫子の言葉を聞いているだけのミロワールの表情は無そのものだ。
「自らの嫉妬(つみ)を、受け入れたままに死ぬべきです」
「ええ。彼女は、わたしを許してはくれないかしら」
「それは、どうであろうな」
鬼灯は首を振った。ミロワールの話をじつと聞いていた彼は同情しなかった訳ではないと口を開く。しかし――「結論から言おう。貴殿を受け入れることは出来ない」
『ええ、ええ、そうなのだわ。浮気者になってしまうもの』
ぷん、と拗ねたような台詞を並べる『嫁殿』に鬼灯は大きく頷く。そうだ、この命を捧げるべきは嫁殿だけで――嫁殿以外の女性を受け入れると言ったならばそれは嫁殿への裏切りであり、彼女の言葉を借りたならば浮気者だ。
「しかし、分かる。……辛かったな、親から愛されぬ事がどれ程辛いか。
貴殿も人の身だったのだ。嫉妬する事自体は当たり前だ。だが己の寂しさの為に他者を巻き込むなどはあってはならない」
「ええ……」
何度も、何度も、自問自答する事だろう。
――神様、私は間違っていたのでしょうか。
鬼灯は目を伏せて、首を振る。多くの者の心を弄び踏み躙り、そしてこの迷宮で怨嗟を渦巻かせてきたのだから。
「その罪は、償わねばならないさ。それがどれだけ寂しくともな」
どれだけ寂しくても。寂しいから、愛されたいから、ずっとこの儘。誰かを巻き添えにして消費して。まるで大衆向けのコンテンツの様に繰り返される情の事情。それが『ありきたり』であることをジルは知りながらミロワール「満たされない儘、満たされないと嘆くだけ。
「今まで向き合った誰かの事を直ぐに忘れてそのままっすか?
僕は、絶対賛同出来ないっす。前に進まなければ、その先を見なければ、駄目っすよ」
ジルは首を振った。停滞。それは水の巡りを濁らせる。心の巡りも命の巡りも全て滞っては汚泥の様に沈むだけだ。
「薬師の務めとしても、僕の心があるがままで居る為にも、足を止めて居る暇なんてないっすよ。セイラも引っぱたきたいっすから!」
「ふふ、セイラ――セイラをね。ええ、彼女は『我儘』だけれど、私と比べ物にならないくらい寂しがりなのよ」
どこか、愛おし気にミロワールがそう言った。それを聞きながらジルは彼女たちは皆、誰かを愛し、そして、愛されなかった殻なのだろうかと考える。
「寂しがりか。まあ、アレだよね。あんた、ホントは殺されたいんじゃないのかい?
できる事なら、片割れに。だから他人にも片割れを殺させるんだ。廃滅で海に溶ける前に、片割れのトコに行く為に……さ。遊んでほしいなんて言って、求めてるのはただの共連れだろう?」
『かたわれ』のところに行けなかったときに一人で寂しくないように――それが誰でもいいという発言の元になるというならば。悪趣味だとニアは呻いた。
「ホントさ、魔種ってやつは。間違ってるってわかってても、止められないんだろ。
見逃してやることだってできやしないんだ。なんたって『世界を破滅させる』んだから、さ」
眼前に立った黒髪の乙女。彼女は「そうね」と静かに言った。素直に此の儘眠っていくならばちょっとくらいは傍に居て――彼女を簿得てやることだってできるのだ。白い指先にさよならを、告げる事だって。
「きっと、混沌に来る前の俺ならあなたを受け入れてた。
愛されたい、寂しい……元の世界での俺もそうだったから」
黒髪に黒い翼が惨めで、輝く人達を羨んでいた。愛されるそれを見て、涙が落ちる事だってある――きっと、ミロワールだってそうだったのだ。ドゥーは柔らかに声をかける。
「……こんな気持ち、辛かったよね。
でも、俺は生き延びることで未来を掴んだ。あなたは自分の手で未来を潰した。
そんなあなたは愛せない。俺の可能性の一つみたいなあなたを……受け入れられない」
人生は洗濯を続けるものだ。何かを得て何かを喪っての繰り返し。ドゥーにとっては『自分が選ばなかった未来』に立ったミロワールが酷く、恐ろしいものに見えた。彼女は自分の鏡の様なのだから。
「あなたの事は忘れないまま生きていくよ。これが俺なりの選択で誠意だ」
「忘れないでいてくれるの?」
黒の中で白いかんばせがくっきりと浮かんでいる。唇が動き、それが震えていることに気づいたときドゥーは彼女は寂しかっただけなのだとそう、実感を強くした。
「『人は失ってからでしか、大事なものに気づけない』――大事な半身を自分で殺めておいて、寂しい……? 妬み嫉み……自分は、誰かにはなれへんのよ」
結局は別の人にも『誰かの大切なものに成り代わる』ことも、なれやしないのだ。蜻蛉は目を細める。女郎達にもそうしたものは居ただろうか。ああ、きっと――いたのだろう。
「寂しいから、誰かと心中したいやなんて、身勝手は受け入れてあげられへん
辛い現実を抱えきれんようになって、身を投げて……あげくこんな姿になり果てて」
蜻蛉の唇は「憐れな子」と紡いだ。まだ年若い彼女。その重責を拭うことは出来なかったのだろう。
「皆、大事な人がおるの……その人を残して一緒には死ねないの
やで、うちは……貴女を受け入れてあげるわけにはいかんへのよ、ごめんね」
「貴女も大切な人がいるの?」
囁くようなミロワールの声音に、蜻蛉は頷いた。妬ましいわね、と囁いたその声はきっと彼女の本心なのだろう。
妬ましいという響きを聞いたとき、彼女が魔種であることをハルアは実感した。受け止めてあげたいと、一時思ったその言葉は彼女の中では確固たる気持ちで会ったのは間違いではない――けれど、迷宮を進む様に彼女自身の心も揺れていた。
「ごめんね。あなたを突っぱねたり、優しい顔したり……ボクは嫌なやつだ。でも」
ハルアの唇が震える。そうだ、彼女の身の上話を聞いたときに分かったのだ――一線を越えたら戻ってこれないのだと。その身に沁みついた死の香が罰であるかも分からない。
「助けたい……けど、ボクにも越えちゃいけない境界があるんだ。
それが今で、破ればこのボクはいなくなってしまう」
気持ちを酌み交わすことなく表面だけで優しくし合う関係をハルアは友人とは呼ばなかった。そう思えばこそ、友人になると伸ばした手をそのままにはしておけなくて――ごめん、とハルアは繰り返す。
「貴女は、やさしいのね」
ミロワールのその言葉に、ハルアは唇を噛んだ。見遣った黒髪の少女は、嗚呼、今にも泣きそうなのだ。こんなにも、命が終わる気配を孕ませて、泣きそうに笑っているのだから。
「僕もさ、君と一緒に愛しあって廃滅病になった。けれど最期まで精一杯生きるつもりだよ。
元から寿命で先なんてそんなに無いけど生きることを諦めるつもりはない……命の価値は残された時間の長さじゃない。おかしい?」
ムスティスラーフは何処か照れ臭そうに少女に言った。まるで、友人へと語りかけるかのようなその声音は一緒にアルバニアを斃そうと誘っていた。
「僕からは君と歩む未来を、愛を与えよう。だから君も愛して欲しい、不埒な僕を。
愛ってさ押し付けるものじゃない。お互いが受け取れる物が愛なんだ」
「貴方が『鏡像(わたし)』を抱きしめた時に思ったわ。きっと――愛って酌み交わすものなのね」
私は独り善がりだったの、とぎこちなく笑ったミロワールから感じぬ敵意にムスティスラーフは唇を噛んだ。愛し愛され、そして、世界が回っていくならばよかったのに――愛されることが分からない儘、愛し方すら知らなかったのか。
「……お前にも姉妹が居たンだな、ミロワール」
「ええ、ヨハンナ」
レイチェルは、どこか彼女に妙な共通点を感じていた。それは愛しい妹を喪ったこと。しかし、その喪失には大きな違いがあることは二人の間に横たわる。
「大切さは喪ってから気付くモンだ。俺もお前と同じ廃滅病。海に溶けて、妹の元に逝けねぇのは嫌だ。だけど此処で一緒に死ぬ訳にはいかない」
海溶けて無惨に死なぬのならば。そういうレイチェルの声に「ヨハンナも優しいわ」と楽しげな声が返った。ああ、そう呼んだのは彼女が鏡像で『見た』からなのだろうか。
「なら、俺から出来るのは只1つ。ミロワール、お前を俺の手で殺してやる事だけだ。廃滅病で死ぬんじゃなければ、片割れの元に逝けるだろ? きっと」
「ええ、きっと。そうね。私たちができるのはそれだけだわ」
アルテミアは静かにミロワールを見た。妹だけが愛され、独りぼっちだった自分自身。孤独に耐えられなかった幼稚な心。それは納得と理解の上にあった。
「私、共感は出来ないの。それに、するつもりもないわ。
なぜなら、鏡像とはいえ、私に大切な妹をこの手で殺めさせた事を許しはしないのだから。それは貴女の得た苦しみと何も違わないでしょう?」
アルテミアは史に向かう少女を見て、静かに囁いた。己の苦しみを分け与える事は決して共生の手順ではないのだ。
「わたしには両親が生きてるのかもわからないし、そもそも最初から存在しているのかもわからない。寂しさは自らの行いの結果」
ココロは淡々と、そう言った。医学を志し進まんとした彼女には『感じる事のなき』寂しさ。あるかもわからぬその感情を確かめるようにココロは『心』に問いかける。
「海は人をひとりにする。望んでひとりになった人はひとりのまま、寂しさに満ちて、さらに満ちて、息もできずに海で死ななければならない」
だから、怠惰な儘で死を受け入れる事も、強欲にも共連れを探すことも認めることは出来なかった。
「わたしが助けるのは救われたい人だけ。あなたの救いの望みは口だけ。だから――救えない」
ベークは残る狂王種を斃しながら黒髪の少女を見て理解ができないと頭を振った。親もなく群れもなく、敵ばかり。孤独を感じるよりも明日を生き延びることが出来るかさえ不安であったベークにとって『ミロワール』は恵まれていた。
「嫉妬? 愛? 一人ぼっち? おかしなことを言いますねぇ、『両親は少しでもあなたを愛していたんでしょう』?」
杜撰だと言う。明日をも知れぬ暮らしの中、この絶望と廃滅の海を越え、果てに何があるかを見たいとさえ思っていた。だからこそ、立ち止まるわけにはいかぬのだとベークは『王国の威信』を背負う様に宣言する。
「愛されたいだけなら海の底で蒙昧の者とでも語らってればいいじゃないですか。
死ぬなら一人で勝手にどうぞ。僕だって、この蒼に身を窶した時点でその覚悟はしてきましたよ」
エクスマリアは無理だと首を振った。彼女にとって魔種と手を取り合う特異運命座標は『あり得ない』とまではいわなくとも、そう起こる事のない未来だという認識が当た事もある。それは廃滅病(アルバニア・シンドローム)が蔓延する只中では確率はゼロに近いのだ。
「ミロワール。鏡像に隠れ、己の顔も晒せぬ、哀れな魔種。マリアの手は、お前の手を取ることは、出来ない」
その病が根絶されたならば、手を取り合うこともできるかもしれないとエクスマリアが告げた声に、ミロワールは何処か来たいと絶望と不安を混ぜ合わせたような顔をして何かを言いかけ――
「よく わからないわ そのこをころしたって あなたが あいされるわけでもないのに
どうして ころしてしまったの? どうして じぶんでころしておいて さみしいだなんて いうの? あなた じぶんかって ね」
「ええ、そうだわ」
ポムグラニットにミロワールは言った。寂しいなら殺してあげる。慈悲もなく――そして、真正面から飛び出したその言葉にミロワールは怯えたように指先を振るう。
「あら」
痛みを感じる事はないが、赤いというのは分かった。それがミロワールによる拒絶であることをポムグラニットは知る。
「しねば さみしくないわ?」
「ええ、けれど。分からない儘殺さないで。いやよ、いや。それって『私と何が違うの』」
赤が滴っている。それを見てポムグラニットの体がぐらりと揺らいだ。
「分からないのが厭か。なら、教えてやろう『魔族』は皆殺しだ」
ハロルドは一貫してそうすることを決めていた。誰かを害することに慣れた人間は魔種と何ら変わりない――それがどうしたとハロルドは嘲笑した。
「平和な世界に俺のような存在は必要ない。もといた世界でもそうしたように、貴様ら魔種を皆殺しにしたら別の世界へ行く方法を探す。
人々に平和を齎し続け……そして、この身 朽ちるまで戦い続けるためにな!」
「貴方、狂ってるわ!」
「お前だったそうだ。魔種になる前にお前も破綻していた!」
ハロルドのその声と共にミロワールは怯えたままに攻撃を重ねる。魔種。それが脅威であることがその身をもって実感されるが、ミロワールは『イレギュラーズの言葉で本気で殺しに来ていない事』は分かった。
「まるで、我儘な童に御座るな……付き合い切れぬで御座るよ。そも、愛とは求めるものに非ず。差し出すもの也……それが分からず、与える事をしなかった者が今度は欲しいと? 主は、拙者達を笑わせにきているので御座るかな?」
幻介は寝言は寝てから言えとミロワールへと斬りかかった。彼女の物語は片割れを殺し、己を闇に落とした時点で終わっているのだ。まやかしに惑わされるほどに甘くはないと振り翳したそれをミロワールが反撃を返す。
「どうやって、愛せばいいの? 私はそれさえ分からなかったのに!」
「それこそが貴様の罪。……決して償い切る事の出来ぬ贖罪よ。
主は今、此処で拙者達に斬られる。そして、その行き先は―――地獄で御座るよ!」
幻介の体に叩きつけられた一撃が、重たく圧し掛かる。骨の軋む気配に、彼は僅かに呻いた。
「……ワタシも廃滅病にかかっちゃったけど、最後まで諦めるつもりはないよ」
芽衣は声を震わせる。ゆっくりと顔を上げたミロワールを見据え、『人を害する者』を厭う様に芽衣が狂王種を撃退していく。
(さっきより数が減った……?)
そう感じたのはきっと、間違いではなかったのだろう。
「お前の過去なんざ知らねえよ。魔種に堕ちた時点で、『嫉妬』に狂った時点で、もう俺達とは相容れねえんだよ」
グドルフの言葉に、きゅ、とミロワールが唇を噛んだ。それがどうしてなのかは先ほどの行動から分かる。寂しがりは誰かに心を傾けなければ『まともな判断能力』もないのだ。突如としてハロルドやポムグラニットに攻撃を繰り出したのもそう、否定された瞬間に怯えが覗いてくる。
「てめえはそのちっぽけな愛で満足してりゃ良かったんだ。――いや。もう、今更何を言っても無駄だな。お前は間違って後戻りできねえ所まで来ちまった」
「もう、戻れないのかしら」
グドルフにそう、問いかけたミロワールは「私は『理解もされない存在』なのかしら」と攻撃の手をやめて呟く。
「さあな。少なくとも『お前は魔種』で『俺たちはイレギュラーズ』だ」
ミロワールとカンベエは少女を呼んだ。静かな闇の中で、見つめた彼女は確かに闇だ。宵の色をした寂し気な存在ではないか。
「お前は殺してしまった、鏡写しの自分を欲しているだけだ。
その胸の黒洞洞たる虚を埋められる存在など最早この世にはいないと……とうにわかっているのだろう……もはや取り返しはつかぬと」
首を縦に振ったのは『戻れない』事を自分でも理解していたからなのかもしれない。死の定めから掬い上げてやりたいと願うイレギュラーズ達が居る事もわかっていた。気づかいや同情、慰めでミロワールに躊躇いを与えた者達が居る事だってわかる。しかし、カンベエは『自分なりの結論』を持っていた。
「お前がここにいては、片割れの光もくすんでしまうぞ」
光はいずれは消えてしまう。しかし、闇とは常にそこにあるものだ。カンベエができるのは影の様に自身に寄り添うであろう『闇』を覚えておくことだけだ。
「約束だ。全力を以ってその悲しみごと叩き切る」
「きっと――それが、いいのね」
諦めを孕んだその言葉にカンベエは唇を噛んでから頷いた。
「……そう。君にも、おれと同じで…兄弟がいたんだ、ね。鏡像の時とは……また、違うけれど。…君は…おれと似ているところ、あるの…かも」
チックは静かに、そう言った。寂しい、傍に居ないと、と思う彼女。警戒を露にしてイレギュラーズを見遣るミロワールにこてり、とチックは首を傾ぐ。
「……本当は、かたわれの事。好き…って。思ってた?」
「――すきよ」
唇が、震えた。かたわれの声が、海の底より響いている。泡の様に、静かに立ち上って、名を呼んでいるのだ。
「傍に逝きたいと、願うなら。手伝う事は……して、あげる。
……でも、叶える……する事は。駄目。それは……鏡像に、言った通り。一緒に死ぬ……のは、君じゃない……から」
ミロワールの体から力が抜けた。その様子にグドルフは『理解されず意味もなく、記憶にも残らず死んでいくこと』を斯様に恐れているという事だけは分かった。彼女は理解できないという言葉に、異様に反応して駄々をこねていたのだから。
「そうだったんだね。死ぬことが怖いんじゃなくて……寂しいのが怖いんだね。
なら、病気で終わる前にキミを終わらせるよ。大切なヒトを嫉妬で失くして、一人ぼっちで寂しくても、ひとつでも救いがあるように」
アクセルは優しく、そう言った。共に死ぬことは出来なくとも、妹がいるよとその背を押してやることは出来る。それが『少女の求めた最善』の為なのだ。
(共感はできないが理解はできる。
少なくとも俺はあの視線を知っている……いや、厳密には同じではないか)
エイヴァンはミロワールの事を理解できれども共感できなかったのは『当たり前』にあったはずの事が、ミロワールにとっては当たり前ではなかったのだろうと感じていた。
傍から見れば些細な違いだが、と尾人から見たならば気の遠くなるような、そんなものだ。同じ親の元で、同じ時間を過ごしたって、きっと――別物になるのだ。
それが誰の事とは言わず、エイヴァンは唇を噛み締めた。
「君が見せてくれたのは――そうか」
雨月は唇を震わせた。ミロワールの周辺に存在する鏡に映り込んだのは彼にとっての大切な友人だった。一度は諦めてしまった人生に再び炎を灯してくれた命の恩人たる彼――それを殺すなんてできない、と雨月は掌に力を込めた。
(コレは彼じゃない……彼のように勇気や情熱や希望なんてない。彼の形を借りるだなんて卑怯だな)
卑怯だ、と思えど。敵であれど救いたいと願ったのは本当なのだと雨月は鏡像へと聖なる光を放つ。
「君は……分かっているのかもしれないね。誰かを傷つけてしまうこと。それは肉体的なことではなくても、どんなに深く悲し理由があったとしても決して許されることではないんだよ。
だから君を受け入れることはできない。ごめんね――君は一人なんかじゃない筈だよ」
イレギュラーズが彼女を斃したとして、廃滅病で海に溶けて消える前に彼女を『光の妹』の元へと送り届けられたならば、きっと、そこでは妹が笑って待って居る筈なのだ。
「止まない雨はないんだよ」
そうだ。此処に降る雨は優しく、そして哀しい。縁はその横顔が幼い少女に見えてぐ、と息を飲んだ。
「……悪いな、嬢ちゃん。お前さんと一緒にいてやることはできねぇよ。
少し前までの俺だったら、いくらでも付き合ってやれたかもしれねぇがね」
停滞より進む理由を手に入れた。小指に絡むような赤い糸は二つ。死なせたくないと願うものが二人いる。
絶望の只中で、彼女が身を堕とすほどの絶望を自身も味わい、もう一度向き合うことをリーデルに言った。誰よりも寂しがりであった彼女を昏い海の底へと沈めた自分自身――今度こそ、その手で引っ張り上げてやらねばならないのだ。
「俺はな、必ず帰るから待っててくれと、大事なやつに誓ったんだ。
俺はこのまま廃滅病で死んだって構わねぇ。こいつは今まで逃げてきた俺への当然の罰だ」
でも、違うのだ。『彼女』は自分と同じ場所に立つと同じ呪いをその身に受けてまでも尚、ミロワールの前に立っていたのだから。
「まるで、違うな」
ジェイクは笑った。それは『夜の蝶』なんかではなかった。美しい夜の煌めき。それこそ、彼の愛する只の一人。
「海に混ざるのが怖いなら何故アルバニアに挑まなかった?
俺はここを抜け出し、アクエリアを制圧し、アルバニアを引き釣り出してぶっ殺す。てめえと心中なんざ真っ平御免だ」
「貴方は分かっていないわ。私達はあの方には逆らえないの。分かるかしら、『あの方』を見た時に感じる悍ましさ。『可能性』を得ているというその『素晴らしさ』に驕っているの」
此処は通過点であるとジェイクが銃口を向けた時、ミロワールはそう言った。そうだ、イレギュラーズ達の命は『可能性』を帯びて常人よりも運命の力を得ているともいえる。一般人が多少無理したとしたならば死は常に隣り合わせだが彼らはその命にリソースを『見る』事ができる上に、安易に死なぬ様にと神が加護を与えているともいえるのだ。
「そうかい」とジェイクは返した。だからどうした、とは言わなかったが――蝶々が為なのだから彼女の言葉に惑わされてはいれぬのだ。
「君の手を取ることは断る。何故なら、その結末には救いがない。君の望むエンディングには程遠いからだ」
『さあ、終幕だ。ド派手にいくぜ』
「この劇を『宵の子』ミロワールに捧げよう」
朗々と、虚と稔は歌い上げた。それは悲劇であり喜劇であった。此処に『セイレーン』が居たならば、歌でも歌い盛り上げたのであろうか。
謡う様に、稔と虚の攻撃を重ねる中でも、ミロワールは反撃を行わない。
(『なんだ……?』)
そこにあった違和感は確かなものだ。それを眺めながらも片恋に憂う蝶は「人生をあきらめたのですね」とミロワールへと囁いた。
「僕は貴方の相手をしてる暇などないのです。廃滅病で人生を諦めきっているのなら、そのまま死になさい。
抗う心をもたないものに何を言えと言うのでしょう……貴方の言うことはただの甘えに過ぎません」
幻は首を振る。人は誰だって奇跡を起こせる――それは強い信念から生み出されるものなのだ。憐れにも下を見て人を妬み嫉み、諦めるミロワールにはそれすらできぬだろうと幻が作る幻想の蝶が揺れ動く。
「生い立ちに同情しないとはいいませんが。要約すると『自分より妹が可愛がられていた私可哀想』という自己憐憫に過ぎないのですよ、貴女の動機は。
我々を、この海を巻き添えに自滅にするには、いささか自己都合に過ぎる」
寛治は冷静にそう言った。愛されるはずだという思い込みに瑕疵があると告げるそれにミロワールは「ええ」と小さく呟く。
「では聞きます。『貴女は家族を愛そうとしたのですか?』」
「愛し方が分からなかったわ。愛されたことに、気づけなかったのだもの」
もう、ミロワールにはそれを否定し駄々をこねる気力もなかったのだろう。
寛治は「それは貴女が周りに目を向けなかったからでしょう」と静かに、そう、言った。
「HAHA! 嫉妬大いに結構、だが悪いな、俺はグリードだ! 羨むくらいなら求めるぜ、てめぇの手で勝ち取ってこそ価値が現れる!!」
堂々とそう言った貴道は拳を固め――ミロワールの背後に残った狂王種を叩き潰す。
「憐れな娘 哀れな世界。出会えなかったのだな。その射干玉に星を捜せないまま……妬む鏡に成り果てるしか無かったのだろう」
ウォリアの焔が燃える中、貴道が数の少なくなった狂王種を叩き潰し続ける。そうだ、彼がそうするようにウォリアだって『力』でしか語れなかった。
「その道に真なる『終焉』を刻み、業深きその魂をオレが喰らおう。
これは宣誓だ……廃滅の呪いすらも、我が焔が死の果てまで焼き尽くす」
掲げられた剣を包んだ炎を少女は綺麗と呟いた。その呆然とした気配にウォリアは哀れなと何度も繰り返した。
「キミが死ぬまでキミとオドってあげる。でも、イッショには死ねないヨ」
死ぬまでの寂しさを紛らわせて忘れ去瀬、遊びまわることは出来るけれど、とジェックはゆっくりと肩を竦めた。
「キミが『かたわれ』を殺せてシマったように……結局シぬ時はヒトリなのさ。一緒に死んだって、ヒトリの死が二つナラんでいるだけダヨ」
「ふふ、貴女と死んでも?」
「ソウ。死を受け入れてはアゲられないけど、ソレまでの時間を紛らわシテあげる。それは一緒デショ?」
踊りましょうと手招いた。弾丸が、ミロワールの頬を掠める。戦意を感じさせぬ彼女は「痛いわね」と小さく囁いた。
「……そろそろ話終わった……?」
リリーはゆっくりと顔を出してからため息を吐いた。兎にも角にもギルティなのだ。
「……そんなの全部逆切れじゃんよねぇ……。親に干渉されずに一人で家にこもってられるとかむしろ勝ち組じゃん……。
そもそも海は墓場じゃないし……? 身投げとか海に暮らしてるこっちが迷惑するんだけどさぁ……」
ぶつぶつと呟きながら、リリーは苛立ちをあらわにした。闇をバールで叩きつけ、呟く彼女の声にミロワールは「海も面白いわね」と囁く。
「悪い冗談にも程がある。一緒に死ぬなんて願い下げだ。生憎君と違って私達は『生きていたい』ものでね」
しかし、理解はするというマルベートの傍らでLumiliaは頷いた。ちら、と彼女を見遣る。彼女は強い、過保護になりすぎる事はないが相手は魔種だ――ああ、けれど、彼女は『理解され』ていると感じた相手にはどうにも無力だ。
(……まるで、迷子ですね。肯定されたことに満足して、受け入れられたことに心を添えて、どうするべきか迷ってなされるが儘)
Lumiliaは「もう苦しむことも苦しませることもない、終わりにしましょう」と囁いた。マルベートは緩く頷く。目の前に立っている鏡はもう罅が入っているではないか。
「君は哀れで幼い獣だ。安心して欲しい。心から愛してあげるし、後悔も寂しさ命も全て喰い尽くしてあげよう」
サンディは笑う。ああ、何も知らない世間知らずの子供がそこにはいるのだと、おかしいものを見るようにからからと。
「俺だって『疎まれてた』から棄てられてたからな。周囲なんてそんなもんよ。でも、その様子じゃ分かってねーな?」
天邪鬼だ。彼女は自分が嫌いで、けれど、誰かに愛してほしくて。唯一の理解者を殺して『自分が分からなくなって』いるではないか。
「嫉妬してる場合じゃねーんだ。鏡を見ろよ。いいレディじゃねーか。
静かに笑ってりゃ男の1人も引っかかる。街中で突然槍の試し突きの標的にされるような『死んでもいいガキ』とは違うんだ」
ぎこちなく、黒髪の少女は笑った。その笑みを見て、サンディは「素敵なレディだぜ」と笑う。宵の深い瞳は闇夜よりも尚、星空とそうするに相応しい。黒いドレスを思わせたそれは虚無を纏っているのだろうか。
「俺は死にたくないヤツしか引き上げらんねーぜ!」
手を差し伸べた――『彼女に敵意がない』のならば。イレギュラーズの手を取るならば、その死の間際まで共に居ようと声を張る者たちもたくさんいた。
理解は、きっと、理想と遠く。けれど、彼女は『理解され』『肯定され』『死ぬ間際は愛されたかった』だけの子供であったのかもしれない。
「キミを受け入れれば、わたしもキミも死ぬ。けれど、キミは『死にたくない』って言った。
辛くて、寂しくて。ホントは誰かと死ねれば、それで良かったのかもしれない。けれど、『死にたくない』のもホントなんだと思うから」
シルキィは「わたしも死にたくない」とそう言った。分かろうとしてその病を酌み交わして、それでも――死にたくなかった。きっと助かるからとか信じてとか、そういうことは言えなくて、ミロワールのすべてを信じてやることも、分かってやることもきっと、できない。人間は弱くて脆い。だから、今、彼女は言った。
「『死にたくない』と願ったのなら。『一緒に死のう』なんて、言わないでよ」
足が動く。一歩、イレギュラーズの元へと。
「シャルロット」
ぴたり、と黒髪の少女が止まる。イレギュラーズ達に心動かされた少女は『どうしてそうして呼ばれた』のかに気づいてしまった。気づきたく、なかったのだ。
「シャルロット・ディ・ダーマ。
私は『狂王種をアクエリアに向けて出陣させなさい』と言いました。
かの島を喪ってはならぬと。そう言いましたよ。それが――どういうことですか」
顔を上げたジェイクはそこに立っている女を確かに見た。
「『セイレーン』」
セイラ・フレーズ・バニーユ。その嫉妬の魔種は苛立ちを露にして黒髪の少女を見下ろしている。
「貴女にこのように大きな力を与えたのは、アクエリアに向けて出陣したイレギュラーズを迷宮に留めんとするため。
それがどうした事ですか? 貴女は狂王種を作り出さず、イレギュラーズ達の言葉に涙してなされるが儘!」
セイラ・フレーズ・バニーユが呻く。反撃の気配をさせていなかった『ミロワール』は――シャルロット・ディ・ダーマと呼ばれた少女は悍ましい気配を感じるように唇を震わせる。
「私、私は――妬ましいわ。……だ、だって、この人たちは未来を見ているんだもの。ね、妬ま――ッ」
ばりん、と。
大仰な音をさせて砕け散ったそれに縁が「空が割れた」と呟いた。虚と稔はまるで天が落ちてくるようだとさえ感じている。
「待って、セイラ。違う、違うわ。私はちゃんとあの人たちをここに留めて――! アルバニア様の邪魔なんてしないッ、嫌、ごめんなさい!」
その声を残して、鏡の迷宮は霧散した。
成否
成功
状態異常
第3章 第5節
長い黒髪に、真っ黒の瞳。それが彼女であった。魔種ミロワール、宵の子。
彼女の出自は海洋王国の小さな村だ。漁村を営むその一家の娘、家族の誰もが黒い髪を持たぬその一家の中で『異質』であったミロワールは揶揄われ拾われ子とまで揶揄されたそうだ。
特異運命座標は彼女を根本より否定しなかった。
許されざる事をしたとしても――『生きるために必要だった』事だと告げる者もいた。
廃滅病で死にたくないならば――『その前に殺してやろう』と慈悲を与える者だっていた。
ミロワールはその姿をイレギュラーズ達の前に晒してから小さく息をつく。
気づけば『鏡像世界アクエリア』より現れ出た狂王種は消え去っていた。
自分を殺してくれると言ったイレギュラーズにミロワールは心の奥底より好感を覚えてしまったのだろう。
彼女は魔種で、
彼女は『異質』で、
彼女は――この世界には受け入れられない存在だというのに。
「ミロワール。ああ、やっと姿を見せてくれたのですね?」
「……セイラ」
確かめるようにミロワールは言った。長い黒髪を揺らしたミロワールはセイラ・フレーズ・バニーユをまじまじと見てから目を伏せる。
「イレギュラーズはアルバニア様を斃すつもりなのだそうよ。
きっと無理よ、ええ、無理だわ。無理――だと思うのに……」
「ああ、おかしい! 貴女はあろうことかイレギュラーズに肩入れしたのですね!
その甘言に惑わされ、彼らを信じてみたいと! 『あの方』を斃す手を貸せと言われ貸さなかったのは利口です。
ええ、ミロワール。そんなことをしている暇なんて『あなたにはないでしょう』?」
傷だらけの少女は小さく笑った。そうだ、そんな暇なんてなかったのだ。
もう自身は廃滅病に侵され『もうすぐでリミット』が来るのだから。
「貴女は嫉妬の魔種。あのように未来を目指す者たちが妬ましくてたまらないでしょう?
それとも――『そうも思えぬほどに好感を覚えたのですか』? 魔種だというのに、人間の様に!?」
その言葉は自身がどちらにも居場所がないとさえ思わせた。
ミロワールは――『シャルロット』は妹『ビスコッティ』を妬ましく思っていた筈なのに!
イレギュラーズ達によるその言葉で、どうにも心が掻き回されたのだ。
ビスコッティの元に行くためならば、彼らに殺される道を選びたいと、そう思わせられたのだ。
「ああ、『鏡(ミロワール)』、貴女は、鏡だから……そうして希望を抱く彼らを映してしまったのですね。
憐れなあなた。何も言われず、否定されるだけならば『あなただって殺した』のでしょう?」
魔種は死んでしまえと謗るものがいたならば、きっとそうした事だろうとセイラは笑いながら言った。
「同情し、傍に居てあげると。友人の様に語らうことを求めてくれた、彼らの優しさを映したら……。
嗚呼、可愛そう! そうすることも出来ずむざむざと傷つくだけ傷ついて深海で泣いているのですものね。
殺されればよかったと! けれど、『怖くなってしまった』のだと!」
――生きたい、と言ってもいい。
その言葉がどこまでもミロワールに、シャルロットに纏わりついた。
生きたい。
イレギュラーズ達と未来を掴みたい。あの方を斃すなど無理なのに。信じさせるのだから。
死にたい。
愛おしい『ビスコ』の傍に行って「ごめんね」「待たせたね」と笑いかけたい。
そのどちらもが彼女をアクエリアより逃亡させた。足は竦むことなく、その場に居る事を拒絶したのだ。
「可哀想な、シャルロット・ディ・ダーマ。鏡の魔種ミロワール。『半端者』の貴女。
最後に、選ばせてあげましょうね。もう一度のチャンスを得て『イレギュラーズ達を殺すか』、それともすべてを放棄して『私に殺されるか』」
シャルロットはそれを聞いてから、口をぽかりと開けて、唇を震わせた。
彼女の選択は――
GMコメント
●達成条件
・『ミロワール』の鏡の破壊(下記『達成度』の目標達成)
※ミロワールの迷宮達成度
1:狂王種討伐数
2:参加イレギュラーズの『脱出数』
上記が一定数を超えた段階で迷宮は壊れ、鏡が破壊されます。
●魔種『ミロワール』
鏡の魔種。少女であることだけ判明していますが鏡であるために『誰かの姿を借りて』居ます。
バニーユ夫人とは旧知の仲であり、彼女自身は廃滅病に罹患しているために死を恐れ悲しんでいます。皆さんなら救ってくれるはず、そして『皆さんなら死ぬなら一緒に死んでくれるはず』とバニーユ夫人の提案したアクエリアでの『遊び』を行っているそうです。
●ミロワールの迷宮
魔種ミロワールが作成した迷宮です。鏡の中にはアクエリアが存在し、狂王種たちが生み出され続けています。
(狂王種たちは海の生物ですがアクエリアの中を無尽蔵に動き回れるように改良されているようです)
また、鏡の中では『自分自身』または『プレイングで合わせた相手』が敵となり襲い掛かってきます。自分自身を退けることで外へ出るための出口が開きます。
(※合わせプレイングをした場合は『両者で冒頭に名前を指定orグループタグ』をご記入ください)
●狂王種
無尽蔵に存在します。出来るだけ倒してください。
●ラリーシナリオ
※報酬について
ラリーシナリオの報酬は『1回の採用』に対して『難易度相当のGOLD1/3、及び経験値1/3の』が付与されます。
名声は『1度でも採用される度』に等量ずつ付与されます。パンドラはラリー完結時に付与されます。
※プレイングの投稿ルール
・投稿したプレイングはGMが確認するまでは何度でも書き直しができます。
・一度プレイングがGMに確認されると、リプレイになるまで再度の投稿はできません。リプレイ公開後に再度投稿できるようになります。
・各章での採用回数上限はありません。
●本シナリオの特殊ルール
・本シナリオでは『作戦達成度』に応じて良影響を<バーティング・サインポスト>へと与えます。
・本シナリオでは各章に設定される『作成達成度』に応じて章が進行します。
(最大5章まで。作戦達成度に応じて章数は短縮される可能性があります)
それでは、皆様。鏡の国へいらっしゃい。
●重要な備考
<バーティング・サインポスト>ではイレギュラーズが『廃滅病』に罹患する場合があります。
『廃滅病』を発症した場合、キャラクターが『死兆』状態となる場合がありますのでご注意下さい。
Tweet