シナリオ詳細
<グラオ・クローネ2018>ドリームコラプサー
オープニング
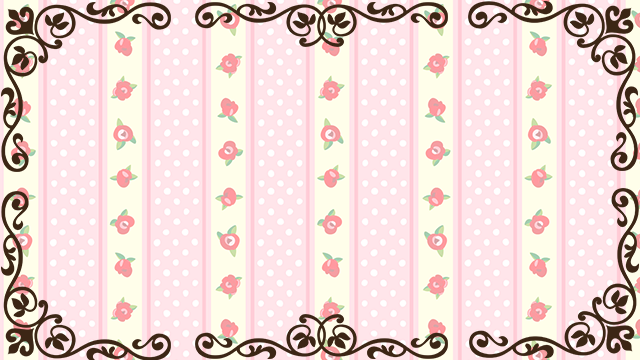
●
近代日本が幕を開けた明治三十六年。
元は華族の令嬢のために設立されたと言われている。
平成となった今日でも幼稚舎から大学まで、伝統を格式を重んじた教育が掲げられていた。
二月の澄み切った空の下で、今日も穢れをしらない少女達が勉学に励んでいる。
ここは、そんな乙女達の園。
――
――――
「あら、どうしたの?」
お姉様の問いに、少女は慌てて小さな箱を後ろ手に隠す。
「い、いえ。なんでもないんです」
気づかれてしまっただろうか。
「おかしな子ね。放課後の会議には遅れないようにしなさい」
「はいっ」
「あなた、今日は少しおかしいわよ?」
「そ、そそそ、そんなことはないです」
「そう?」
訝しげな表情を見せたお姉様は「じゃ、いいわ」と歩いてゆく。
危ない所だった。何せ今日はヴァレンタインデー。大好きなお姉様に手作りのチョコを作ってきたまでは良いのだが、なかなかタイミングがつかめない。
授業の合間の休み時間に渡すのもどうかと思い、また咄嗟に隠してしまった。なんというか、もう少しムードが必要だと思うのだ。
でもお姉様は喜んでくれるだろうか。
学校にこんなものを持ってきて、叱られてしまうかもしれない。
結局、授業の内容はまるで頭に入ってこなかった。
不安な気持ちのまま迎えてしまった放課後。いつも彼女は会議が始まるだいぶ前に、生徒会館へ向かう。紅茶を入れ、お菓子を用意して先輩方を待つのだ。
(あれ、お姉様と一年。名前は何だったかな)
校舎のほうで、お姉様が下級生となにか話している。
下級生の手には小箱が見えて――
息が詰まりそうになる。見知らぬ下級生の子が大好きなお姉様に、きっとチョコレートを渡そうとしている。
そんな所を、これ以上見てはいられなかった。
焦燥混じりの冷たい感情が胸にこみ上げ――
少女はお姉様に気付かれぬよう、そっと生徒会館入口のドアをあける。
「くーぅちゃん!」
「うわあああああっ!」
ドアを閉めた瞬間、後ろから突然抱き着かれた。
誰かと思えば生徒会役員の桜様だ。というかこんなのって完全にセクハラで。
「どうしたの、そんなにびっくりして。あーー、さては」
●
「ということに、なってしまったんじゃよ!」
「えぇ……」
依頼人の言いたいことがさっぱり分からないものだから、イレギュラーズはかろうじてそれだけを口にした。
「つまりじゃ」
懸命に説明を続ける依頼主、幻想貴族クルーク・レ・アルトワジーの話は、おおよそ次のようなものだった。
この短杖。夢の崩壊者『ドリームコラプサー』の存在意義を端的に述べるならば、拷問器具である。
人の生活における最後の砦たる夢に干渉して破壊し、魔術によって設定した夢を強制的に見せることが出来る。
無論、通常はとてつもない悪夢を見せることになる。
この貴族はこの道具を使い、これまで数々の政敵と対峙してきたのである。
もっともこのおっさんは魔術が使えないから、外部の魔術師を雇って設定を依頼しているという話だった。
「それが、こんなことになってしまったのじゃ! 敵の嫌がらせに違いない!!」
貴族のおっさんはかんかんに怒っているが、その悪夢がどうも何者かによって、不思議な夢に塗り替えられてしまったのだ。
夢の内容はどこか異世界の女学生となり、どことなくグラオ・クローネに良く似た日常を送るというものらしい。
さっさと元の効果に戻したい所なのだが、この杖には弱点があるのだ。籠めた魔力が切れるまで夢の内容を変更することが出来ないのである。
そして魔力の残りは、ざっと数十回分はあると来たものだ。
「はぁ」
いやがらせもなにも。こんな風に魔法の効果をぺらぺらと語って見せびらかしていれば、そんなことにもなってしまいそうである。
なんだか迂闊なおっさんだが、それは言わぬが花であろうか。
「それで、どんな依頼なのかしら?」
「おおお。そうじゃった」
まあ、ものすごく奇妙な夢ではあるが、悪夢ではないから。効果が切れるまでローレットのイレギュラーズに使わせて欲しいらしい。
「自分で使えばいいんじゃないかしら……」
だって、悪夢ではないならば。
「そ、れ、が! じゃよ!」
なんでもおっさん、その状態に気づいてから。とりあえず回数を消化するために自分にも、奥方にも、メイド達にも、執事にも使ってみたのだ。
夢の中では現実世界の事も覚えていないし、文化も風習も違う自然に溶け込んで振舞ってしまうらしい。
要するに意識せずとも勝手に可愛い女の子になりきってしまうらしいのだ。まあ、それは良いだろう。
しかも同級生と女の子同士で手をつなぐだけでどきどきするような有様で、それもそれで仕方ないのだろうが。
恐るべきことに、その夢はその日『共有』されてしまうのだ。
そしてこのおっさん。夢の中で大好きだったお姉様は、執事のじいさんだったのである。
なんか起きてから、夢について皆でわいわい話していて気づいた。気付いてしまった。本当に話さなければよかった。
「あんな目には、二度と、二度とあいとうない、頼む!! この通りじゃ!!」
「えぇ……」
イレギュラーズは本日二度目の言葉を返し『てか犯人て。その雇われ魔術師の関係じゃないの』等という言葉を飲み込んだ。
- <グラオ・クローネ2018>ドリームコラプサー完了
- GM名pipi
- 種別イベント
- 難易度VERYEASY
- 冒険終了日時2018年02月25日 21時31分
- 参加人数50/50人
- 相談7日
- 参加費50RC
参加者 : 50 人
冒険が終了しました! リプレイ結果をご覧ください。
参加者一覧(50人)
リプレイ
●
私、鳴海ほのか15歳。
中等部に通う普通の中学3年生……だったんだけど――
冬の正午。
やわらかな木漏れ日につつまれて、二人の少女がはにかむように微笑んだ。
「という訳でチョコと素敵なお洋服作ったの」
「わ、わ。いつもありがとうございます」
レンガを敷いた中庭――なんでも獄ヶ原醍醐という有名な建築士が作ったという道らしい――で、ほのかが振り返る。
なんの取柄もない、けれど平和だったあの頃はもう戻らない。
この眩しい笑顔の。あの日訪れた彼女との出会いが、ほのかを変えて――
「私の為に着て、そしてチョコを食べてほしいの……ね?」
「ほ、ほええ」
「いいでしょ?」
ぐっと押すほのかに、彼女は頬を染めて俯く。
「ほのかさんがそう仰るなら……」
世界で一番かわいい彼女に絶対に合う素敵な衣装。
着て、チョコを食べてもらって、その様子を写真や映像に収めるのだ。
この子を世界で一番可愛く撮れるのは、ほのかだけなのだから。
そんな光景の先、楡を囲むように並んだベンチに腰かけて。結はそっと本のページをめくる。
周りではお弁当を広げ始めている少女達の姿が目に留まるが。
「ご、御機嫌よう。その……良い天気に!」
リンの不慣れな言葉遣いに、結の口元がふわりとほころんだ。
母の熱烈な勧めで中途入学した彼女にとって、お嬢様学校で知られるこの学園の敷居は高かったけれど。
「もうっ、笑わないでよ。確かに似合わないかもしれないけどっ」
「そんなことないわ」
結がそっと本にしおりを挟む。
のんびり一人で本を読むのが性に合っていた結と、お嬢様に囲まれ疎外感を感じていたリン。
そんな二人が今はこうして一緒にいるというのは、ある種必然的なものだったのだろうか。
今では一番の親友だと、胸をはってそう言える。
「今日は、その、お弁当つくってきたんだけど」
喜んでくれるだろうか。自分ではそこそこ美味しく出来たと思うのだが、考え出してしまえば不安が止まらない。
リンは慌てた様子でお弁当箱を可愛らしい竜胆の花柄の袋から取り出すが――
「わっ」
膝からころげそうになるお弁当箱を二人が支え。
――触れ合う。すべらかな指と指。
頬を染めて視線を外す結に、リンの鼓動が高鳴り。
その近くの木陰に居るのは。
(うッッ、なにあれ尊い……!!)
今日もお姉様達は美しい――そう溜息をつく冥利はガチ恋厳禁過激派ピンチK(迷惑かける若い子)絶許DD(推し多数)のお姉様見守り隊、会員ナンバー2213。要するにお姉様がたファンクラブ。お姉様オタク(ガチ勢)である。
この場にいるお姉様方は誰しも楽しそうに話しているが、彼女にはそんな勇気もない。
むしろこうして木の陰から見守っているだけで十分というもので。
「む……あぁ、そこのお前」
そんな彼女のすぐ後ろから声がする。
「へ、私?」
「良ければ飲むか?」
人気というから買ってみたイチゴミルクではあるが、リルクルスには少々甘すぎたというだけなのだが。
「なに、まだ一口しか飲んでいない」
これはまずい展開だ。リルクルスお姉様といえば水泳部を導く冥利が推しにしている代表格のお一人な訳で。
「ふ……気にするな。お前には幾たび世話になったからな。これはその礼だ」
リルクルスが冥利の横にある木にそっと手の平を当てる。
「う、うわぁあっ!?」
お世話ってなんだ。水泳部で撮らせて頂いた尊い写真をファンクラブ同士で交換していることか。
というかなんなのだこの状況は。姉オタとしては、自分が輪の中に入りたい訳ではないのだが。
「不服か?」
美しい顔が近づく。
けれど、そんなことは滅相もない訳で。
●
そんな中庭の隣。学食へ続く廊下でアンナは冷たい窓に手の平をあてた。
「はぁ、まったくどの娘も浮かれて……私達の本文は学業だと言うのに」
独りごつ生真面目な彼女は風紀委員である。
「ほらそこ! チョコもいちゃつくのもせめて放課後まで我慢なさい!」
「ごめんなさいっ」
かの名物生徒会長もあのような調子で『いいんじゃなくって?』などとハートを飛ばしまくる姿が容易に想像できてしまう。
というか。言ってしまえば彼女の想い人――大切なお姉様は他校生であり、放課後まで会えないのである。
(……待ってて下さいね、私のお姉様)
自分を律し他人を律し、学業の時間が終わった後に堂々と会いに行くのだ。
チョコレートは渾身の力作。どのように食べてくれるだろうか。そしてあわよくば私も――
……うふ、うふふ。うふふふふふ。
「……あら、私とした事がはしたないですわ」
ハンカチを口元にあてる。何か光っていたのは気のせいだ。
さあ、輝かしい未来、めくるめく愛のひと時のために頑張るのだ。
雪はいつものようにカウンタに並お弁当やパンを見つめている。
今日は何にするか。食べたいものは多いが、そんなにたくさん食べられる訳でもないから大変なのだ。
日替わりか、それとも限定のグラオクローネというパンか。
(……今日は、パンの気分)
という訳で、至福の時がやってくる。
温かな光が差し込む学食では、既に多くの生徒たちが思い思いの場所で話に花を咲かせていた。
「おー…! 今日はなんだか皆がソワソワしてるね……?」
いつもの仲良しメンバーでテーブルを囲むヨルムンガンドが辺りを見回す。
「ヨルちゃん、今日バレンタインだよ」
「んー……? あー! あの、好きな人にチョコをあげるってやるか……!」
すっかり忘れていた。みんなの事は大好きなのに、チョコの用意なんてしていなかったのだ。
「じゃあ、ヨルちゃんは貰う側っ」
そういうと彼女は小さな鞄から小箱を取り出す。
「はい!」
「え……? 私は用意してないのに」
「私がヨルちゃんのこと大好きだからあげるだけだもん」
「じゃあ私も、はいっ! ヨルが食べてる所みてると、なんか幸せになるの」
「わーっ! やっぱり大好きだ……っ!」
「わわっ」
手を握り合う三人。
「それなら……このチョコ、一緒に食べよう?」
「うんっ」
「はい。あーん……」
「あーん」
食べちゃいたいぐらい可愛いとは、おそらく三人は三人とも思っているのであって。
「ど、どうか……」
消え入りそうな声で、ルシフェルが壁にそっと手を這わせた。
さらさらの黒髪が儚げな頬を伝い、口元に影を落とす。
「まぁ、貴女。如何なされましたか?」
そっと肩を支えるルル家に寄りかかるルシフェルの頬はあまりに白かったから。
「大変、人を呼ばないと……」
「あなたの血を、わけてくださ、あはぁん」
「あら、血を……?」
血液嗜好症(ヘマトフィリア)というものだろうか。
気はすすまないが――ルル家は自分の指先をそっと噛み、流れる赤を彼女の唇に当てる。
はむ。
「あらら、そんなに飢えた犬のように夢中になって」
はむはむぺろぺろあむあむあぐあぐぺろぺろ。
あっしゅごっんんっおいちいルルたんおいちいよお。
「少々落ち着きが足りませんわよルシフェルさん」
夢 見 流 腕 緘 !
「ぎえぴぃぃ!!?」
「はぅっ! わたくし一体、なにを!?」
「正気に戻られたようで何よりですわ」
「あらご機嫌よう、小さきひと」
「えぇ、私これからランチなのですが、ご一緒にいかがかしら?
貴女には少々激しめの教育が必要そうだと感じましたし、ね」
「やだ、激しいだなんて愛さえ感じますわ」
年齢制限とか、ガチとか、そんなものではない。これはもっと、恐ろしい物の片鱗なのではないか。
――
――――
そんな食堂の中で雪は一人、チョコレートパンをそっと口に運ぶ。心身共に生き返る。染みわたる。
と思ったのだが、隣に佇む下級生の女の子は、なんだか浮かない顔をしている。
「どうした」
びくりと肩を震わせた少女は目をそらすが、どこうともしない。
「何かあるなら話してみろ……」
「あの」
つかえながら、少女はぎゅっと瞳を閉じて、唐突に叫んだ。
「雪お姉様、好きです!」
昼休みも終わりにさしかかっている。
そんな食堂を抜け、教室のほうへ向かう手前の部屋――
「オクト様?」
静かな怒りを湛えた声が保健室に響く。
「もうお昼休みは終わりましてよ?」
「はいはい、聞こえてます、聞こえてますー。サボってちゃ、悪いってんだろー?」
のんびりとした声音に少女はため息一つ。
ベッド横のカーテンを開ける。
「良いじゃねぇか、困んのはアタシだけだしよー」
半身を起こしたオクトの美しい黒髪は微かに乱れていた。
勝気な瞳に射抜かれるように、保健委員の少女は視線を落とす。
「……なんだよ、急に黙んなって」
「――き、ですのよ」
「え?」
「好き、ですのよ!」
彼女の手にはリボンに包まれた小さな箱があって。
「す、好き? 待て待て、アタシら同性だろ!?」
慌てて身を起こすオクトを、少女は睨みつけた。口元が震え、目に涙が溜まっている。
「ああっ、わ、悪ぃって、泣きそうな顔すんな! 別に嫌って訳じゃねぇよ!」
「お返事を、いただきとうございます」
「へ、返事? あー……今すぐじゃなきゃダメ?」
少女は口を閉ざし、オクトの豊かな胸に顔をうずめた。
「……ダメです」
小さな呟きに、覚悟を決める時だった。
「アタシも――好きだよ」
●
こうして午後の授業は終わりの鐘を告げた。
今日は待ちに待ったヴァレンタインデー。その放課後である。
アレクシアは半年前、一目見た時から恋焦がれてきたお姉様にチョコを渡す為、一人廊下を歩いていた。
向かう先は科学部の部室である。
彼女が思い返す憧れのお姉様。それは美しい黒髪にスタイルは抜群。今年の化学グランプリでは銀賞を受賞。英検に情報処理検定と、才色兼備を地で往く科学部の部長である。
後輩達からは『学園一のクールビューティ』『学園一胸が大きいお姉様』あるいは実験への研究姿勢からか『希代の死霊魔術師ジーク・N・ナヴラス』等と呼ばれていたりもする。
当人は少々気にしていたりもするらしいが、さておき。
当のお姉様はくしゃみを一つ。部室へと向かう前に機材の用意をしようと、下駄箱のほうに立ち寄ったのだが。
「これは、何でしょう?」
かがんだ拍子に赤い眼鏡へかかった美しい黒髪を指先で払い、彼女は小さな紙を取り出す。
手紙だろうか。
今日は実験を予定しているのだが、ともかく行くだけ行ってみるしかないだろう。
そんな頃、少女は一人屋上へと向かう。
(あの人の靴箱に、放課後の屋上に来てくださいっていう告白の手紙は入れてきたけど……)
そんな手紙の差出人は彼女だ。
と、すれちがった拍子に何かがふわりと見えて。少女は振り返る。
「あの、ハンカチを落としましたよ」
そっと拾い。
「あら、ありがとう」
手渡しながら微笑む少女にアレクシアは礼を述べたが、去り際の少女は親を探す子猫のように、少し肩が震えていて。
そんな彼女の悩みは深刻だった。
本当に来るか。否か。来ても良い返事が貰えるか否か。手紙を出した少女はそんな気持ちでいっぱいだったから。
不安と焦燥が渦巻く胸に手をあて深呼吸する。
(ううん、そんなことない!)
悪路に挑むアルプス・ローダーのように勇気を奮って。
(きっとぼくの好きって気持ちは伝わるから!)
彼女は険しい山道に挑むような気持ちで階段を登ってゆく。
――でも、どうしてだろう。
そう思いアレクシアは足を止めた。先ほど屋上へと向かっていった少女の横顔が脳裏に焼き付いて離れないのだ。
すれちがい、落としたハンカチを拾ってもらって、少し目があって、微笑んでくれた。
ただそれだけの筈だったのに。
(私の心はお姉さまのものだと思っていたのに……)
このままではお姉さまにチョコを渡すことなんて出来ない。
もう一度あの子に会って確かめないと。
自分自身の気持ちが何であるのか――もしかしたら私はあの子に――会って確かめなければならないから。
会いたいのではない。
アレクシアは踵を返し、少女の後を追って屋上へと向かう。
(これは仕方ないのよ……!)
さて、そんなトライアングルの予感を物陰からチェックしていたのが新聞部部長のクロジンデと後輩部員の二人である。
「いまからインタビュー……ですか?」
「不要だよ、時間かかるし邪魔するのも悪いー」
「えええ」
「文章は写真から適当にでっちあげるのだよー」
「そっちのほうがダメですよう」
既にあちこちで写真を撮り来週の記事を充実させていた彼女であるが、これはちょっと波乱の予感がするものだから大変だ。
パパラッチ魂が呻る。
それに彼女の代で廃部にする訳にもいかない。印刷機が差し押さえられない程度には捌かないとならないのだから。
●
革命部の放課後は忙しい。
「ん……よく寝た……」
西へ傾いた太陽が照らす教室で、シオンが顔を上げる。
「はっ……そーだ……! 早く家庭科室に行かないと……!」
今日こそ学校一の不良、兼、部長のルーミニスが打ち立てたプラン。
その名も『美味しいチョコ配りまくってバレンタイン台無し計画』が発動する時なのだ。
あのカタリナお姉様♡が率いる生徒会を打倒するためにも、こうしてはいられない。
「シオンも来たわね、チョコを大急ぎで量産するわよ!!」
高らかな宣言と共に、大量の材料が机に並ぶ。両腕と共に美しい銀髪がふわりと広がり。
(あぁ、お姉様の銀髪の髪……凛としたお顔…尊すぎますわぁ……)
毎晩お姉様のことを考えるだけで、ヨハンは耳としっぽがむずむずしてしまう。
「沢山配って特別感を薄れさせてやるのよー!!」
何かそんな計画らしいが、とにかくお姉様がすることは全て正しいから良し。
「シオン……お姉様の邪魔をしたら許しませんわよ!!」
「頑張ってチョコレートを作ってルーミニスおねーさまに渡す……!」
三者。溶かして、固めて、箱に詰めて。
シオンは作り方は分からないが、お姉様の手際を見様見真似で。
結局もうなんか商業規模である。
「ついてるわよ」
「お姉様がこんな近くに!」
ルーミニスが顔を近づけ。
「い、いけませんわ……よだれが……」
ヨハンの頬についてチョコを指でさらう。
「お姉様お姉様お姉様お姉様お姉様…!! ルーミニスおねえさま~~~~~っ!!!」
ヨハンのしっぽがピンと伸びる。
「そうそう作ってて思い出したのだけど二人に渡したい物あったのよ」
「なんだろう……?」
眠たげなシオンと、耳をピンと立てるヨハン。
「はい、日頃からありがとね……!」
「にゃおおおお!」
そうだった。シオンも日ごろの感謝をこめて。
「……はいどーぞルーミニスおねーさま……!」
そんなこんなで楽しい時を過ごせども――
昨晩、夜更かししてのチョコレート作りが中々に祟るもので。
計画は失敗しても、そこには三人の幸せそうな寝顔があるのであった。
「くくく……」
暗い物陰でオロディエンの眼鏡が光る。
不要な予算はカット。そう、彼女は生徒会の会計である。
「ここで生徒会の年間収益を黒字にすることで、私は大学の商学部へ推薦で進学できるんだもんね」
今まさに革命部へと魔の手が忍び寄ろうとしていた。
「オロディエンさん。愛を忘れてはダ♡メ♡ヨ♡」
そんな彼女の肩を撫で、豪奢な桃色の髪をかきあげるのは♡聖カタリナ女学院♡の理事長の孫娘――カタリナ・チェインハートである。
容姿端麗、スタイル抜群。歩くたびに新聞部のフラッシュが焚かれる。美貌の戦乙女とは彼女のことだ。
そんな彼女も今日は生徒会を率いて、こうして学園内を見回りを行っているのである。
生徒――つまり姉妹達の風紀のみならず、生活を守護し、規律と愛を育むのだから。
そんな生徒会一行が中庭を歩いていると、ふわりとした美しい金髪が目にとまる。
二学期の頃デンマークからやってきたお嬢様――クレイスだ。
下級生から羨望の的になっている肢体。そのすらりとした腕を、後ろから小さな腕にそっと重ねて。
「ぁっ……」
細い背に豊かな胸があたり。
「集中しナさイ」
「っはい!」
「このフォーム。忘れてはダメですヨ」
スポーツ万能な彼女は昼休みともなると、多くの下級生に囲まれていろいろな事を教える毎日になっていた。
「中庭の様子を視察しますので、会長は先にあちらへ」
そう述べたのは会計のクローネだ。生真面目な彼女はこうして全校生徒の動向を見守り、予算に反映しなければならないのだから。
だが、そうしているとゆらりと視界に靄がかかる。
周りの音がずいぶん小さく聞こえ――仕事を終えた後で生徒会のお姉様方にチョコをお渡ししたいのに。
「いけナいッ!?」
ゆっくりと崩れ落ちる彼女を、しなやかな肢体が優しくささえた。
「大丈夫?」
きらきらとしたクレイスの金髪が眩しくて。
高鳴る胸の鼓動にクローネは――
一方、美術室では愛莉が一人、石膏像をぼんやりと眺めていた。
今年のコンクールに出展する絵を仕上げなくてはならないのだがモデルが決まっていないのだ。
否――本当は決めていた。
だが言葉すらかけられていない。今日は愛の日だからとチョコレートまで用意していたのだが、こんな時間まで言い出せず仕舞いなのであった。
結局、諦めて公募してしまった訳であるが。
ふと美術室の引き戸がゆっくりと開く。
「アリソンさん!?」
絡み合う視線に、二人は身動きもとれず、どれだけの時が流れただろうか。
「まさか……あなたが来てくれるなんて……」
想えば入学して初めてのコンテストの日。その絵に一目惚れした彼女は学園中を探し回った。
美術室で見た愛莉の姿は、今でも忘れることが出来ない。
今までは先輩の姿が、描かれた絵が見られればそれでよかった。
だが今年は最後のコンクール。逃せばこの想いは二度と伝えることが出来ない。
「絵……描く前に手を握ってもいいでしょうか?」
「は、はいっ!」
チョコがそっと手渡され――
それは暖かくて。
溶けてしまいそうで。
今年は最高の絵が描けそうだった。
●
という訳で。
そう。何故か今日は家庭科室が開いている。
教師の粋な計らいだろうか。それとも生徒会の手回しだろうか。
さておき。これは千載一遇のチャンスである。
なぜなら、こういう日は自由に使っていいと決まっているからだ。
「はーい。そういう事でチョコレイトケーキを作ろうねー!」
「はい、お姉様」
そんなルーニカの言葉に頷いたイリスは、本当はこっそりとチョコ作りをしようとしていたのだ。
お姉様へ日ごろの感謝のつもりだったけれど――
「合言葉は皆笑顔だ、いいね!」
前に立つ二人へ向けて、アラクをはじめ後輩達が一斉に返事した。
そう。甘い物作り放題の食べ放題。アラクが胸の前で可愛らしく拳を握る。
「ケーキと言う甘い響きと、チョコレイトという少し苦味の聞いた響き。不味いわけがないだろう!」
果敢なリーダーシップを取るルーニカの隣が、イリスにとっては一番落ち着くのである。
何より。こうしていると、顔も知らない男性に嫁ぐことがほぼ決まっている――そんな未来への不安が和らぐ気がして。
「賛同してくれる者は思い思いに作ってみて欲しい。さぁ体現するんだ! 君の情熱を!」
後輩達と共に頷いたイリスは、調理器具の用意。そして湯せんの準備を始める。
「今この貴重な時間を、一時も無駄にするんじゃないぞー!!」
未来(さき)の事なんて分からない。
理解も祝福もされないかもしれない。
この手を取ったことを、後悔しない為に――
「お姉様方、焼き終わったらお茶会にしたいな」
アラクが小首をかしげる。
「はっはっは、もちろんだ!」
ルーニカの盛大な肯定に、アラクは可憐な白髪の下で頬を染めた。
アラクが作ったのは簡単で美味しいシフォンケーキ。ふんわりきめ細やかに、けれど舌の上ではしっとりするように焼き上げるのがコツだ。
切り分けて、たっぷりのクリームを添えて。
結局、紅茶と共に並んだのはチョコレートやケーキの山で。なかなか結構な量ではあるが。
「はいはーい」
ルナシャが勢いよく家庭科室の戸をあける。
「ルナシャさん、よいところへ」
イリスが微笑む。同じクラスの頼もしい味方が現れた。
「よくぞ参った!」
「自称『チョコ試食委員会』の私にお任せあれ」
どんな出来栄えでもばっちり味見。美少女のお手製。それだけで尊き価値があるのだ。
という訳でルナシャは、テーブルに顎をのせて。上目遣いにあーん。
「ルナシャさん、可愛らしいです」
まずはイリスの生チョコレート。
「あまーい」
幸せそうなルナシャの顔に、イリスが頬を赤らめる。
「うんうん。その照れた顔もきゅーと」
それからルーニカお手製のザッハトルテ。
「お姉様方のお菓子美味しい……!」
アラクの口元がぱっとほころんだ。
最後に。後輩の子が作ったケーキが――
「しょっぱー……砂糖と塩、間違えてない?」
「はわわわ、塩だったです」
「誰だー紛らわしいトコに調味料置いたのー?」
あ。
……やっば、私だったかも。
そんな家庭室近く。西側のひっそりとした場所に化学室がある。
猫のようにくりくりと、好奇心にあふれた瞳がピペットから溢れる赤い液体をみつめている。
「これと、これを混ぜると……」
一滴。二滴。
フラスコの液体に沈み、拡散して往く赤い渦は――
「おや?」
シアンが慌てて立ち上がる。
「レンジーさん、これ、光って!?」
――爆発、である。
化学室に広がる桃色の煙に、レンジーとシアンは腕で顔を覆う間もなく。
「ふにゃあ……?」
ふわりと甘い香りにつつまれて。レンジーは椅子の前に両手をかけシアンの顔を下から覗き込む。
とくんと、シアンの心が跳ねた。
「……なんだか今日はレンジーさんが愛らしく見えます……」
「シアンくん……君って、とっても魅力的だにゃー」
なぜいままで気が付かなかったのか。
シアンのスレンダーな腰に頭をすりすりと。そのまま抱き着くレンジーの喉に、シアンはそっと指を這わせた。
ころころと幸せそうな音がする。
こんなに。
こんなに愛らしいのに。
「にゃあにゃあ!」
なんだか甘い香りがする化学室の上。手芸部の部室でガドルはマフラーを編んでいた。
窓に背を向け隣同士で。同じようにマフラーを編んでいるのはカシエである。
ボーイッシュなガドルとは対照的に、淑やかなカシエは編み物も上手でいつもこうして教えてもらっているのだ。
毛糸を足そうと手を伸ばした時――
「あっ……」
――小さな声をだしたのはどちらが先だったろうか。
絡む視線を互いに外し、先に口を開いたのはガドルだった。
「鎖編みが上手に出来なくって」
上気したガドルの頬の色をボブカットもシースルーバングも、隠してくれないから。
「ああ、ここはね……」
顔を近づけたのは、網目をよく見るためだったけれど。
桃色に染まる二人の頬がゆっくりと近づいて。
「せ、先輩……」
ふと顔をあげれば、みずみずしい唇が今にも触れ合いそうな距離にある。
明るい色の豊かな髪が指先に触れ。ふわりと優しい太陽と石鹸の香り。それはまるで上質なカシミヤのようにガドルの手を撫でる。
見つめ合う二人は。茜色の夕日が差し込むその部屋で――
●
生徒会書記であり、風紀委員でもあるソフィアは憂いている。
学校は学び舎であるのだが、校内はあまりに騒がしかったから。
とはいえ注意すれども校内中がこれではどうしようもない。
今日の所は全てを諦め、独り静かに勉強でもしようと、こうして図書館に足を踏み入れたのである。
このままではいけない。
綱紀粛正。立派な家柄の殿方に嫁ぐに相応しい、女性としての立ち振る舞いを身に着けるために。
騒然とした空気に飲まれないように。ソフィアは数冊の本を選び取る。
「わ、私ったら……!」
表紙には清楚な百合の花が咲き、二人の少女が見つめ合うシルエットが描かれ。
「いえ、しかし、無理解なままに校則で縛り付けるのも悪手。知っておくべきでしょう」
言い聞かせるように、彼女は本を開いた。
そう。
本の世界はいい。
現実を忘れられる――
茜色の夕日に照らされ、一人しずかに頁をめくるノインが嘆息する。
毎日繰り返される退屈な日常。何が『ご機嫌よう』か。誰も彼もがニコニコと。
とはいえ何よりも彼女はそんなことも言えない自分自身に腹を立てていた。
そんなことを考えながらも、頁はめくれていく。
活字を目で追うだけで。気になった言葉一つでも頭に入れば御の字だと。そう言っていたのは誰であったか。
そうしている間、熱い視線でずっと彼女を見つめていた少女がいたことにも。そして机にそっと置かれたチョコレートと手紙にも気づかぬままに。
図書館はいつも静かである。
部屋の隅では今日も、赤毛を三つ編みにした少女ウィリアムが活字に視線を落としている。
その姿は言外に『私に構わないで』と告げていた。
――けれど。
様々な想いを胸にシェリルは彼女の前に立っている。
「なに?」
ウィリアムの冷めた視線と、シェリルの怜悧な瞳が交差する。
執行者シェリーと言えば生徒会の影。焼きそばパン一つで、生徒会から様々な依頼を請け負い執行する存在だ。
美しい白い髪。運動神経抜群成績優秀。生徒達からは恐れられていると言っても良い存在だ。なんとうか。っょぃ。
彼女はそれでも影に徹している。抱く想いは『いつも皆が幸せになれるように』と。
けれど、この日は。
「あなたの事を――」
ウィリアムが顔を上げる。
「いつも想っていた。私のこの気持ちを受取って欲しい」
今日という日に幸せを得たいのは彼女も同じだった。
ぱさりと本が落ちる。
本の中の世界だけがあればいい。
今日まではそう思っていたのに――
そんな中庭へ、三階の方からひずんだギターの音色が聞こえてくる。
音楽室で行われる黒羽のライブはいつも人気で、なかなかチケットが手に入らないのだ。
それも今日はバレンタインライブ。熱気は否応にも高まっている。
「今歌える歌を歌うだけだ。楽しんでいこうぜ!」
メンバーが頷き合い、一瞬のベースソロからヘヴィなギターリフが刻まれる。
そこに乗る、ハスキーな声のハーモニー。
「黒羽さまぁ~!!」
オーディエンスの少女達は瞳を輝かせて、歓声をあげ続けていた。
一方の中等部。
吹奏楽部部室の前で、一人の少女が中をじっと見つめていた。
金髪に青い目。ツインテールの可愛らしい女の子だ。
視線の先に居るのは二年生のLumiliaお姉様。ちょうど教員や先輩後輩、日ごろお世話になっている人達へ小さなチョコレートを配り終えた所だったのだが。
「あの」
扉が開く。
「どうしましたか?」
一年生の後輩。シエラ……ではなく、確かリオレットと言っただろうか。部活は違うが、委員会で話した事がある。
「先輩! あの……その……私……」
消え入りそうな声。後ろ手に隠すチョコレートが震えている。
「わ、わらひと……つき、付き、付きあってください!!」
ついに、言ってしまった。数か月前、音楽祭でのフルート演奏が心を焦がして離さなかったから。
唐突な告白にLumiliaは僅かにたじろいだ。両手を伸ばして差し出したのはチョコレートが入ったハート型の箱である。
そうは言われても彼女自身、好意を向けられること自体があまり得意ではない。
「ダメですか!? う、うぐ、えぐっ」
「……な、泣かれても困りまっ」
だが、もう後には引けない。
「わ、私の……私の! 全てを捧げますからぁ!!」
全身全霊をこめた体当たりだ。というか凄いこと言ってる。
「……もう、今回だけですよ……!?」
そう言うLumiliaは――押しには弱かった。胸に飛び込んできたリオの髪をそっと撫でる。
白く儚い月の光のように、ふわりと夜香花の香りがした。
●
「こちらの式が成り立つ時に、xで偏微分すると」
「へんびぶん」
「えっと、さっきのこれです」
悠凪の指先が頁を手繰る。手早い指示はしっかりと理解出来ていることの証明だ。
「おぉ……」
言われる通りに思い出してみれば、同じやり方で新しい問題が解けてしまった。
しかし、なぜ勉強させられているのだろう。
勉強は苦手なリジアだが、こうして優等生の悠凪に教えられるようになってから、しっかり赤点から免れている。
この学園の授業はかなり進度が早く難しい。
赤点をとってもらっては困るというのは事実ではあるのだが。
それよりなにより。大好きなリジアとこうして一緒にいることがなにより嬉しいというのは心にとどめて居る事実だった。
「冬葵……これは、なんと読む」
「これは分かるのでは?」
けれどそれは、今度は分かることを聞いたリジアにとっても同じという気もする。
「……分からなくはないが、教えろ」
リジアがじっと覗き込む。悠凪の鼓動は聞かれてしまっているだろうか。
一通りの課題が終われば、後は。
「あぁ、そういえばバレンタインデーでしたね」
まるで思い出したかのように、悠凪は可愛らしい小箱を手にとる。
「……バレンタイン。……なんだったか……お祝いの日?」
「です。というわけでチョコをどうぞ?」
用意周到な悠凪であるが。
「……何か、欲しいものはあるか」
リジアだってお礼がしたい。
そんな悠凪が欲しいのは。
――
――――
閉め切った教室の窓は喧噪から遮られ。
夕暮れの、ただ温かで優しい光だけが二人を照らしていた。
「こうして同じ学校に通えるなんて」
バレンタインだからだろうか。それとも目の前の少女が居るからだろうか。少しだけ甘い香りが残る教室で。
「幸せで死んでしまいそうです」
シキがぽつりと告げる。胸がそわそわして、頭がくらくらして、とても落ち着いていられない。
「はわわ、死んじゃダメですよ?」
彼女はいつもこうしてティミ・リリナールことリリーの心を擽って行く。
「……あ、本当に死にはしませんよ」
どこか少しだけ危うくて。静謐で。さながら日本刀のように美しく。そして鋭い少女。
胸元に手を置いたティミが教室の後ろに向かって歩いていく。
お知らせのプリントと、学級新聞と、それから。
「……あの、私、リリーさんに伝えたいことがあるんです」
シキの手の平が彼女の横を通り過ぎ、壁にそっとあてられた。
「シキさん?」
振り返ったティミが思わず視線を落とす。
「私と、出会ってくれて……必要だと言ってくれて、ありがとうございます」
微かな息遣いさえ聞こえる距離で。
「……私にも、キミが必要です」
「あ、あの、その……私も」
シキの美しい黒髪が頬をくすぐって。
「他の誰でもなくて……今、ここにいる、リリーさんが」
細く白い指先が、ティミの顎を優しく支える。
逃げ場のない視線の先。静かな赤い瞳が間近にあって――
頬の薄桃は、沈みかけた夕日のせいだけだろうか。
●
「この学校って、仲良さげな人達多いよねー」
校門へ向かってのんびりと歩くリンネが、リィンに語り掛ける。
「うん」
それは誰とでも話しやすいという事でもあって。
今日も教室でみんなと談笑したり、お昼を食べたり。
チョコを渡す所を軽く冷やかしてみたり。リィンにまとわりつく同級生を威嚇してみたり。
そんないつも通りの日常が、通り過ぎようとしている。
リンネとリィンには、この日も特別なことは何もない。
けれど、それでいいのだろう。
ただ。登校した時も。休み時間も。今も。
いつも通り。
二人はずっと隣で。
ずっと手をつないでいるのだから――
一般の生徒達は、そろそろ帰る頃だろうか。
「ごめん、待ったかい? 渓」
部活の後輩に捕まってしまったというロズウェルの荷物はちょっと重そうで。
「かっこいいんだし、チョコ沢山だったんでしょ」
そんなことをいいつつ、門の外へ歩いてゆく。
「確かにチョコは貰ったけどね……」
でも。
「一番欲しい人からは貰えてないんだ」
去り行く夕日に照らされて、染まった頬は見えないけれど。
「それだけもらったなら、一個ぐらい増えたっていいでしょ?」
渓は歩いたまま。視線も合わせず、突き出すように小さな箱を見せる。
「え?」
立ち止まって。
「渓が僕にこれを? ほんとに?」」
つんとした普段の彼女からは想像も出来なくて。
「い、いらないなら。私が食べるよ」
「あ、いや、いらないとかじゃないよ! 嬉しい、凄く嬉しくてさ」
大事にしまって、じゃなくて。ちゃんと味わって食べたい。
「……よかった」
口を結んで俯く渓に。
「じゃあ、はい、僕からも」
いつも元気な渓の瞳がうるんだように見えて。
「渡す気は無かったんだよ? 不格好でさ、とても君に見せられる物じゃないから」
「いいよ」
そう言った渓の声がかすれて。うれしくて。
だってロズウェルが精一杯の気持ちをこめて作ってくれた、チョコレートだから――
この時間になればアニー達生徒会もようやく仕事を終え、生徒会館に戻れる。
ほっと一息つけるのだが、アニーはちょっとそわそわしていた。
ティータイムに使う第二会議室では、彼女お手製、自信作のチョコレートケーキが待っている筈だから。
この日、この時のために何度も何度も練習を重ねてきたのだ。
「それでは、わたくし♡は先生方にご報告をして参ります♡♡」
そう言ったカタリナ♡お姉さま。
居並ぶシェリルお姉さま。ソフィアお姉さま。クローネお姉さま。オロディエンお姉さま。
そうそうたるお姉さま方は食べて下さるだろうかと、そんな風に気後れしてしまう。
「わたくし、一足先にお茶の準備をして参りますわ」
はじけそうな期待と、押しつぶされそうな不安に、アニーが言の葉を紡ぎ。
「アニーさんもお疲れなのではなくて?」
「大丈夫ですわ!」
居てもたってもいられない。
真っ赤になった顔を見られてしまうだろうから。
もし。もしも。『あなたが作ったチョコレートケーキが毎日食べたい!』なんて言われたら。
お姉さま方のお弁当だって毎日つくれてしまうから。
お湯も沸かして紅茶もいれなければ。
アニーはお姉さま方へ可愛らしく頭を下げ、中庭の向こうへゆっくりと歩いてゆく。
どんなに急いでいても、スカートのプリーツを翻すようなはしたない真似なんて出来ないのだから。
紅茶はカタリナお姉さまのプリンスオブウェールズ。それからダージリンオータムナルのミルクティ。夏摘みのウバ――
お姉さま方の好みはばっちり把握済なのだ。
日は落ち。金色に輝いていた木々は、瑠璃色の空へ黒いシルエットを落としている。
そんな誰も居なくなった中庭へ。
図書館から出てきたヘルモルトは、ほうと溜息をついた。
世間はバレンタイン。この学園も甘い空気で一杯で。
結局こんな時間にならなければ静かにならないとは。
けれど高等部の二年生ともなればもう受験生なのである。
大学までエスカレーター式に進学する生徒の中にはのんびりした空気もあるが、将来を決め外部への受験を志す生徒であれば騒いでもいられない。
そんな時。
「きゃっ」
物陰から飛び出し来た子猫に驚いたのだろうか。背の小さな少女が足をわたわたともつれさせ。そのまま思い切りつっぷした。
中等部の子だろうか。
「大丈夫?」
そう言ってくれたのは、ものすごくきれいな人だった。
「頭でも打ってたら大変よ、立てる?」
「……っはい」
小柄に見えても彼女は空手部の部長。けれど高等部のお姉様の肩は華奢だけど、すらりとしていて。
ふわりといい香りがする。
可愛い子だ。月の光に照らされた短めの黒髪は綺麗に切りそろえられていて、肩にかかるヘルモルト自身よりも少し短いだろうか。
「ありがとうございます」
頬を染めてはにかみ手をひかれる少女の手はあまりに小さくて。細くて。
彼女は思わず――
(食べちゃいたくなる)
悪い癖だ。
だけどバレンタインだもの。
(仕方ないわよね)
どんな可愛い声を聞かせてくれるのだろう。
「お名前は?」
いたずらな微笑みに、答える少女の胸は高鳴り。
「わたしローラ……ローラン子・ガリラベルク!」
成否
成功
MVP
なし
状態異常
なし
あとがき
ごきげんよう。
夢を覚えているのも、忘れてしまうのも。皆様次第でございます。
全員描写のつもりですが、万一の抜けはご連絡下さいませ。
それではそろそろ夜が明けましてよ。
pipiは皆様の、またのご参加を心待ちにしております。
GMコメント
ごきげんよう。
pipiですわ。
●目的
魔法をかけられた日の夜。異世界のゆりゆり『バレンタイン』な夢を見る。
とにかく皆さんは、お嬢様学校に通う中学生か高校生の美少女です。
がんばってみてください。
バレンタインというのは夢の中の世界にある行事で、『グラオ・クローネ』に似ています。
オープニング中の杖の使用回数とやらは、参加人数分でぴったりです。
情報確度はAです。
というか全般的に超ご都合主義です。些末な事は気にしなくて大丈夫です。
●重要な注意!
この依頼は深刻なキャラクター性の崩壊をした夢を見る可能性があります。
またプレイングによる指定がない場合、超適当にグループ化されて、勝手にゆりゆりさせられるかもしれません。
ちょうど誰もいなければ、名もなき美少女とゆりゆりさせられます。
あえてカップリング相手に名もなき美少女を指定しても構いません。
そのほうがよろしい場合は、そのようにご指定下さい。
相棒と一緒に参加出来なかった場合、相方様の描写は出来ませんが、一人その方への想いを綴るのも良いかもしれません。それもまた百合です。
美少女は美少女のまま。
大人も子供も、おじいさんも、動物も。勇ましい名前の人も。夢の中ではみんな中高生の美少女になります。
キスやハグなどのデリケートな表現は、プレイングや感情等で双方の合意が明確に認められる場合でなければ描写されません。
でも落とした消しゴムを拾ってくれる隣の子と指がふれあったら、どきどきしちゃいます。
すごく勝手にどきどきしちゃいますので、十分にご注意下さい。
もちろん年齢制限が必要になるような描写は一切ありません。
●相談
ペアを組むなり、おっさんにつっこみをいれるなり、お好きにお使い頂ければ幸いです。
●ロケーション
夢はいわゆる現代日本のような世界です。
どちらかというと可愛い女の子しか出てこない漫画とかアニメとか小説みたいなノリです。
キャラクターにはそんな異世界の知識が一切なくても、夢の中ではなぜか疑問も違和感もなく生活出来てしまいます。
むしろ現実世界の事なんて、夢の中ではさっぱり良くわかりません。
夢を見る前や後、現実世界の心情等は一切描写されません。全部オープニングの前半部みたいな感じです。
別にお嬢様言葉とかじゃなくても大丈夫です。
とにかく美少女です。
ですがノリノリで夢を過ごさないと、きっと寂しいことになっちゃいます。
●出来る事
中等部と高等部は、校庭と中庭を通じて隣り合っています。
ご自由にお過ごしください。
A:放課後の家庭科室
特別に解放されており、ケーキやチョコレートを作ったり、一緒に食べたり出来ます。
B:昼休みの中庭
かわいいお弁当を食べたり、おしゃべりしたり、こっそり本を読んだり出来ます。
イチゴミルクの紙パックジュースが人気です。
C:昼休みの食堂
おしゃれなランチや、購買のパンが食べられます。
D:生徒会館
生徒会の一員として、ケーキやお茶を楽しめます。
役員とか生徒会長やりたい? どうぞ!
会長が2人とかいたらどうなるって?
夢だし!
E:放課後の中庭や教室
みんなでおしゃべりしたりできます。
誰も居ない教室で、相手を壁際に追い詰めたり、愛の告白したり出来ます。
F:その他
図書室とか、保健室とか、音楽室とか、部室とか、ありそうなものはだいたいあります。
別に授業中とかでもいいです。
更衣室? シャワー室? 植物用の温室? 温水プール? 体育倉庫? いいですとも!
●プレイング記述
下記の注意を必ず守り、プレイングを書いて下さい。
一行目:A~F(出来る事)
二行目:同行者名(ID)(無い場合は不要。複数人で組む場合は【グループ名】でタグを作り表記して下さい)
三行目以降:自由なプレイング
Tweet