PandoraPartyProject
真夏の恋のおまじない II

ぎい――と。
重い木戸が開く音がする。
石造りの薄暗い室内へ、にわかに陽光が差し込んだ。
「よいしょっと」
ゆっくりと階段を降りてきたのは、一人の女性であった。
「勉強頑張るのはいいけど、ちゃんと食べなさいよ。はい、おべんと」
「おいおい、無理しないでくれよ」
「はいこっちは、フユツキさん、でいいかしら? はじめまして。
タータリクスが、いつもお世話になっております」
「おや、これはありがたい。クオン=フユツキだ。
こちらこそ、弟君にはいつもお世話になっております。
ところで、こちらはター君の彼女さんかい?」
「そ、そそそ、そんなわけないでしょう。姉さんだよ、って前に話したでしょう」
タータリクスは見て分かる程に狼狽えた。
「話したもなにも、ちゃんと『弟君』て言ったぜ。イッツ・ジョーク!」
「ほ、ほほ、ほんとに。もう、フユツキさんは!」
「さすがに無礼だったね、この通り謝ろう」
そんな二人のやり取りを、姉は笑っている。
初秋の残照を思わせる、柔らかく暖かな顔で――
内向的なタータリクスは、これまで女性と付き合ったことなど、ありはしない。
クオンというあけすけな友人は、そんなタータリクスをこうして度々からかうのだった。初見は苦手なタイプであったが、今では意気投合して錬金術の研究を手伝ってもらっている。
旅人(ウォーカー)であるクオンの知識は極めて深いようだが、この世界の法則には適合しないものがあまりに多い。一方のタータリクスは、この世界での技術こそ持ち合わせているが未熟な点も多く、また少年時代にラサの『アカデミア』で師匠を失ってから、たびたびスランプに悩まされていた。
平たく言えば、補い合うにうってつけの同士だったのだ。
「それより天気もいいのに、外で食べたら?」
「おさそいはうれしいけど、薬液を加熱しててね、目が離せないんだ」
「姉さんは寝ていてくれよ。昨日も熱を出しただろう」
「そんなに心配しなくてもいいのに。それじゃ少し休んでいるから、ちゃんと食べてね」
ゆっくりと階段をあがって出て行く姉に、ありがとうは言いそびれた。
ひどく忙しかったのだ。
実験室では再び、ランプの明かりだけが揺れていた。
「いい姉さんじゃないか」
「さすがにちょっと過保護でしょう、僕だって良い歳なんだぜ」
「あっはっは、違いない。てか美味いな、このサンドイッチ。お礼は弾まなくっちゃな」
「いっそフユツキさんが、姉さんとくっついてくれればいいのに」
クオンはそれに答えなかった。
タータリクスの視線はフラスコに注がれており、クオンの表情は知る由もなく――
「姉さんの料理は、美味しいんだ。父さんと母さんの味を改良してるらしいよ。
病気が治ったら、父さんと母さんの店を復活させるんだーって。いつも言ってる」
「いや、なんか悪いこと聞いちゃったな。ご両親」
「死んじゃったのは子供の頃だから。フユツキさんは気にしないでよ」
実験は往々にして、目を離すには短く、待つには長すぎる。
いつもは良く喋るクオンに合わせるタータリクスだったが、この日はめずらしく先に口を開いた。
「姉さんは子供の頃から、身体が弱いんだ」
タータリクスが錬金術を目指したのは、元々は姉の病気を治す為であった。
今では立派に生活出来ている訳であるから、悪くない仕事だ。手に職というヤツである。
「ほんとかよ?」
「いや本当の切っ掛けは、子供の頃だったのかもしれない」
それは幼少期の、ちょっとしたハプニングの事だった。
ある夏の日に、タータリクス少年は森の中で薬草を摘もうとしていた。
大人達に黙って危険な森に入ったことは後でしこたまに叱られ、詰問の末に妖精と出会った事を白状させられた。
タータリクスは心の中で、妖精姫に何度も謝った。
とはいえ大人達からすれば、子供がそうした幻想を抱くことは珍しくない。
よしんば本当に妖精だったとしても「たまたま危険な魔物でなくて良かった」という話だ。
あの当時にグリムアザースなどという存在は、人のうちには数えられていない。
けれどタータリクス少年は小さな妖精の姫君から受け取った、霊薬の小瓶を隠しもっていた。
タータリクスはまだ嘘をついていたことを、ひどく咎められた。
ついに全てを白状させられた日にも、少年は心の中で妖精姫に何度も何度も謝った。
けれど周囲の大人達は笑っただけだった。
どうせどこかで拾った小瓶に、蜂蜜でも溶かして飲ませたのだろう。
ごっこ遊びに違いない。けれど「そういうのは、そろそろ卒業しなさい」。
結局はそんな結末であったのだ。
少年は罪悪感と純朴な正義感を、心の内に戦わせて耐えた。
「あの薬で、たしかに姉さんは、だいぶ元気になったんだ。
もっと小さな頃は『大人になれないかもしれない』なんて言われてたのにさ」
姉が生きたのは、たかが滋養強壮薬一本の成果ではないだろう。
姉本人が頑張った結果かもしれない。
治療師の腕が良かったのかもしれない。
あるいは治療師が姉の病状を多少悪く言っていただけかもしれない。
いずれにせよ人を助ける薬に関する強い思いは、少年の心に深く刻まれたのだ。
――いつか、あんな薬が作れるようになりたいなあ……。
その想いは、タータリクスが錬金術師を目指した原点となった。
実際のところ、森で出会った妖精のお姫様に、少年はどこか胸の奥が熱くなるのを感じたのだろう。
惚れ薬等と誤解された栄養剤は――妖精郷の霊薬は、けれど小さな恋のおまじないでもあったに違いない。
当の少年は一滴も口にせず、そも本来の効能とは、まるで違った結果ではあったのだけれども。
恋に理由なんて必要ない。恋の神様はいつだって気まぐれだ。
やがて少年は大人になり、心に燻っていた想いなど、いつの間にか綺麗さっぱり消え去っていた。
おおよそ初恋などというものは、ある種の薬液のように時間が揮発させてしまうのだ。
幼い日のものであれば、なおさらに――
「けど。研究で救われるのは、きっと姉さんだけじゃないはずなんだ」
人は想いを昇華する生き物でもある。これは純朴な『正義感』であったのだろう。
「なるほど……立派なもんだ。普通に尊敬しちゃうぜ」
現実を生きる中で、幼い日の思い出は遠く色あせて行く。
この時タータリクスの心にわだかまり続けていたのは妖精姫の想い出ではなく、在りし日のアカデミアで『しでかした』事件についてだった。
錬金術の道を目指したタータリクス少年は、ラサの『アカデミア』という今無き研究所に入門した。
そんなアカデミアでの師――博士は錬金術師ではあったが、薬学よりは生命研究に通じていた。
勉学の師が『学びたかった方向と違う』というのは良くある話で、生真面目なタータリクス少年はそれはそれで、一生懸命に学んでいたのだ。
――だがある日、事件は起こった。
師はタータリクスを助手として、外道の法を用いて人間を怪物へと変貌させてしまったのである。
それを切っ掛けに、アカデミアは崩壊した。
当時の生徒達――ブルーベル、リュシアン、そしてタータリクス達は、皆散り散りとなったのだ。
ブルーベルやリュシアンは、きっと自身を恨んでいるだろう。
そして怪物に変貌してしまったジナイーダは――
タータリクスは、実験の全容を知っていた訳ではない。
悪いのはタータリクスではなく、師だったのかもしれない。
だが知らぬ間に、その片棒を担いでしまったのは事実だった。
だからこそ正義感の強い少年であったタータリクスは、心に罪の意識と深い傷を負ったのだった。
故に一時期のタータリクスは、錬金術など見たくもないと閉じこもっていた。
それでも現実というものは金(かね)を欲するものである。
錬金術という単語は皮肉なもので、無から金(きん)を生み出せる訳でもない。
生きていくためには、とにかく食い扶持を稼ぐ手立てが必要だった。
姉の病状も良いとは言えず、生活を支える手立ては、やはり錬金術しかなかったのだ。
タータリクスは安価なポーション等を売り、生活を支えていた。
だが書物だけを頼りとする独学は、得てして行き詰まりがちでもある。
そんな時に、たまたま出会ったのがクオンだった。
「けどまあ。さすがにター君はないでしょう」
「そりゃ嫌だろ。いい歳になって、母だ姉だのに感謝はしても、縛られたくはないだろ」
「はぁー。上手くいかないなあ。才能、ないんだろうなあ……」
思い出話は枯れ果て、話題はいつもの愚痴に移ろい。
――それから数日が過ぎ去った。
今日も今日とて、実験が続いている。
今日も今日とて、姉はお弁当を作り運んで来る。
姉はいつもと変わらず、実験に熱中するタータリクスの後ろから、何やら話しかけてきて。
けれど実験はいよいよ佳境を迎えていた。
疲労は心身ともども限界に達しようとして――いや、越えていたのだろう。
だから、言ってしまったに違いない。
「もういい加減やめてくれよ!」
「え、と。ごめんねター君、あの、そんなつもりじゃ」
「ター君、ター君て、ガキじゃあないんだぜ! 三十路越えてんだよ。僕も、あんたもさあ!」
タータリクスは声を張り上げた。
「おいタータリクス……お姉さん、後で良く言っておくから、ごめんね」
実験からは、目も、手も、離せない。
今失敗すれば、ここ数日の成果が吹き飛んでしまう!
「あの! えっとね。ごめんなさいフユツキさん。
ターく……タータリクス。お弁当はちゃんと食べてね。
お姉ちゃん、ちょっと買い物に行くから、心配はしないでね」
姉は踵を返し、実験室には再び静寂が訪れる。
「手元がおろそかになってるぜ、お姉さんのことか?」
「いや……」
「心配してんだろ」
「……そうだね。ひどいこと言ったなって」
「ビンゴ! オレが見てきてやるよ。市場のほうだろ? 実験に集中しとけって、仕事だろ」
「ありがとう……フユツキさん……」
「その他人行儀な呼び方、いい加減どうにかしろよ。クオンて呼べって」
クオンが去った後も、実験は続いていた。
数刻が経過した頃だろうか。
フラスコの薬液が、淡い輝きを放ち始めたではないか。
「……っ!」
これまでタータリクスが作ったものよりも、品質の高いポーションだ。
タータリクスはあわてて、羊皮紙に書かれた魔法陣と魔術式の計算にチェックを入れる。
この配合なら、間違いなく霊薬の――些細かもしれないが――改善になる。
姉の病状も、この品質ならもう少し良くなるかもしれない。
「っしゃああ!!」
腕が、膝が、肩が震えた。
「よっしゃ! よっしゃ! よっしゃああ!!」
心臓がはじけそうだ。
どっと、疲労がやってきた。
目がしぱしぱする。なんだか息切れだってしている。
そもそも数日間、ほとんど寝ていなかった気がする。
……酒でも飲もうか。
「いやいっそ、ポーション飲んでやるか? でも、見せなきゃな。フユツキさんと、あと姉さんに」
そしたら、謝らなきゃ――
そんな時だ。重い戸が開く音が聞こえたのは。
「出来た! 出来たよ!! フユツ……キ、さん。――ッ!?」
「すまない……間に合わなかった」
クオンが抱えていたのは、ぐったりとした姉の体と、魔物の死骸だった。
剣の一撃で仕留めたであろう魔物の残骸を投げ捨てると、クオンはタータリクスの姉をそっと横たえる。
「姉さん……? 姉さんッ!」
すがりつくタータリクスに言葉はかけず、クオンは数歩後ろに下がった。
「オレがもう少し早く出ていれば、こんな事には」
呼吸はない。
脈拍もない。
服がじっとりと黒く濡れている。
手のひらについたぬるりとした感触を、ランプの光が舐め――赤い血だ。
「たすけ、ないと。これ、出来たんだ、姉さん。ポーションだよ」
姉の口に傾けた霊薬はとぼとぼと零れて行くばかり。
傷口とおぼしき場所へかけても、なんの変化も訪れない。
「言いにくいが、お姉さんは――」
「死んでなんかいない!!」
認めない。絶対にみとめないぞ。認めるもんか! まだ謝ってもいないんだ!
ありがとうって、いつから言ってなかったんだっけ。
今はどうだっていい。謝罪もお礼も、後回しだ。
このポーションは治癒の効果があるんだ。どうだ。
こっちは研究用に買い付けた、高額なものだ。これならどうだ。
だったらこれだ。とっておきもとっておき。闇市で仕入れた秘薬中の秘薬だ。
なんで。
なんで動かないんだ。目を覚ましてくれないんだ。
なんで、どうして!
死んでなんかいない。死んでる訳ないんだ。だって、さっきサンドイッチをくれて。
おいしかったんだ。暖かかったんだ。
暖かいんだ。姉さんは。姉さんの身体は。
――死んでないならさ。なおせる薬。あるんじゃないの?
ふいに響いた声に、タータリクスは顔をあげた。
「リュ……シアン……」
それはアカデミア時代の友人であった。
「久しぶりだねえ、タータリクス……」
その声は、ぞっとするほど冷たくて、心の中を掻き毟るほど穏やかだった。
「どうして、ここに」
「そんなのいいじゃない」
リュシアンが笑う。
「それよりさ。ジナイーダも、君のお姉さんも。治せる薬があるんじゃないの?」
「……どこに」
「君が言ったんだろう。おとぎ話の国――アルヴィオンにさ」
「妖精……郷……アルヴィオン……」
「行きなよ。妖精郷にさあ!」
「行きたい、行くんだ。行って……行けば、あのお姫様が、きっと。会いたい」
「会おうよ、そのお姫様に」
「会いたい!!」
「変えようよ、この運命を」
「変えたい!!! 僕は妖精のお姫様に会って、運命なんだ、これが、本当の!」
タータリクスの力が爆発的に膨れ上がる。
たとえば『正義』という罪への罰が、『色欲』の呼び声だったとしたら――
「ははははははは!! 会いに行くよ、マイ・リトル・プリンセェス! 僕は運命の人だから!」
――なるほど。目的が捻じれるか。だが上手く行ったようだ。
クオンは壁に背を預け、腕を組んでいる。
「協力に感謝しよう。これからも上手くやりたいものだな」
タータリクスに聞こえぬように述べたクオンを一瞥すると、リュシアンは表情一つ変えること無く去って行った。
やるべき事はまだ残って居る。
「さあ、急いでお姉さんを凍結するんだ。肉体を保存しろ。
妖精郷へ行く方法は、これから一緒に考えようじゃないか」
クオンはタータリクスの肩へ手を差し伸べたが――
「どうして? 僕はね、お姫様に会いに行くんだ。だって――運命の人だから!」
答えを聞いたクオンは、己が額を手のひらで押えながら笑いをこらえるのに必死だった。
反転という代物が、こんなにも面白い現象だとは!
「お姉さんの遺体は、どうにかしないといけないね」
「お姉さん? 遺体? うわ、なにこれ。死んでるし。
これ誰だっけ……まあいいや。血が出てるし……キッタナイ! こういうの駄目なんだよなぁ!」
タータリクスは姉だったもの――死体を蹴りつけると、靴についた血を布きれで拭った。
「じゃまだなあ、これ」
「では廃棄処理しておこう。腐敗、崩壊。この際だから教えておく。黒化(ニグレド)の基本だ」
「何からなにまでありがとう……フユツキさんは、本当に恩人だよ!」
「……は、は、は」
「そんなことより、急いで研究しなくっちゃあねえ!」
「ああ、頼むよ。その技術が頼りなんだ。タータリクス君」
魔種になってくれた、君のね。
旅人に力なんてものは、ありはしない。
だったら『わらしべ長者』を、させてもらうとしよう。
パワーロンダリングとでも呼ぶかね。別になんでも構いはしないが。
魔種リュシアンと通謀したクオンは、かねてよりタータリクスの姉を殺害する計画を練っていた。
姉自体がどうというより、タータリクスの心に強い衝撃を与えて、容易に反転させるためだ。
旅人であるクオンは、無辜なる混沌の法則に縛られ、かつての世界同様の力はなかった。
だが魔種というものは、そうではない。
多くの魔種は、反転と同時にその力を飛躍的に増大させるものだ。
ならばクオンの技術と親和性の高い『錬金術師』を『反転』させたなら、どうか。
その力はクオンにとって、利用しやすいのではないか。
こうしてついに『運命の時』がやってきた。
タータリクスが実験に集中し、姉が一人で外出した、その時だ。
クオンは姉を殺害し、アリバイに使うための魔物も斬り捨てて、犯人に仕立て上げたのだ。
それから『原罪の呼び声』を聞かせるために、事前に話をつけていたリュシアンを呼びつける。
タータリクスはクオンの計画通り、もののみごとに反転してくれた。
おとぎ話の――しかしクオンが実在を確信した――妖精郷への足がかりは、こうして成った訳である。
一連の事件の中で、ブルーベルと共に二種の秘宝を手に入れたクオンは姿を消し――
アルヴィオンには『冬』が訪れたのであった。
――ばかなものだ。死人がよみがえる訳がない。
その程度の『おくすり』で、覆水が盆に返るものか。
他ならぬこの私が、何度試したと思っているのかね。
ローレットの情報屋と深緑の迷宮森林警備隊は、総力を尽くしてブルーベルとクオンの行方を追った。
けれど結局、一同は姿を消した者達を発見することが出来なかったのだ。
断片的に拾った情報を、情報屋達はイレギュラーズへ――敢えて尋ねた者達へ――粛々と伝えた。
拾えたものは、所詮は過去の出来事であった。
だからこのお話は、今はここでおしまいだった。
目下の最重要課題は、アルヴィオンでの決戦なのである。
「お前のせいじゃ、なかったってよ。気にすんなって」
誰かが声をかけた。
未だ自身を責め続けるストレリチアは、うつろな瞳から涙をこぼし続けている。
妖精郷をめちゃくちゃにしたのは、タータリクス少年の運命を壊したのは、ストレリチアではない。
その罪悪感も、後悔も、あるいは傲慢でさえあるのかもしれない。
けれど切っ掛けさえ無ければ、運命なんてまるで違っていたのかもしれないのに、と。
その想いを振り切ることが、どうしても出来なかった。
小さな小さな妖精は、あり得もしない『たられば』に縛られて……。
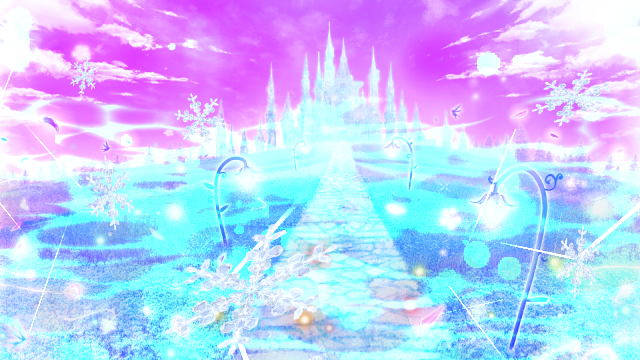
姿を消したブルーベルとクオン=フユツキは発見出来ませんでした……。
妖精郷アルヴィオンは――滅亡の危機に瀕しています……。
妖精郷アルヴィオンに決戦の時が迫っています。
2020/08/12頃、ストレリチアが街角に現れるようです……(!?)。
※サミットの結果、各国に領土が獲得出来るようになりました!
キャラクターページの右端の『領地』ボタンより、領地ページに移動出来ます!
→領地システムマニュアル