PandoraPartyProject
遂行者代行

この世は理不尽で塗り固められている。
どれだけ平和を尊び、他人に対して真摯であろうとも、大切なものを喪えば簡単に覆ってしまう。
涙を流し世界を呪おうとも、神は手を差し伸べてはくれないのだと心底思い知るのだ。
「であるならば、あらゆる手段を使い、成し遂げようではないか!」
神への信仰では何も救われない。
己を救うのは自らの行動。
あらゆる手札を行使し、知略を張り巡らせ、確実に目的を達成する。
レプロブス=レヴニールという男は正しい意味で『遂行者』であった。
聖痕など持たずとも、己の目的を達成するという強い信念を宿している。
「救うのだ! 旅人の『瘴気』に冒された人々を! この国を! ──この世界を!」
間違った歴史を修正し、今の世界は全てまやかしであったと目を覚まさせるのだ。
旅人はこの世に毒をまき散らす悪魔であるのだから。
それを根絶やしにすることは、この世を救える唯一の方法である。
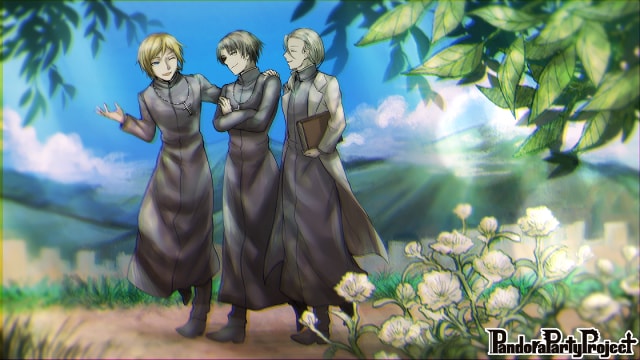
「君達なら分かってくれるだろう、アラン君、リゴール君……」
今は『亡き友』と、古くからの親友の名を呼べば、三人で過ごした日々が脳裏に浮かんだ。
もし歴史を修正出来るなら、アランや母も蘇らせることが出来るのだろうか。
ペストマスクの奥で、憂う瞳が揺れる。

アーデルハイト神学校の第二聖堂へ足を踏みいれたレプロブスは先客が居るのに気付いた。
大きな窓から垂れ込める光を受けて佇む男の姿は、まるで聖人のようだとレプロブスは表する。
銀の髪は陽光を反射して輝き、聖騎士然とした鎧を身に纏う男。
レプロブスはその顔に見覚えがあった。
「……君はパーセヴァル君か、久しいな」
「お久しぶりですレプロブス先生」
パーセヴァル・ド・グランヴィルはレプロブスの声に振り向き、青い瞳を細めた。
石床にレプロブスの靴音が響く。ゆっくりとパーセヴァルの隣に歩いてきたレプロブスは、彼と同じように大きな窓から陽光を受けた。
「在学中は色々とご迷惑をお掛けしました」
「なあに、君ほどの美貌と家柄ならば誰もが傾倒し、羨望の眼差しを受けるのも無理は無い」
羨望は裏返せば嫉妬の対象ともなりえる。パーセヴァルの在学中に起った問題に対して、当時教鞭を執っていたレプロブスは相談を受けたことがあるのだ。懐かしさで口元に笑みが浮かぶ。
されど、レプロブスはパーセヴァルの瞳をじっと見つめる。
学生時代よりも逞しく成長した大人の姿だ。
目の前の男は、『四年前の大戦で死んだ』と聞き及んでいた。
彼がもし仮に生きて居たのなら、『大罪人』である自分を警戒せぬはずがない。
しかし、パーセヴァルはあの頃のままレプロブスに笑顔を向ける。
「先生とはもうお会い出来ないのかと思ってましたよ。先生の座学は楽しかったから
……今はどちらを巡礼されているのですか?」
違和感があった。
パーセヴァルの言葉は、まるで『司祭であった頃』のレプロブスに向けられているようだった。
「各国を回っているからな。今はハウエルに居る」
「ああ。今はあの辺にいらっしゃるのですね。聖都からも近いですし今度一緒にご飯でもどうですか?」
パーセヴァルが『正常であれば』レプロブスを前にして何らかの警戒の意思が働くはず。
されど、目の前の男からは食事の誘いが出てくる。レプロブスは彼の真意を確かめるため一石を投じる。
「考えておこう……そういえば『娘』さんはどうしてるんだ?」
レプロブスの問いかけに瞳を数度瞬かせたパーセヴァルは、突然苦しみ出した。
「大丈夫か? どうした」
「は……、ぐ……、頭が」
頭を押さえてその場に膝を付いたパーセヴァルを咄嗟に支えるレプロブス。
「レプロブス先生、私は……、どうなって……娘? そうだ、私は戦っていたはず……おかしい。何かがおかしい。戦わなければ……」
やはり、何か記憶障害に陥っているのだろう。どういう経緯かは定かではないが、これは好機に思えた。
既に死亡していると目されている人間が、何の因果か自分の目の前で弱っている。
これに手を差し伸べれば何が起るのか。
――もし、パーセヴァルの力が手に入るとしたら。
非力である自分の理想を叶えられるのではないか。
レプロブスはパーセヴァルの背を優しく撫でる。
「ああ。君はまだ戦いの最中なのだ。敵に術を掛けられている。
記憶が混濁しているのではないのかね。それも敵の策略だ。惑うなら私の言葉を信じればいい」
暗闇の中で灯された灯りに縋るのは人間の性である。
「そう、ですか……不甲斐ない。レプロブス先生が居てくれて、本当によかった」
意識を落したパーセヴァルを抱え、レプロブスは「よく、おやすみ」と囁いた。
後に、パーセヴァルが『遂行者』であったことを知ったレプロブスは、その『代行』として力を行使する事となる。
対価に死を求む

聖都フォン・ルーベルグ近郊の街ロザミエラの建物は、他の街と同じように白い壁で設えられている。
窓から見える白壁とアジュール・ブルーの空のコントラストが美しい。
遠くから子供のはしゃぐ声が聞こえた。何でも無い日常がロザミエラにはあった。
動いている。生きている。未来がある。
――何て、恐ろしいのか。この先には絶望しか残されていないのに。
和装を身に纏い、布で顔の殆どを覆い隠した『ミサ』と呼ばれる女がパタリと窓を閉めた。
「なぜ、わたくしに協力してくれるのですか?」
ミサが痩せぎすの男レプロブス=レヴニールへ問いかける。
「あなた様は旅人(ウォーカー)を殺したいのですよね? わたくしは旅人でございます」
静かに問いかけるミサに対して、レプロブスは嫌そうな顔で視線を合わせず言い放った。
「協力だと? 馬鹿馬鹿しい。旅人なぞ根絶やしにすべき存在だ。貴様含めてな」
レプロブスは旅人を忌み嫌っている。ならば何故、旅人であるミサの目の前に居るのか。
それは、この会話が『交渉の場』であるからだ。
「私は旅人を殺す。しかし、己の動ける範囲は限られているだろう。貴様に力を与える代わりに貴様と貴様の主人の旅人も死ぬ。二人も殺せるわけだ。これは効率がいいと私は考える。だから、これは協力ではなく対価だ。貴様とそいつの死を以て完了する、契約にすぎない」
目的と報酬は明確であり、それ以上の干渉や情報の共有は一切行わない。
ミサが成功しようがしまいが、いずれ全員殺すのだからレプロブスには問題などなかった。
これは手段である。ミサも己が主を殺す為にレプロブスの力を借りるという手段を選んだ。
目的さえ遂行されれば、その過程など些末なことだろう。
「分かりました。ではその力をお借りいたします。対価はわたくしと美咲様の死をもって」
――さあ、あなた様に永遠の揺り籠を。苦しみ続けることのないように。
しばしの眠り

石畳の上を静かに歩いて行く人々の姿が見える。
黒衣を身に纏った聖騎士達が向かう先は、グランヴィル小隊の共同墓地だった。
先日のハウエル襲撃の際、五人の戦死者を出した小隊の面々は、誰もが沈痛な面持ちで口を閉ざす。
まだ傷も癒えぬ者も多い中、少しでも早く仲間を安らかな眠りにつかせてやりたいと、一番重傷であったライアン・ロブルスは立ち上がったのだ。
「無理すんなよ」
墓地までの道中、ふらついたライアンを支えたのは『星の弾丸』ロニ・スタークラフト(p3n000317)だ。
「ああ、俺は大丈夫だ。ありがとう、ロニ」
それよりも早く彼らを眠らせてやりたいのだとライアンは五つの棺を見つめる。

「――天にまします我等が主よ。
願わくば見守りたまえ。招きたまへ。救いたまえ。
正義を遂げた者達は幸いである。
なぜならば自ずと祝福されるためである。
それでは皆様、オルメルの福音書四章十節をお開き下さい。
聖騎士は悪魔へ言った。
『正義を脅かす者、正義を唆す者、正義を拐かす者は天より裁かれる』
悪魔は答えた。
『ならばアルタワ人(びと)に正義はあらんや』
聖騎士は答えて言った。
『人がパンを欲すれば麦をまく。これも正義でなくば何か』
生きとし生ける者がみな全て正義を持つならば、聖なる祝福を受ける。
これは麦農夫もパン職人も同じであり、そして剣と盾とによって破邪を為す聖騎士も同じ。
聖オルメルがそのように述べた一節であります」
司祭であるリゴール・モルトンは、聖典から視線を上げると粛々と述べた。
「ジェーン・スコットは勇敢な兵士でした」
そして続ける。その半生を振り返るように。
どこに産まれ、どんな人柄であり、何が好きで、何をなし、何と戦い、そして散ったのか。
モートン・エドワーズもそうだ。
レオナ・グレコも、ダニエル・ベイカーも、ルルカ・コスタだって――
次々に読み上げられていく五人の名前を『青の尖晶』ティナリス・ド・グランヴィル(p3n000302)は胸に手を当てて反芻する。
彼らの中では不甲斐ない上官であったのだろう。
もっと自分が上手く指示出来ていれば、彼らは死なずに済んだのかもしれない。
埋葬された彼らの墓碑の前でティナリスは祈りと共に謝罪を述べる。
「ごめんなさい……」

その言葉は小隊のメンバーにも届いただろう。
ティナリスの後ろに一歩近づいたニコラ・マイルズが眉を寄せてティナリスの背を見つめる。
「何でアンタが謝んのよ」
ニコラの声にその場に居たメンバーに緊張が走った。
血気盛んなニコラの事だ。ティナリスに怒号を浴びせかけても不思議では無い。
ティナリスもニコラからの叱咤を予想して振り返る。
「……アンタは良くやったわよ」
ニコラはティナリスの背をぽんと叩いた。
思いがけない言葉にティナリスの目に涙が浮かぶ。
「あの子供救って、ローレットの人達と協力してワールドイーターを倒したんでしょ?
だったら、胸を張りなさい。モートン達が命を賭けて頑張った甲斐があったと証明しなさい。
下を向くなんて許さないわよ。アンタは私達の上官なんだから。彼らの名前を覚えていなさい」
「はい……っ!」
涙を拭って、再び墓碑へと向き合ったティナリス。
己の元で散っていった部下達の名を胸に刻み、それでも青き瞳の輝きは前を向くのだ。
――――
――

「あ、みつけたよぉ」
葬儀が終わったあと、ケルル・オリオールは同室だったルルカの遺品の中から大きな箱を引っ張り出して来た。その中には様々な手持ち花火が敷き詰められている。
「ルルカ、夏の終わりに花火したいって買い集めてたんだよね。棺の中に入れるわけにもいかないし」
「じゃあ今夜、修練場でやろうぜ」
ロニの提案にグランヴィル小隊の面々が頷いた。
群青の空と瞬く星の下、手持ち花火のほのかな灯りが修練場を照らす。
次に打ち上がるのは大きな夜花。こんなものまで用意していたのかとケルルは目を細める。
「ふふ、ルルカも喜んでるね」
ケルルは同室だったルルカの明るい性格が好きだった。
しんみりした葬儀より、きっと皆がはしゃいで花火をしてくれる方が寂しくない。
「あーあ。また、そっちに行きそびれちゃったなぁ……」
何度、同室の友人を送っただろう。
ケルルはルルカの笑顔を思い出しながら一筋の涙を流した。
墓が暴かれたとの報を受けたのは、それから数日後のことだった――
※ハロウィン2023の受付が開始しました!
※天義、海洋方面で遂行者の行動が続いています――天義は対応に動いている様です。
これまでのシビュラの託宣(天義編)|プーレルジール(境界編)
トピックス
 PPP新潟オフ開催のお知らせ!
PPP新潟オフ開催のお知らせ!
2023年8月26日(土)! Re:version第二作『Lost Arcadia』
Re:version第二作『Lost Arcadia』
ティザーサイトオープン!- 【ラサ】烙印後遺症についてはこちら
 【天義】シビュラの託宣
【天義】シビュラの託宣
特設ページにて黒衣(騎士制服)が公開されています。- シリーズシナリオ(特設)一覧ページ
