シナリオ詳細
自分なんかいらないと思ったんだ
オープニング
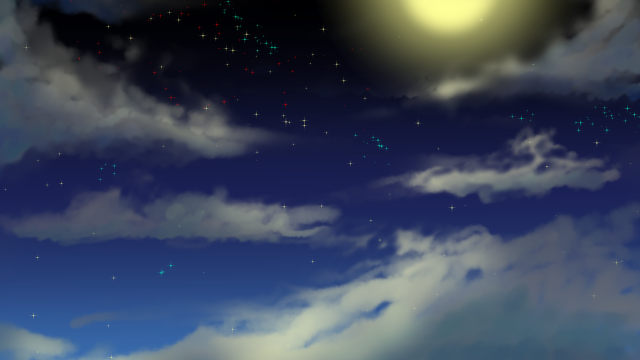
●とても簡単な仕事
ある男がいた。
名をヤクシニーという。
男は才能ある音楽家で、人を喜ばすすべに長けていた。
彼の開くコンサートでは連日客席を埋め、多くの人に好かれていた。
生来のお人好しで不器用でもあったために、貴族の仕事を安値で受けたりひとに楽曲を譲ったりしていたが、どうにもそれで満足なようで、男はあちこちで愛された。
そんな彼が自殺を決意したのが、今年の夏のことであった。
ある男の話をしよう。
名をヤクシニーという。
男は才能ある音楽家で、人を喜ばすすべに長けていた。
それゆえに彼と同日にコンサートを開いた音楽家は客を取られるといってパトロンに文句をつけたり、悪い噂を作っては流していた。
生来のお人好しで不器用であったために、難癖をつけられるような仕事を押しつけられたり、何かのミスを押し広げて音楽家失格であると報じさせるものが現われた。
それでも満足そうに仕事をする彼を恨み、彼を活動停止にする運動がおきた。
彼の作った曲が自らを侮辱しているとして貴族の娘が糾弾を始めたのだった。
比較的立場の弱いパトロンは男を切り捨てる決断をした。
言葉にはしないまでも、曲の依頼をしない、コンサートを開きたいと言っても先延ばしにする、作った曲が誰かに盗まれても知らぬ顔をする……そんなことが続いた。
仕事が生きがいであった男は摩耗し、ついに自殺を決意した。
これで終われば、ただの悲劇だったのに。
●とても難しい仕事
「ある呪いの話をしようか」
『黒猫の』ショウ(p3n000005)が水で薄めた酒を手に、裏酒場のカウンターに腰掛けている。
「ある音楽家が、別の音楽家に向けて放った呪いだ。
名は、『道連れの呪い』」
道連れの呪いとは、対象が自殺をはかることによって完成する病原菌のような呪いである。
呪いは死した魂をとらえ、死の事実を知った者たちに情報感染を繰り返し、同じように自害する衝動をもたらす。
「なぜこんな呪いがかけられたか、だって?
さあね。けれど、こっそり自害しようって音楽家にこんな呪いをかけるくらいだから……死を汚名で上塗りしたかったんじゃないかな。
彼の名前は永劫に呪いと共に語られ、死をさけるべく人々はこの情報を燃やし尽くすだろう。
それは人間ひとりの死というより、後生に残る音楽家という存在の死を意味する。
彼の徹底的な削除を、何者かが望んだんだ」
空になったグラスをなでる。
悲しい音がした。
「それを避ける方法がひとつだけある。
ここにいるメンバーに依頼されたのも、それだよ」
写真と手書きの地図がカウンターテーブルを滑った。
「彼が自害する前に、彼を殺害するんだ」
依頼人は、彼のパトロンであった。
- 自分なんかいらないと思ったんだ完了
- GM名黒筆墨汁
- 種別通常
- 難易度EASY
- 冒険終了日時2018年10月12日 21時05分
- 参加人数8/8人
- 相談7日
- 参加費100RC
参加者 : 8 人
冒険が終了しました! リプレイ結果をご覧ください。
参加者一覧(8人)
リプレイ
●『僕は条件を呑んで自分から身をひいたんだ。なのに彼女は追い出してやったんだと自慢し条件すらも踏みにじった。かつての楽園はもう彼女だけの遊び場だ』
酒場。
普段賑わう人々も、夜な夜なやってくるサックス奏者も、陽気なウェイトレスも、その日は居なかった。
陰気なウェイターと傷ついたバーカウンターと、八人のイレギュラーズだけがあった。
半分まで減ったグラスを傾ける『特異運命座標』不動・醒鳴(p3p005513)。
からんと氷の鳴き声がする。
「面倒くせぇな、嫉妬とか呪いとか……あのヤクシニーって音楽家に興味がわいたところだったのによ。人生を儚んで自殺しようって奴だ。何を聞いてもバツが悪ぃ」
「けれどそんなの、あんまりですのー……」
『悪辣なる癒し手』マリア(p3p001199)は消えそうな声でグラスを両手に包んだ。ひんやりとした滴が手のひらを通してカウンターの小さな傷にしみてゆく。
(悪意に晒されて死ぬなんてー……なんだか昔の自分を見ているようで、いたたまれないですのー……)
マリアは仲間たちのほうを強く振り返った。
「私にも、何か力になれないでしょうかー……!」
「何か、ねえ」
『メルティビター』ルチアーノ・グレコ(p3p004260)はアイスコーヒーにミルクを落として、その様子をじっと見つめていた。
じわじわと黒を侵食していく白色。やがてまざればどちらでもない色になるのに、お互いがお互いを拒むようにじわじわといびつにねじれてゆく。
「音楽を捨てれば楽に生きられたろうに、彼はできなかったんだろうね。彼は呪いに負けようとしてるんだ」
ストローをくるくると回してかき混ぜる。氷がぶつかる音が涼やかに鳴る。
「ところでさ、呪いって、誰がかけたものなのかな。パトロン本人だったりして」
「それはないでしょう」
『『幻狼』夢幻の奇術師』夜乃 幻(p3p000824)が背筋を伸ばして言った。
指先に姿の分からぬ音楽家の人形を生み出し、オルゴールの上へのせる。ころころとなり始めるオルゴール。
「仮にそうだったとして、僕らに殺害を依頼する理由がありません。ただ殺害したいだけなら呪いなどかけず暗殺を依頼すればよいだけなのです。僕らはこの殺害依頼を完全に隠匿できるわけではありませんしね」
『海淵の呼び声』カタラァナ=コン=モスカ(p3p004390)が濡れたナプキンを強く握りしめた。
千切れてしまうほど強く、血が滲むのではと思うほどに握りしめてから、手を離す。
「呪いをかけた人を探そうとしたんだよ。依頼人のパトロンさんは知らないって言うし、一番怪しかった貴族の娘って人はガードが堅くて近づけなかった」
カタラァナの様子に強い憤りを感じて、『極夜』ペッカート・D・パッツィーア(p3p005201)はグラスをすいっと撫でた。
小鳥のように清らかな音を立てて鳴る水面。
「よせよせ。いくらギルド条約があるからって、貴族相手に無茶したらどうなるかわからないぜ」
貴族の汚さや冷酷さを、この幻想で暮らしていれば少なからず経験することになる。邪魔な人間にこっそり刺客を送り込んだり何かしら痛い目に遭わせたりといったことは呼吸をするかのごとく簡単にこなす……やもしれぬ。
「今回の呪いだって、『そういうもの』かもしれないぜ」
「…………」
憤りをそのままに振り向くカタラァナ。
俺をにらんでどうするんだよと手を翳すペッカート。
「『私は名門音楽家。みんな私を褒め称えなさい。あら目障りな音楽家。活動停止に追い込んでやったわ。けれど音楽だけ残るのは目障りだから、全部消してもらいましょう。あースッキリ!』」
「よしなヨ。あくまで推測ダ」
『水葬の誘い手』イーフォ・ローデヴェイク(p3p006165)がグラスを少しばかり強く置いて見せた。
マリアが身を乗り出す。
「ヤクシニー様が音楽家として死ねば、呪いが解けるんじゃありませんのー……?」
「それは、どうなんだろうネ。これでも魔術はすこし分かるんだけど……」
イーフォは紙ナプキンにさらさらとペンを走らせた。
『呪い→自殺→情報感染』という明確な図式だ。
このうち呪いと自殺の間に斜線を引いて断絶する。
「自殺するまえに殺せという指示は、『呪いを解けないから永遠に自殺がでいないように他殺にしてしまうしかない』ということなんじゃないかナ?」
「それでもー……!」
食い下がろうとするマリア。
ルチアーノが手を翳して笑った。
「まあまあ。気持ちは分かるよ。賭けてみたい、よね? 僕もそう考えるから……僕なりの考えも話していいかな?」
ルチアーノがカウンターを指でトントンと叩いて記憶を探る仕草をした。
「たとえば毒を使った暗殺を仕掛けられたとするよね。毒にも色々あるんだけど、毒の種類と対処法を申告してきた場合は……そこから二つのことがわかるんだ」
立てる二本指。
「『過去に用いられた事例がある』『対処された事例も存在する』……今回は呪いだけど、似たようなものだよね。過去に同じ呪いが用いられていて、しかもそれを他殺によって感染を回避した事例が恐らくあるんだ。一応、この前提に嘘はないと思う。さっきも言われたけど、普通に暗殺を依頼すればいいだけのことがらに嘘を混ぜる理由がないからね。最悪言わなきゃいいんだし」
「で、方針は決まったかの?」
酒場の扉が開き、『大いなる者』デイジー・リトルリトル・クラーク(p3p000370)が現われた。
日中の逆光を背負い、独特なシルエットを揺らす。
「約束通り、ヤクシニー氏の楽曲を調べてきたぞ。今から頭にたたき込むのじゃ」
ぴらぴらと楽譜をかざすデイジー。
「殺せと言われれば確かに殺そう。じゃが、殺し方は指定されなかった。ならば……死出の旅路をせめて美しく飾るのじゃ」
もしかしたらそれこそが、この依頼の本質だったのかもしれない。
デイジーは少しだけそんな風に考えて、すぐに首を振った。
すぐには信じたくないではないか。
暗殺依頼が、パトロンから精一杯の餞別であったなどと。
●『遊び場を彼女は焼き尽くし、つばをはいて去って行った。もうあの場所にはなにもない。僕の居場所も、楽しんでいた人々も、むなしくからからと回る風車だけがある』
覚醒。
馬車がとまる感覚で目が覚めた。
ポケットから出したコインを御者へと手渡して馬車を降りる。
白いシャツと土に汚れたズボン。
音楽家ヤクシニーは青空と雲を見て、使い古した自分の革靴のつま先を見て、ゆっくりと歩き始めた。
ここに来るまでに御者と話した内容を思い出した。
馬を進める間が暇なのだろうか、御者は何度かヤクシニーに呼びかけて会話を促したが、それにまともに応えた覚えは彼に無い。
そんな一方通行の会話の中で、この場所で下りるような人はそういないと御者が語っていたのを思い出したのだ。
後ろで馬車の止まる音。
何人かが下りる足音。
こんな場所に。
ヤクシニーが振り返ると、御者席に座ったイーフォが小さく手を上げた。
「ヨカッタ、まだ間に合ったんだネ」
あえて。
個人の記憶をひもとくように観測しよう。
その場に現われたのはおよそ五人の男女だった。
イーフォ、マリア、ルチアーノ、ペッカート、幻とそれぞれ名乗ったはずだ。
彼らがどんな順番で、どんな内容を、どういう脈絡で話したのかをヤクシニーは正しく記憶していない。
芋の根をひくように記憶をたぐるなら、こんな具合だ。
――キミの音楽は、とても多くのヒトの心を動かし、そして潤いを与えた。
――こんばんはですのー、ヤクシニー様。ご機嫌は…良いわけないですわよねー……
――人の心を動かすのは難しいこと。でも貴方は音楽で心を動かした。
――僕達、貴方のパトロンの方に貴方が自殺しそうと聞いて心配で駆けつけたんです。
――本当にここで飛び降りるのか? 多分想像よりも高い崖だと思うぜ。
――キミはクリエイターとしテ、人々に音楽という娯楽の素晴らしさを教えた。音楽はキミのすべてだろうケド、逆に言えば音楽もキミを欲していル
――この土地を離れ、一からやり直しをしませんのー……? このまま死んでは、もう何もできなくなってしまいますのー……! 音を聴く事も奏でる事も、誰かの笑顔を見る事もー……!
――嫉妬による憎しみもあっただろうけど、それ以上に人々に笑顔を届けることができた筈。凄い人だね、本当に。
――それにここには後悔と絶望と憎悪の悲鳴しか聞こえない。キミはその一部になりたいっていうのかよ。
――作りたい音楽があるんだろウ。いま死ぬのは、音楽と永遠に決別するということダ。
――音だけではなく可能性すら自分の意思で棄てるのであれば、貴方は音楽家としてはもう既に死んでいますのー……! でしたら、音楽家ではなく一人の人間としてー……! 生きてみてはもらえませんのー……!?
――自分の名を捨ててでも、貴方の愛する音楽にしがみついてほしい。
――確かに俺にとってはいいハーモニーだ。まぁ、あんたも死んでからも永遠に音楽の一部になれるんだから悪い話でもないのかもな。でももっといい音楽を知ってるんじゃないか?
――天国とやらがあるんだとしたら、そこには自殺したらいけなくなるんじゃなかったか?
ヤクシニーは彼らの話す内容にどう回答したのか、ヤクシニー自身すらよく覚えてはいない。
五人の男女が、今から自害するつもりであることを知っていて、それを止めようと考えていることだけは、ヤクシニーにも分かった。
皆そう言う。ヤクシニーはたしか、そんな風に思ったのだと記憶していた。
つらければ死ねと述べる者はそういない。であると同時に、自殺を止めようとする人間の前で死ぬことができるほど、ヤクシニーは強くなかった。
自殺とはいえ人間ひとりを殺すことは、彼にとってとても重く困難な作業だった。
いや。
そうだ。
ひとつだけこんなことを言ったはずだ。
「私は、音楽家として死んでおります。もう、生きていたくはありません」
風に揺れる草。
帰りの馬車を見知らぬ男女と待つのは気まずいと、その場を歩いて離れようとしたヤクシニーを、『cock-a-doodle-doo!』という不思議な呼び声がとめた。
「よ、ヤクシニーさん。パトロンさんが気にしてたぜ。死にそうだってよ」
醒鳴がギターケースを背負ってやってきた。
ヤクシニーには彼が、遅れてきた六人目に見えた。
「なぁ、俺はあんたに習いたいことがあってきたんだ。ちょっと付き合ってくれよ」
ギターを取り出して『さあ』という顔をする醒鳴に、ヤクシニーは泣きそうな顔で『やめてください』と後じさりした。
その理由や根拠を説明できるような表情では、もはやなかった。
醒鳴に連れ添う形でやってきたカタラァナの目には、ひどいショックや苦しみを感じる顔に見えた。
胸に刃を突き立てられたような、思うだけで指が震えるような、それはそれは苦しい出来事が、過去にあったのだろうと察するに十分な顔であった。
ちょっとでいいんだと頼み込んでみた醒鳴の肩を、カタラァナはそっと叩いた。
肩を落とし、ギターを下ろす醒鳴。
幻とペッカートが、ヤクシニーを囲むように立った。
「貴方の存在から貴方の曲すらなかったことにしようとしている方がいらっしゃいます。そんな方に覚えがありませんか?」
びくりとヤクシニーの肩がゆれたのを見て、幻は心当たりがあることを察したが……。しかしヤクシニーは『わかりません』と首を振った。
「こんなことになったのはキミのせいじゃないだろう。同じ絶望を味あわせてみたくはないか?」
続いたペッカートの問いかけに、ヤクシニーはひどく悲しい顔をして首を振った。
自分で何をいったのかよくわからないという顔で、けれど恐らく本心で、彼は消え入るようにこう言った。
「それでは誰も幸せになれません」
「なら、やるべきことは一つじゃ」
デイジーが腰に手を当てて立っていた。
「『道ずれの呪い』を知っているかの。お主が自害をすればその厄災がお主を知るもの達にばらまかれる。故に妾達はお主が自ら命を絶つ前に殺しに来た、と言うわけじゃ」
デイジーのいう『妾達』がイーフォやカタラァナをも含んでいることに気づいて、ヤクシニーは慌てた様子で振り返った。
呪いのことなど初耳だというリアクションだったが……。
「お主は被害者じゃ。お主をこの境遇に追い込んだ者を、妾達を恨む権利がある」
まるで追い詰めるように一歩、デイジーは歩み寄る。
「お主は良い音楽家じゃった。しかし、残念なことに妾はお主の演奏を聴いたことが無い。故に、これは人づてに聞いたことじゃ。音楽家ヤクシニーの演奏は素晴らしかったと。お主がコンサートを開いた街で直接聴いた事じゃ」
これが事実であったかどうかの裏付けはない。もとい、必要ない。
「お主の奏でた音楽は今を生きる人々の心に残り続ける。それをつまらぬ呪いなどで貶めたくは無い。お主の演奏を思う時の、人々の笑顔を妾は汚したくない。故にここで妾がお主を殺す」
デイジーが懐から取り出したのは、ナイフでも銃でも注射針でもなく、一冊の楽譜だった。
「それで、みんな幸せになれるのですね」
ヤクシニーはそんな風に言ってうつむいた。
「呪いをかけた人は残念がるでしょうけれど、私が死んだと聞けば、喜ぶでしょう」
まるでそれが救いであるかのように。
デイジーたちは首を振って、それぞれの楽器を取り出した。
「聞いて貰うぞ。最後の演奏会じゃ」
●『僕は負けたのだ。彼女に、彼女を取り巻くものに。そしてなにより僕自身に。だから僕は負けを認めず他者にすがりつく亡者と化す前に、僕自身を焼却することにした』
宙に浮く鍵盤を優しく叩きはじめるカタラァナ。
デイジーとルチアーノがゆるやかにバイオリンをひきはじめ、醒鳴はギターを奏で始める。
幻は目を瞑って生み出したハンドベルを鳴らし、マリアはスティックを持って同じく幻が作ったドラムを小刻みに叩き始めた。
ホルンを吹き鳴らすペッカート。
ハーモニカを鳴らすイーフォ。
彼らの演奏会は当事者であるヤクシニーを中心に、一曲だけを奏でて終わった。
「さよならヤクシニー。キミの音楽、ステキだったヨ」
「妾たちの歌で安らかに眠れ」
「せめて最後は、音楽でね」
曲が終わった頃、ヤクシニーは仰向けに倒れたまま動かなくなっていた。
彼が最後に何を思ったのか、何を思い残したのか。
誰にも分からぬまま、隠されたまま。
死体がただ、そこにはあった。
ある後日談を話そう。
ヤクシニーが死亡した報告をうけたパトロンは、ただ黙って報酬の金だけをよこして消えた。
その数日後に、ある貴族の娘が自分のためだけに開いた演奏会の最中刺し殺されたと言うニュースが舞い込んだ。加害者はあのパトロンであり、直後に首をはねられたという。
そのニュースを聞いて、誰かが言った。
ずっと疑問だったこと。
『なぜこれだけの依頼に八人も雇ったんだろう?』
その回答かもしれないこと。
『もしかしたら』
『あのひとはー……』
『ヤクシニーの』
『最後を』
『飾ってやりたかったのか?』
『自分にはできないから』
『せめて、僕たちを使って』
それが真実であるかどうかもわからぬまま。
隠されたまま。
事件は日常のなかに溶けて消えていった。
町のストリートミュージシャンが、ヤクシニーの曲を演奏している。
成否
成功
MVP
なし
状態異常
なし
あとがき
――mission complete
true end 1――『せめてものはなむけ』
GMコメント
音楽家ヤクシニーを『殺害』すること。
これが依頼の要点です。
殺害に至るまでの経緯は指定されていません。
・自殺までの経緯
あくまで予測ですが、自殺の名所と知られる崖へと向かったことが分かっています。
馬車駅から徒歩で崖へ向かい、身を投げるつもりでしょう。
PCたちは現地に赴いて馬車で先回りし、最終的には彼の殺害を行ないます。
・ヤクシニーの状態
生きがいであった仕事を奪われ、抜け殻のようになっています。
鬱も酷く、他人と楽しく会話をしたり社交的な気分になるのは難しいはずです。
彼は音楽家として生きてきて、身体は全く鍛えていませんでした。
そのためさして抵抗がなければ『通常攻撃1回』で死亡まで持って行くことができます。
仮に抵抗されてもほぼ苦労なく彼を殺害することが可能でしょう。
・呪いについて
『道ずれの呪い』はかなりアングラなもので、仮にこの場を生き延びてもまた別の手段で自害をはかるように衝動が続くことになります。
今回がコトを直前で終わらせるチャンスなのです。
Tweet