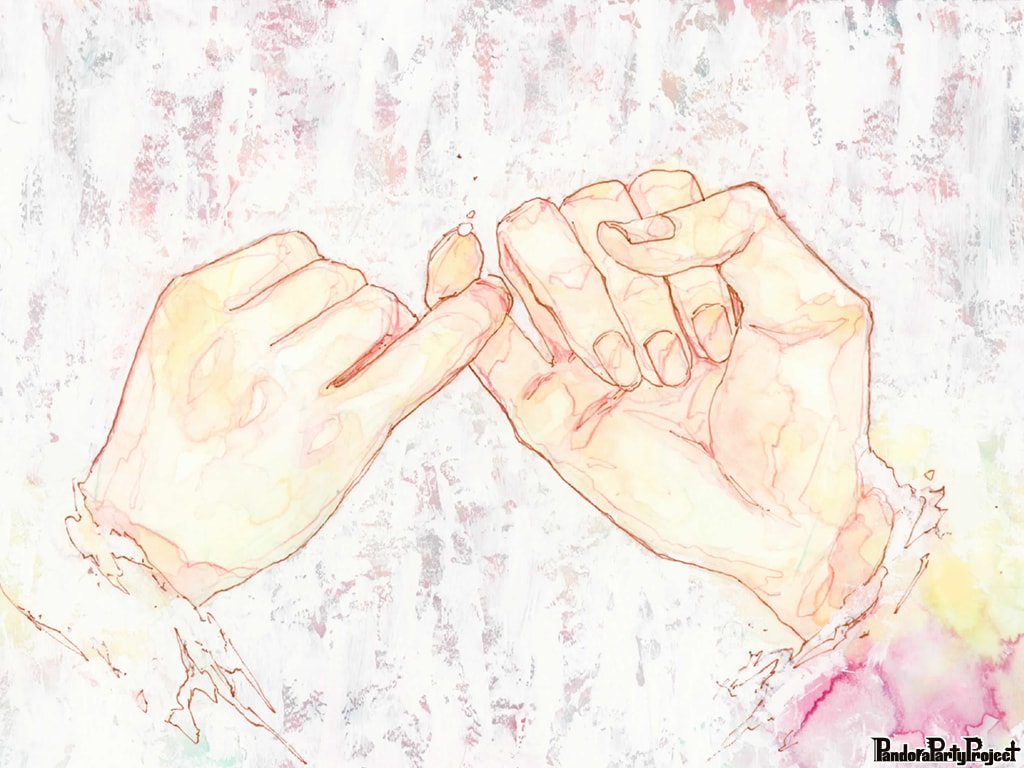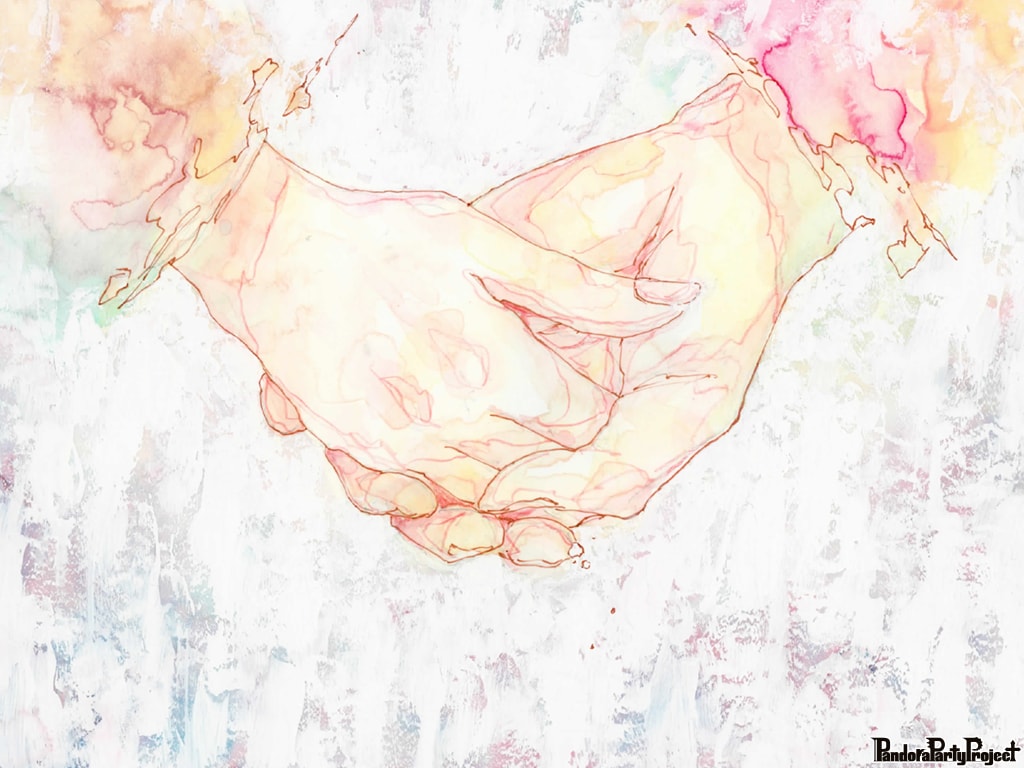SS詳細
2022年2月3日
登場人物一覧
――現在も大規模災害からの復興は続いております。
希望ヶ浜中央駅に存在する大型ディスプレイは震災復興の為の対応策についてを流し続けた。連日連夜ニュースは『大規模災害』の話ばかり。気が滅入るとSNSでは苦しげな声が絶えず流れる日々だ。越智内 定は『大規模災害』が地震や台風と言った自然災害では無く突如として襲来した竜種によるものであると知っていた。その現実を直視出来るようになったのは定にとっては大きな進歩であったのかもしれないが青年には身に余るとしか言いようのない出来事であった。
至近に見た竜の強大さ。その身を切り裂くなけなしの一歩。誰かに背を押された事は覚えている。だが、それだけだ。定は思い出すだけで身の震えが止まらなかった。帰宅してからというものの、最初の頃は部屋で一人、塞ぎ込み頭を抱え続けたがそれすら恐ろしくなった。部屋で一人で佇むことは『越智内 定』というちっぽけな個である事を実感させられるように感じたからだ。大学は休校状態で出欠も取られない。それを良しとして定はぼんやりと街行く人々を眺めていた。
駅前通りのベンチに腰掛けて、街行く人々を眺め続ける。それだけで自分が自分で無いような気がしたのだ。自分にとって多くの誰でも無い誰かに紛れて居れば、彼らからは定さえも大勢の中の誰か一人だ。ジャバーウォックを倒す為だと身を擲ったイレギュラーズじゃない。ただの、男なのだ。
――そう、それでいい。あんなに怖い思いをするならば大勢の内の一人で良いでは無いか。あんな怖い思いをする必要ない。
定は恐怖に苛まれ己の保身ばかりが脳に過っていた。あの肌寒い初冬の日に海へと自転車で行ったことも、大切に財布の中に入れておいたピアスの片割れも。
全てが全て、定の脳内からは消え失せていた。
「定くん」
そうやって呼ぶ彼女の声だって――……
「……な、じみさん……?」
「うん。そうだよ。心配した。だってメッセージも返信が無かったし……心配したんだぜ? これでも」
慣れた様子で隣に腰掛けるなじみは何時もと変わりない。ジャバーウォックが訪れた事さえも知らないような『いつも明るくて優しいなじみさん』の顔をして、定くんと呼びかける。
「……ごめん。まあ、その……頑張ったさ。生きてたから、それでいいだろ?」
「謝らなくっても良いよ。メッセージのことは気にしてないし。生きてて良かった。怪我したんだよね?」
「まあ」
「お大事にね。ちょっと探しちゃったぜ。どこにも居ないからさ」
どうしたのと覗き込むなじみに定は首を振った。今は彼女の事を考えられなかった。定が感じた恐怖をなじみは実感しない――否、していたとしても教えてはくれないのだろう。ただ、なじみは定によりそって、怖かったよねと笑うだけなのだ。
「なじみさんも、怖かっただろ? ……不安、だっただろ」
「うーん、そうだね。うん。怖かったけど、もう」
「もう? そんなに簡単に忘れられるようなことじゃなかったじゃないか。竜だ。現れたのは竜なんだよ。
伝説だ、御伽噺だなんて言われた奴が飛来して、蹂躙して、命が奪われて。それでも過ぎ去ったねって言うのかい?」
隣に座っていたなじみのめが見開かれた。定はそれでも捲し立てる。彼女と同じ気持ちに慣れない事が歯痒い。感じた恐怖を済んだことだと流されることが恐ろしい。
何時だって笑って手を引いてくれた彼女が――今は、はりぼての人形のように思えて酷く苦しくなった。
「僕は怖かったさ。あいつの前に飛び出して、君を救わないと……この場所を護らないとって思ったんだ。
沢山の人に手を貸して貰って、一人じゃ何も出来なくって、傷だらけになって、我武者羅で、でも、怖かったんだよ。
僕はもう、あんな思いしたくない。僕じゃ無くったって良かった。僕じゃ無くったって誰かが為したんだ。僕である必要は……」
「定くんだから、出来たことだよ」
「簡単に言うよね。なじみさんを護りたいと思ったさ。けど、結局ちっぽけな僕だけじゃ何も出来なかったんだ」
「そんなこと」
「そんなことある。なじみさんは僕が戦っている所なんて見ちゃいないだろ? あいつと真っ向から向き合った恐ろしさだって感じちゃいないからそんなことを言えるんだ!」
定は勢いよく立ち上がった。腰掛けたままのなじみを見下ろして、勢いを緩めぬままに捲し立てる。街行く人々の視線も、気にはならなかった。
「なじみさんに僕の恐怖は分からないさ!」
「――……よ」
ぽつり、と呟かれた言葉に定は「え」と声を漏した。なじみの若葉の色の瞳に滲んだ感情は、今まで彼女から見たことがないもので。笑っているわけじゃない。怒っている。怒りの滲んだ眼光が苛立ちばかりを溢れさせる。
「分からないよ! 分かるわけがないじゃない。私は、皆のように戦えやしない。此処から飛び出すことだって出来やしない。
励ましも、助けもいらないのなら君がしたいことをすれば良いじゃない。私は君とは違う。私は君じゃないから君の事なんてちっぽけも知らない! ……知らないんだよ」
ぐい、と何時も被るベレー帽の位置を調整してからなじみは「もう知らないんだ」と呟いた。定は「バイバイ」と一言だけ漏して立ち去っていく背中をぼんやりと眺めていた。
喧嘩、と呼べるのだろうか。弱さを曝け出した自分に彼女が幻滅しただけなのかもしれない。それでも、あの時ばかりは間違ったことを言ったつもりは無かった。
勿論彼女だってそうだ。越智内 定が感じた恐怖は越智内 定のものであり、なじみには理解出来ない。そんな当たり前のことを突きつけられただけで言葉が出なくなった。
『なじみさん』という女の子は何時だって自身を受け入れて、笑っていてくれると思っていたのだ。手を差し伸べて、こっちだよと迷いから救い出してくれるような――そんな、都合のいい女の子であったからこそ、そんな都合の良さを捨てて欲しかった。対等に、ただ、話したかったのだ。
「怖かった。駄目かと思った」と弱音を吐いて欲しかった。同じ苦しみを味わったのだと感じていたかった。それでも、彼女は『なじみさん』を徹底していたから。
「どうして……」
定は俯いてその場にへたり込んだ。立ち去ったなじみを追い掛けることも、aPhoneに未読のままで残し続けた彼女のメッセージも、何もかも。
全てどうすることも出来ない自身と彼女との隔たりを思い知らされるようで酷く狼狽した。
時刻が移ろえど、定はその場に座り込んでいた。動く気力さえ無かったのだ。夕日が陰り、街灯はぼんやりと周囲を照らす。吐く息は白く悴む指先に構うことも出来ずに呆然と足下だけを見下ろした。
「どうしたの?」
見詰めていた地面に、ハイヒールの爪先が入り込む。伺うように屈んだのだろうか。頬を擽った髪先は淡いラベンダー。穏やかな声音にも聞き覚えがあって定は唇を噛みしめた。
「風邪、引いちゃうわよぉ? あ、誰かと待ち合わせ……って訳でもなさそうよねぇ。
もしも暇なら珈琲でもどうかしら。買い物帰りで足が疲れちゃったの。近くのカフェの新作が飲みたいのよねぇ」
「……アーリア先生」
そろそろと顔を上げれば、『さっきまで見ていた』緑色とはまた違う、深く優しい常盤の色が細められた。「やっとこっちを向いてくれたわねぇ」と笑ったアーリア・スピリッツに手招かれ、おぼつかぬ足取りで向かったのは駅前に存在したチェーンのコーヒーショップ。其れなりに客の姿は見られたが、端のテーブル席は空いていそうだ。
「何にする?」
「え、と……あ、自分で……」
「お姉さんのおごりよぉ。休憩に付き合って貰うんだもの。私は限定のチョコレートホイップラテで」
慣れた様子で注文をするアーリアを眺めながら定は「同じものを」と何も考えずに注文をした。席を取っておいてと荷物を渡され、俯きながらテーブル席に腰掛ければ、先程まで定が座っていたベンチを見下ろすことが出来る。雪もちらつきそうな寒さと店内の暖房による温度差で水滴の付いた窓硝子が景色を霞ませた。
ソファーにだらりともたれ掛るように息を吐いてから、天蓋の洒落たランプを眺める定に「お待たせ」とアーリアは微笑んだ。ケーキセットを注文した彼女は「教師って流行には手を出しておかなくっちゃよねぇ」と笑いながら新作のホワイトチョコレートケーキに乗っていたハートを摘まみ上げる。
「それで、どうしたのかしら。あんな寒いところで座り込んでて」
「……いや、その……」
定のチョコレートソースとホイップクリームで甘ったるさを主張する珈琲に小さなハートのチョコレートを差し入れたアーリアは首を捻る。
誰から見たって情けがないほどに落ち込んでいたのだろう。定の答えをただ、待っているわけでもないアーリアはケーキにフォークを差し入れながら嘆息する。
「……大変な仕事だったわよねぇ。ジャバーウォックが来て、希望ヶ浜はまだまだ復興途中だもの。
私達は成し遂げたんだわって、この変わったようで変わらない日常を見ると安心するの。希望ヶ浜は、まだ元気に時を刻んでいけるのね」
「そう、ですね」
「だからね? 越智内 定って頑張った男の子が居なければ街の平和は無かったかも知れないのよ。怖かったけれど、この平和が貴方の頑張りを象徴してくれているのだもの!」
にこりと微笑むアーリアに定は唇を噛みしめた。彼女は何時だって諭してくれる、道に迷えば助けてくれる。不安を解消して手を差し伸べてくれる。
……優しい、世界で一番頼れる『大人』で、先生で、先輩で――そんな彼女が頑張ったと認めてくれるのならば、自分は何かを為せたのかもしれない。
「なじみさんと、喧嘩して……僕は、あの竜が恐ろしかった。情けないかも知れないけれど、もう、あんな怖い想いなんてしなくて良いと思った……」
「そうねぇ、誰だって、あんな怖い想いはしたくは無いもの。けれど、綾敷なじみって女の子を護りたいって頑張ったのは他でもない越智内 定っていう男の子でしょ?」
「そう、です。けど……けど、なじみさんは済んだ話だから気にはしないって。僕の怖さを理解してくれなくて言い、なじみさんの弱さを、不安を見せてくれないことが――」
は、と定は息を呑んだ。そうだ。自分の弱さも、自分の拙さも全て知っていた。自分に呆れていた訳じゃない。
綾敷なじみという『夜妖憑き』の少女のことを定は何も知らなかったのだ。彼女の弱さも、彼女の苦しさも、不安も何もかも語ることは無く明るい女の子に徹している。
これだけの恐ろしいことがあったのに、頼って貰えない不甲斐なさが苦しかった。彼女と『半分ずつ』分け合えないまま、不安に押しつぶされていく自分が情けなくて苦しかった。
「僕は梲も上がらぬ日々を過ごしてた只の高校生だった。オチもなけりゃ、ヤマもない、そんな日常を過してただけだったんです。
……そんな僕があんな奴と戦って、追い返したんだ。怖くないわけない。はは、そりゃ、そうだ……怖くない奴の方が少ないんだ」
「そうよ。誰だって、死ぬのは怖いもの。けど、それをあの子にぶつけたって意味はないわよねぇ……。
イレギュラーズになったんだもの、いつかは覚悟しないといけないの。大切な人の日常を守る為に、戦わなくっちゃならないって」
アーリアの脳裏に浮かんだのは穏やかに微笑むふわふわとしたうんと年上の尻尾の恋人だった。彼の日常を守る為ならば戦える。恋する女は強いのだと揶揄い笑うアーリアに定は「眩しい位だ」と呟いた。驚くほどに眩くて、定は頭を抱えそうになる。
ソファーにもたれ掛って嘆息する。恐ろしさから逃れようとすることばかりだった。屹度、アーリアだって恐ろしかったのだ。
定が感じた恐怖をアーリアも同じように戦場で感じていた。それは誰だってそうだったのかもしれない。特別なことではない。当たり前のような生存本能の警鐘はあの巨大なる竜を前にして崩れゆく街の中で確かに鳴り響いていたのだ。
「先生、僕は――」
なじみさんと話してみる、と言葉を紡ごうとし、定は息を呑む。カフェの入り口で周囲を見回しているのは先程まで目にしていた少女の姿だ。
驚愕してからアーリアへと視線を移せば意地も悪く美しく笑った彼女は「ちゃんと話しなさいな」と柔らかに笑った。
「お姉さんを信頼してくれるのはいいけれど、ここから先は二人の話だものねぇ?」
「いや、でも――」
「だって、と、でも、を積み重ねたって得られる未来は無いのよぉ」
楽しげに声を弾ませてからアーリアは立ち上がり「こっちよ!」と手を振った。気付いたなじみがぱあと表情を華やがせて駆け寄ってくるその一歩一歩に定は沙汰を待つ罪人とはこの様な感情を抱くのだろうかと小さくなって俯くことしか出来なかった。
「アーリアちゃん? ……定くん……?」
「ふふ、来てくれたのねぇ。ごめんなさいね。用事があるのは――」
ちら、と定を見遣ったアーリアがaPhoneを一瞥するような仕草を見せる。『仲直りをなさい』とアーリアが仕立ててくれた舞台なのだと察してから定はごくりと唾を飲み込んだ。甘すぎる珈琲の味わいさえ忘れたように腔内が乾燥していく。それでも、此処で逃げていれば何時までも向き合えない。
『次の11月の約束』も、『君と交わした言葉の全て』が無駄になる事を良しとしていて何が男だ。越智内 定――!
定はゆっくりと顔を上げる。情けない顔をしている自覚はある。だが、それを気にしている暇は今は無かった。
「なじみさん、君と話したいことがあるんだ」
震える言葉が、意を決して確かなものとなる。目の前に立っていたなじみの肩をぽんと叩いてからアーリアは「それじゃあ」と手を振って歩いて行く。
「え、アーリアちゃ、」
振り向いたなじみはアーリアを追い掛けることも出来ずにすとんとアーリアが座っていた位置に腰掛ける。何時もより緊張したように息を呑み、定を眺めるなじみは「ええと」と紡ぐ。
「さっきはごめんね。ついカッとなっちゃって。……定くんは怖かったから誰かに聞いて欲しかったんだよね?」
「違うよ。違う。怖かったし、僕は弱かったけど……君とそれを共有していたかったんだ。君の感じた不安や恐怖を僕が知れないことが恐ろしくて」
「私の?」
「そう。僕は、君を護りたくって、頑張った。けど、君にとってはその頑張りだって過去のものだって思うと――」
違うと立ち上がって定に詰め寄るように言葉を紡いだなじみに定は首を振った。だが、なじみからは掛ける言葉も無い。
自分の恐怖をひた隠しにして笑ったことが、彼を不安にさせたのだから。
「なじみさんは、僕達に死んで欲しくない、怪我をして欲しくないって言うだろ?
それは僕だって同じさ。僕もなじみさんに怪我をして欲しくない。……君は君を顧みないから、僕は不安になるんだよ」
弱いって笑ってくれても良いと定は情けなく笑う。弱い男だとからかってくれても言い――それでも、知っていて欲しかったから。
「ううん、私こそ心配掛けてごめんね」
「いつだって心配しているさ。……だから、約束して欲しいんだ。
なじみさんが困ったとき、辛いときは半分こして欲しい。なじみさんが苦しいときも悲しいときも、僕が君の力になれるように」
約束、と念押すように小指を立てればなじみはおそるおそると言葉も無く其れに触れる。不安げな、緊張の滲んだ瞳は定の指先をじいと眺めてから絡められた。
「努力するよ」
「努力なんだ?」
「努力だよ。だって、慣れてないもん」
にい、と笑って絡めた指先を離したなじみの手を追い掛けるように定は意を決したように手を繋ぐ。定からは初めての手を繋ぐ行為になじみは驚いたのか指先をびくりと跳ねさせた。
彼女の驚いた顔を見詰めてから、定ははあと大きく息を吐いた。ああ、情けない。斯うした行動の一つだけでもどうして緊張するのか。
彼女から手を握られて心臓が跳ねる。彼女と自転車に二人乗りをして触れた体温だって、心が躍った。何時だって彼女が与えてくれるばかりだったから。
「最高の誕生日プレゼントだよ」
「約束が? 私から定くんに何も渡せてないのに。……今度、一緒に選びに行こうよ。定くんの好きなものを買ってあげる」
手を繋いだままそう笑ったなじみに定は「何時にしようか」と小さく頷いて微笑んだ。外れかけた釦を掛け直すのは優しいことでは無かったけれど、彼女と分け合えるなら恐ろしさだって屹度乗り越えられる。心に過る恐怖はまだ多くあるだろう――それでも、足を止めている場合ではないのだと彼女と手を繋げば実感が湧き上がるから。
「……少し歩いて帰らない? イルミネーションが綺麗なんだよ」
定から繋いだ手を、更にぎゅうと握りしめてなじみは笑った。二人で、店の外に出れば寒々しい空気が頬へと触れる。
「私は弱音を吐くのも、悲しいことを伝えるのも得意じゃないから君が気付いてくれると嬉しいな。
悲しい時に、真っ先に君がやってきて大丈夫って笑ってくれれば怖いことだってへっちゃらになれるんだよ」
――君の声が雑踏に混ざり征く。イルミネーションに足を止める人達と混ざり合って、誰かにとっての誰かでしかない僕たちの陰が伸びた。
繋いだ手の心地よさと、『半分こ』のぬくもりがもう離れないで居て欲しいと願うように。