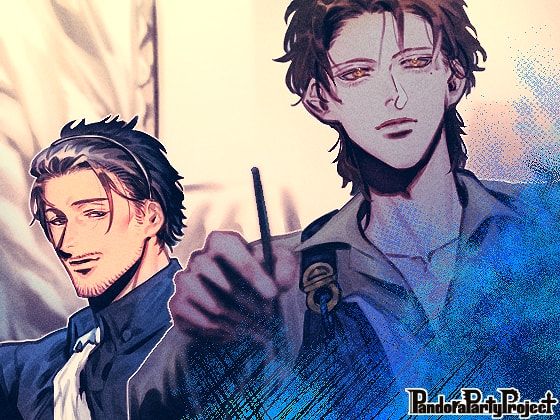SS詳細
エモーション・エモーション
登場人物一覧
●
ローレットの情報屋は忙しい……かというと、割とそうでもない。
情報が入れば忙しいが、そうでないときは各々自由に過ごしている事が多い。グレモリーは主に絵を描いていた。本当は自分のアトリエで描きたかったのだけれど、いつ依頼人が飛び込んでくるか判らないと考えれば、ローレットで描かざるを得ない。
流石に色塗りは家でやるので、ラフをざくざくと書く。思い付いたものをただそのままに、己の感性の赴くままに描く。
そんな時、靴音がグレモリーの傍まで来て、そして止まった。グレモリーはぼんやりとした顔を上げて、其の主を認める。
「グレモリー。……大丈夫かな?」
「……君はベルナルド」
「ああ、そうだ」
ベルナルド=ヴァレンティーノ。特異運命座標でありながら絵筆を握る男、だとグレモリーは記憶していた。いや、絵筆を握る男が特異運命座標になった……という方が正しいのだろうか。
「何か用かな。依頼?」
「依頼……そうだな、提案だ。いつも此処にいるのを見かけて、気になっていたんだが……気晴らしに外に出て書いてみないか?」
「……」
其れは純粋に、ベルナルドの好意だった。画家が時折陥る精神状態を、ベルナルドは誰よりも知っている。そんな時どうすれば良いかも、一応。
グレモリーがいわゆる良くない精神状態――スランプに陥っているという訳ではないが……彼は常々グレモリーを心配していた。理由は彼の描く絵にある。
――感動がない。
それがグレモリー・グレモリーという画家に対する世間の評価。見る目のないものは称賛するだろう。技術はあるのだ。技術はあるが、そこに熱情がない。例えばベルナルドが一筆一筆に込める、狂気めいた意志が――絵から伝わってこない。
其れは悲劇だ、とベルナルドは思う。何も思わず筆を執る画家などいない。冷たい心で絵なんて描けない。必ず其処には熱情が、グレモリーにだって熱情が、……あるはずなのに。其れが誰にも伝わらないのは、悲劇だ。
「……」
グレモリーは沈黙している。彼の肌は白く、どれだけ室内に篭っているのか想像に容易い。室外を嫌う性質かもしれない。ベルナルドは根気よく、グレモリーの返答を待つ。
「……君の」
グレモリーの返答は、意外なものであった。
「君のアトリエが、見たいな」
●
「余り人に見せられるようなところではないんだが……」
「構わない。きっと僕の糧になる。何しろ僕は、余り“普通の”画家と交流を持ったことがない」
グレモリーの返答に、ベルナルドは苦く笑う。普通の画家か、と問われると、そうではない気がするからだ。けれど、グレモリーの友人には、魔術で人からインスピレーションを得るという特異な画家がいる。そんな依頼があったと記憶している。ならば彼らに比べれば、自分は普通の範疇に入るのだろう。
「――これは……」
グレモリーは息をのんだ。アトリエの中は……聖堂さながら。大きいものは宗教画が多いが、肖像画に風景画、おおよそ絵画と呼ばれるだろうものがそのアトリエには詰まっていた。
「君は天義の出身だったね」
「ああ。……宮廷画家が夢だった」
もう無理な話だが、とベルナルドは絵の具の跡が残る床を見下ろす。――天義でその筆を振るい続けた彼は、“どういう訳だか”聖女に冤罪を着せられ、絵画の大舞台から姿を消した。
夢を諦めたかと言われれば、イエスと答えるだろう。だって自分は、罪を着せられたのだから。真実でなくとも、其の“傷跡”がある限り、宮廷画家という座には届かない。
しかし――其れでも。ベルナルドの胸には夢が燻り続けている。筆を折れなかったのは、今でも絵を描くのは、きっと其の夢が自分を突き動かしているからだ。
「……君は、青が巧いね」
黙ってアトリエの絵を見て回っていたグレモリーがぽつりと零す。其れは海の絵だった。海洋だろうか、砂浜から書かれた其のシンプルな絵画は、シンプルだからこそ素晴らしい。透き通るような青、波の白、広がる空の色――青を多く使うこの絵にこそ、ベルナルドの真髄がある。グレモリーはそう感じた。
「僕は青が苦手だ」
「そうなのか?」
「そうなんだ。青は溶かし方が難しい」
「確かにな。薄すぎても濃すぎてもいけない。この海の絵は苦労したんだ。油断するとすぐ――平たくなる」
「だろうね。ところで、イーゼルとキャンバスを貸してもらえるかな」
「描くのか?」
「うん」
言葉少なにベルナルドからキャンバスを受け取り、イーゼルを組み立てると、グレモリーは椅子にも座らず、持っていた鉛筆で線を取り始めた。
自分の絵を見て“描きたい”と思ってくれたのか。其れがベルナルドには嬉しかった。同時に、そう感じて貰えないのがグレモリーという画家なのだろう、とも。
――自分にできる事は何か。
やっぱり其れは、“描く”事なのだろう。ベルナルドもイーゼルと白いキャンバス、そして椅子を持ってきて、鉛筆で線を取り始めた。題材は、目の前の画家。
●
イーゼルとキャンバス、そして筆から絵具から顔料まで、グレモリーは借りて借りて描いた。申し訳ない、とは彼は言わなかった。
彼には情熱がある。ベルナルドは確信している。「今描かなければ全て腐る」とグレモリーは判っているからこそ、借りてでも描いたのだ。
「――出来た」
笑みを浮かべて、グレモリーは言った。まるで難しい工作を完成させた子どものような笑みだった。
「ああ、俺も出来た」
ベルナルドは己が描いた「グレモリー・グレモリーという男」を見て、満足げに頷く。其処には確かに情熱があり、絵に対する執着があり、何よりも“楽しくてたまらない”という感情があった。
「グレモリーは何を描いたんだ?」
「多分、宗教画」
イーゼルをずらしてグレモリーが見せたのは――少女の姿だった。金髪の少女が窓際で、祈りをささげている。陰影には青が使われており、何処か海の底めいた空気すら感じられた。
――……嗚呼、とベルナルドは息を吐いた。グレモリーの絵には、感情があった。けれど、何の感情なのかが判らない。これが彼の患う病魔なのだとベルナルドは知る。
何かを感じるのに、何か判らない。何かあるはずなのに、何なのか判らない。これを人は「感動がない」と呵責なく言うのだと。
あんなに情熱的に筆を執る画家なのに、――いや、だからこそか。そんな時しか感情を表に出せない彼だから、人に伝える感情を持たないのかもしれない。
ベルナルドは祈りにも似た感情を抱く。グレモリーがもっと感情を知られたらよいのに、と。人に渡せるほどの感情を、彼が得られたら良いのに、と。
「君は何を描いたの?」
そう問うグレモリーの表情は、常通り無表情ではあったが――其の瞳はプレゼントを渡された子どものように、きらきらと輝いていた。
彼は何というだろうか。喜ぶだろうか、驚くだろうか。ベルナルドはそっと、キャンバスをグレモリーに向けて――